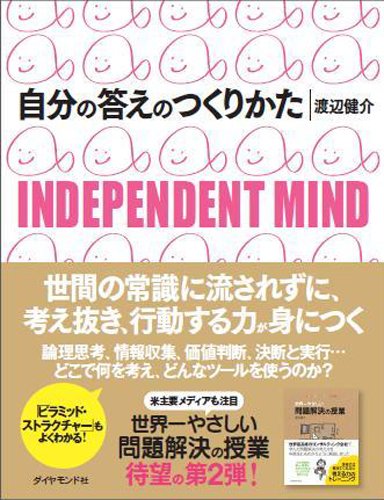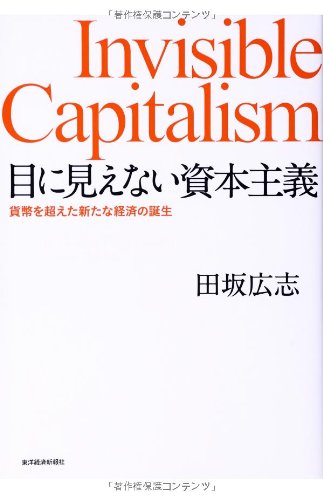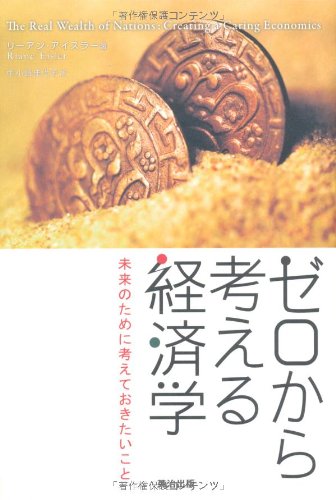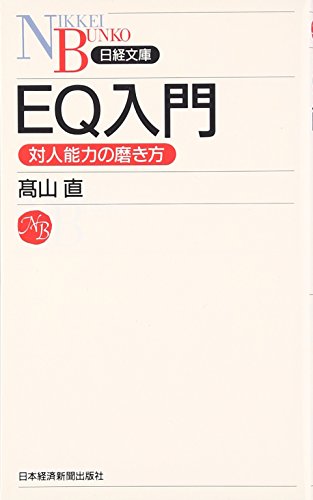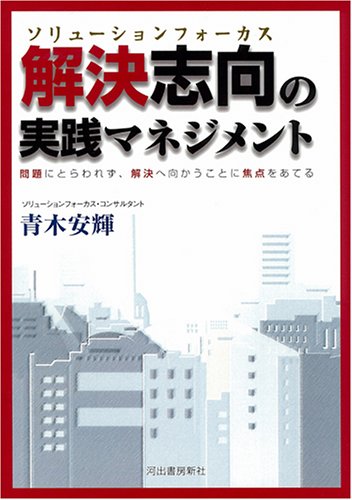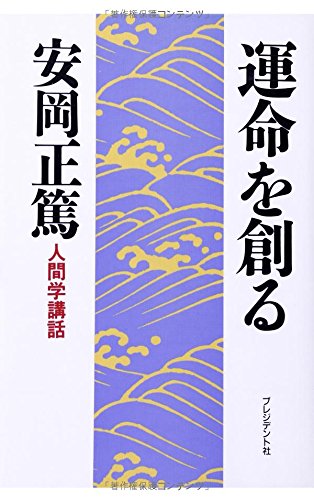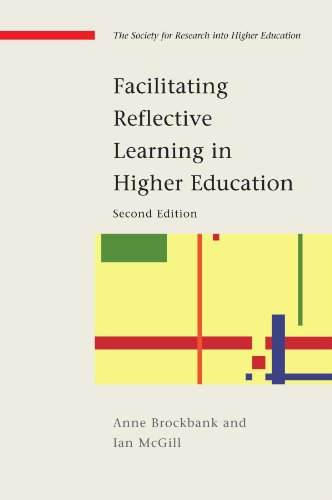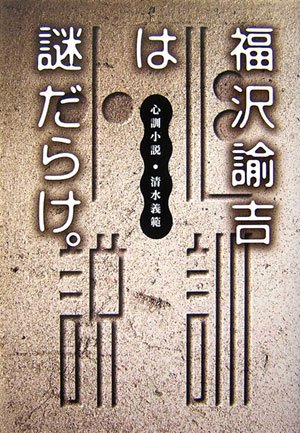まえがき
pros and consリスト、プロコン・リストとも。
リスト
- 1. 選択肢を(丹念に)洗い出す
- 2. 直感やその時点で知っている情報を基に、よい点・悪い点を書き出す
- 3. (よい点・悪い点に)「つっこみ」を入れ、修正をする
- 3A. (それぞれの点の)真偽を明らかにする
- 3B. (よさ・悪さの)度合いを調整する(客観的に表現する、重みをつける)
- 3C. 自分が気づいていない○と×がないか考える・調べる
- 3D. (自分から)仕掛けることによって(○を大きく、×を小さく、×を○に)変えられないかを考える
- 4. 天秤にかけて比較し、最も魅力な選択肢を選ぶ
あとがき
『自分の答えのつくりかた―INDEPENDENT MIND』より。カッコを追加しました。書籍では各項目ごとに解説文が添えられています。
よく作る○×リスト。このようにていねいに考えることで、より納得のいく選択につながりそうですね。
- タイトル: 自分の答えのつくりかた―INDEPENDENT MIND
- 著者: 渡辺 健介(著)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2009-05-22