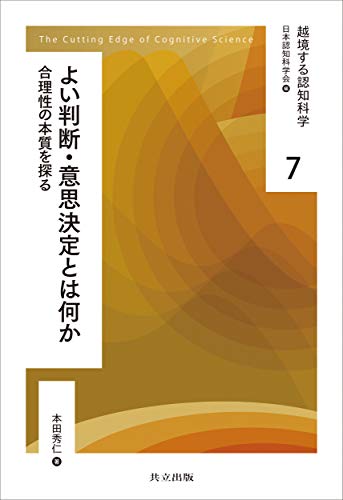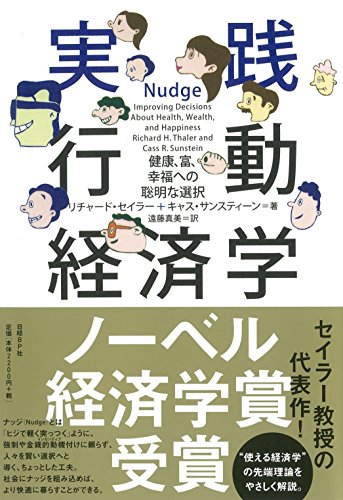まえがき
『ナッジは人の判断や意思決定におけるバイアスを「活用」してよい判断や意思決定に導く介入法である。それに対してブーストは合理的な判断や意思決定を行えるように認知的技量を「高める」ための介入法である。』
リスト
- もし個人が新しい技量を高めるための能力やモチベーションを欠く場合は、ナッジのほうがより効率的な介入法である
- もし政策決定者が人びとのゴールについて明確に理解できなかったり、個人間で明確に異なるゴールが存在していたり、あるいは対立する場合は、ブーストは誤りが少ない介入法である
- もしナッジが機能するためにナッジの透明性を低める必要があったり、あるいはナッジされる人に見えない形にする必要がある場合は、意思決定の逆転性は容易に達成されず、パターナリズム的な介入となる
- もし政府が常に人びとにとって好意的に機能しなかったり、また民間に有害ともいえる選択構造を作り出すことを許容しているのであれば、ブーストはそれらから個々を守る方法を提供する
- もし政策決定者が汎用性の高い、持続する行動を高めることを目指すのであれば、ブーストが目的にかなった方法である
- もしナッジやブーストによる介入によって予期できない、望ましくない結果になるような危険が存在しているのであれば、それぞれの代替案を考えるべきである
あとがき
まえがきを含めて、本田 秀仁『よい判断・意思決定とは何か: 合理性の本質を探る』 (共立出版、2021年)より。リストは参考文献(1)からの引用として翻訳されたものを引用しました。
リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン『実践 行動経済学』 (日経BP、2009年)を読んで以来ナッジという介入法をうさん臭く(つまり3のようなパターナリズム的介入の道具に使われるのではないかという懸念を)感じていたので、ブーストという介入法を知って好ましく感じました。
参考文献
(1) Hertwig, Ralph. “When to consider boosting: some rules for policy-makers.” Behavioural Public Policy 1.2 (2017): 143-161.