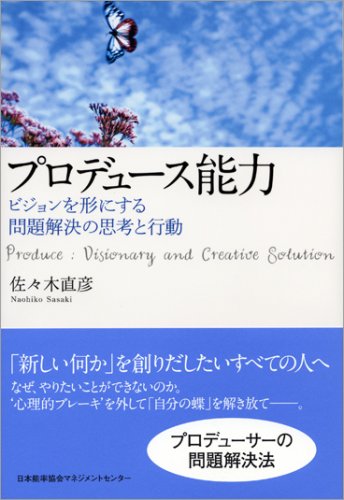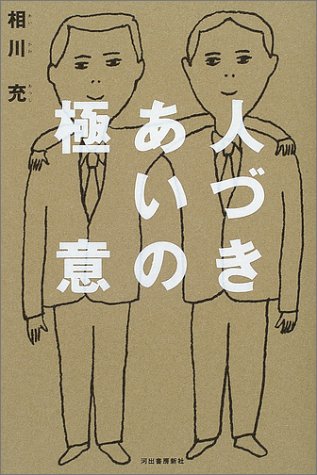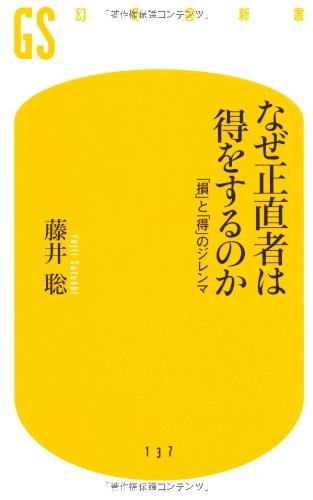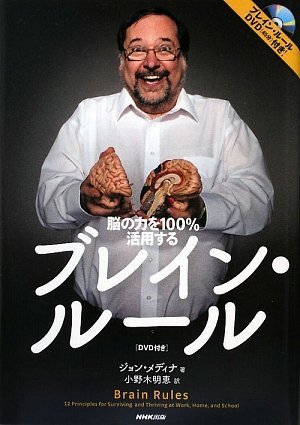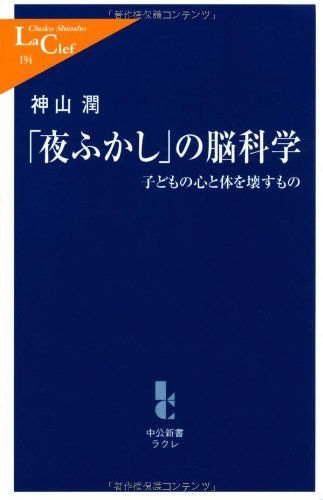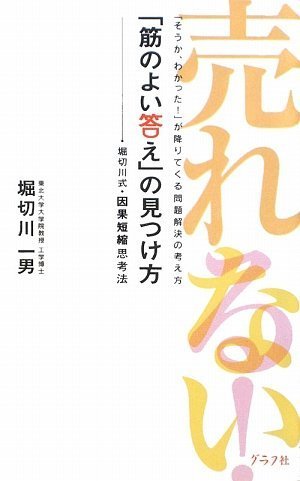まえがき
『〔アメリカの小児科医、T.ベリー・ブラゼルトンによる〕。わたしとしては、「赤ん坊版マネジメントの七つのルール」とでもよびたいものだ。』
リスト
- ぼくがほしいものは、ぼくのもの。
- きみにあげたあとで気が変わったら、ぼくのもの。
- きみから取り上げることができれば、ぼくのもの。
- きみといっしょになにかを作っているなら、その材料はみんなぼくのもの。
- ぼくのものに似てたら、ぼくのもの。
- ぼくのものなら、どんなことがあったって、だれのものにもならない。
- きみのものは、ぼくのもの。
あとがき
まえがきを含めて『ブレイン・ルール』より引用。一歳半になる前の子どもは、こんな感じだということ。うちもまさにそんな感じだったので、思わずメモしました。
このリストは古いもののようですね。下に原文と思われるリストを引用しますが、このリストを掲載しているブログエントリによると、25年前に新聞の切り抜きで見かけたとのこと。
The Toddler’s Creed
* If I want it, it’s mine.
* If I give it to you and change my mind later, it’s mine.
* If I can take it away from you, it’s mine.
* If I had it a little while ago, it’s mine.
* If it’s mine, it will never belong to anybody else, no matter what.
* If we are building something together, all the pieces are mine.
* If it looks just like mine, it is mine.
(Pratie Place)