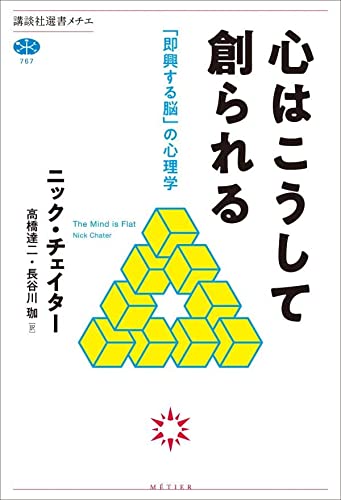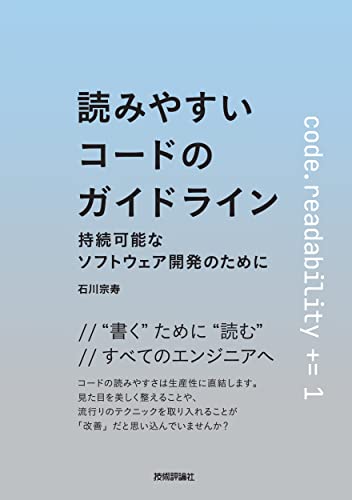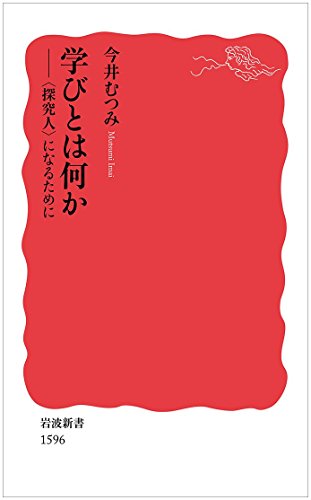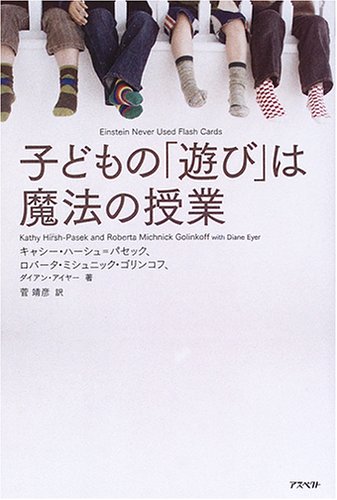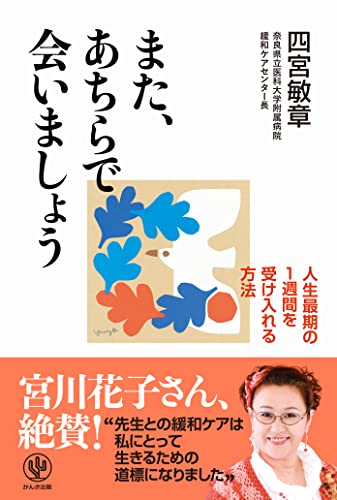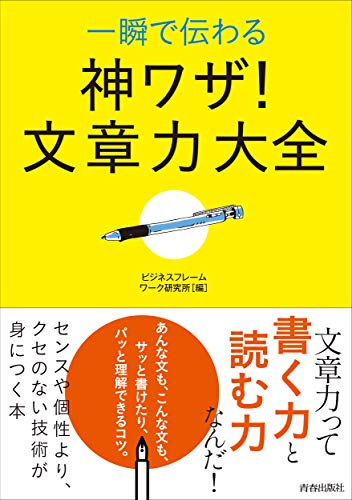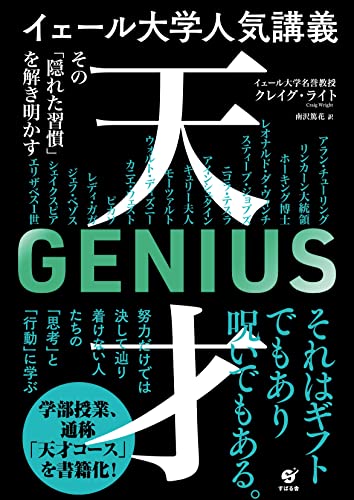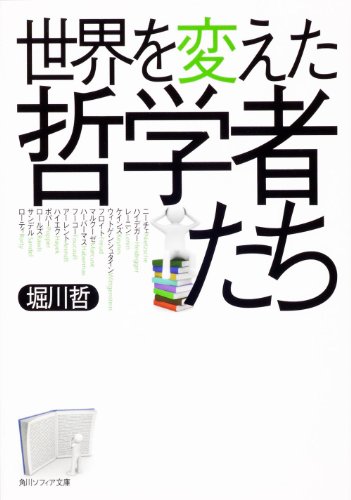まえがき
『心〈マインド〉はどういう仕組みなのか。(略)四つの原理を提案しよう。』
リスト
- 第一の原理: 注意とは解釈の過程である。脳は瞬間ごとに、標的となる情報に「着目〈ロックオン〉」し(すなわち注意を払い)、整理統合〈オーガナイズ〉して解釈しようとする。標的は感覚経験の特定の一部や、言葉の欠片や、記憶などである。
- 第二の原理: 感覚情報について意識的に経験できるのはその解釈のみである。脳が感覚入力を解釈した結果は意識されるが、解釈が構築されるもととなった「なまの素材」と構築過程そのものには、意識的なアクセスはできない。
- 第三の原理: あらゆる意識的思考は、感覚情報へと意味のある解釈を施すことにかかわっている。つまり、その意味のある解釈以外の何も意識されはしない。
- 第四の原理: 意識の流れとは、意識的思考が次々と連なることにすぎない。意識的思考とは、すでに述べたように、感覚入力から意味をもったまとまりを創造するプロセスである。
あとがき
まえがきを含めて、ニック・チェイター『心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学』 (講談社、2022年)より。リストは本文(第七章)を編集・引用して作成しました。
このサイクルに無意識のような「心の奥」が出てこないところがポイント。「訳者解説」より、本書の核となる主張を要約しているように思われる段落を引用します。
つまり脳は、「心の奥」がある(ぎっしり豊かに中身の詰まった内的世界が存在していてそのほんの上澄みが「心の表面」すなわち意識的自覚として現れる)という錯覚を創り出しているのみならず、「心というものが存在している」という錯覚さえも創り出しているのだ(本書の邦題はそこから取られている)。しかし実態は、感覚情報のほんのひとかけらを解釈して意味付けした結果がその瞬間の意識となっているのみであって、それとは別に「心」と呼ばれる何かが確固として存在しているわけではないのだ。
- タイトル: 心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学
- 著者: ニック・チェイター(著)、高橋 達二(翻訳)、長谷川 珈(翻訳)、高橋 達二(解説)、長谷川 珈(解説)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2022-07-14