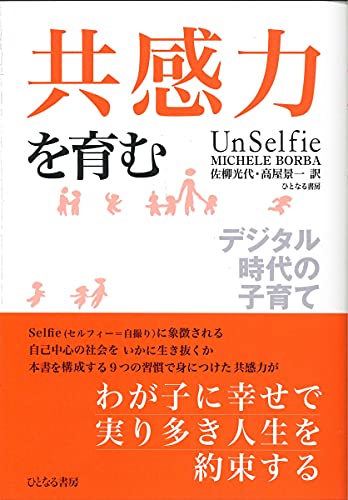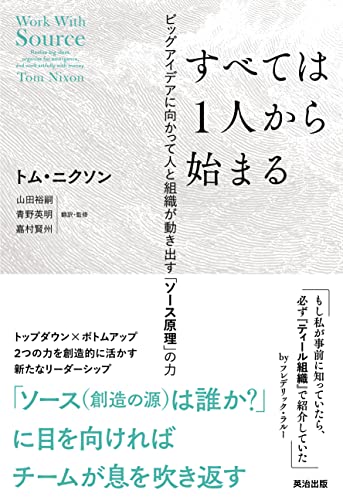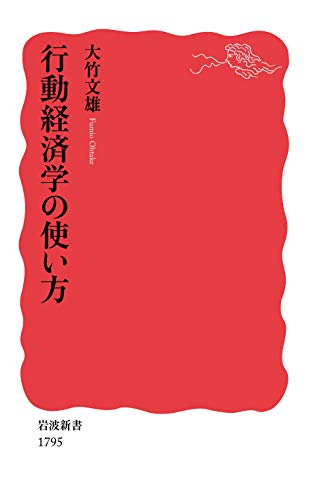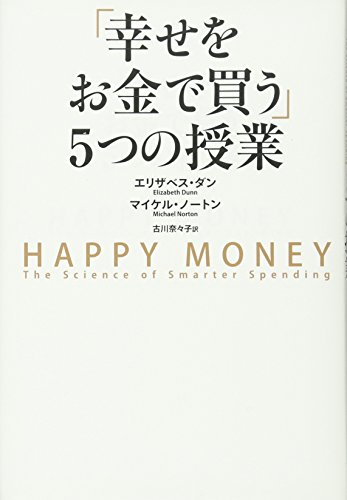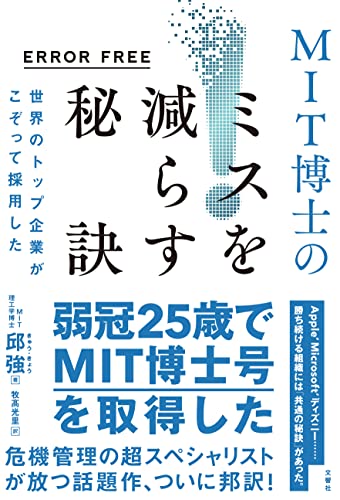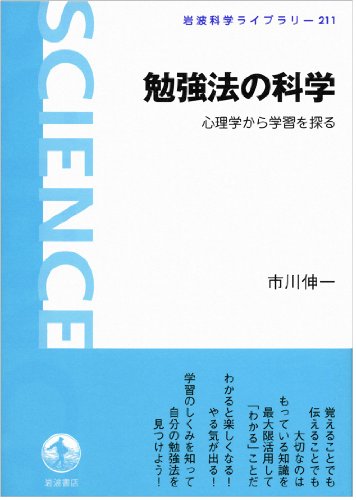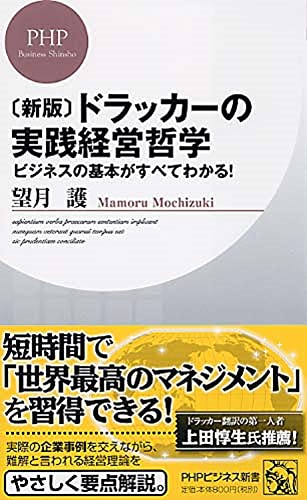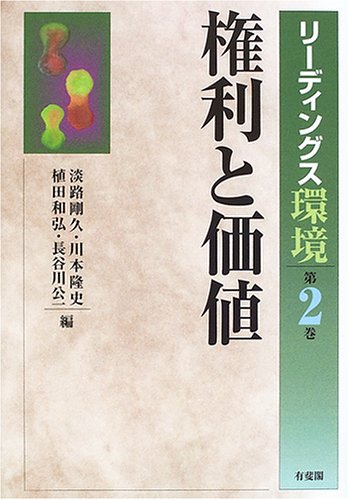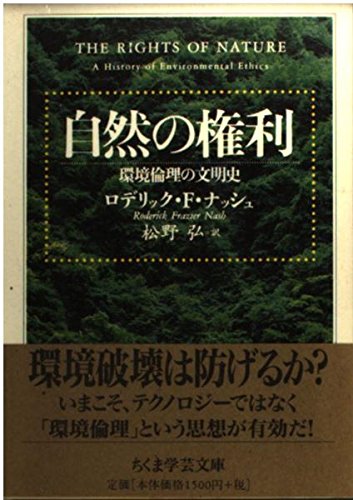まえがき
『ほかの人に寄り添うことは、ほかの人の気持ちと必要を子どもが理解するとともに、「自己没入」を減らして、ほかの人をもっと意識する方法である。共感のスキルを身につけるには、順を追って学べる4つのステップがある。』
リスト
- 相手に注意を向ける …… 相手に注意を集中する / 相手の気持ちに心を向ける / 身を乗り出して話を聞く / 目を合わせる / 相手の考えを認め、頷いたり微笑んだりする
- 相手の気持ちを感じ取る …… 相手の感情を「よく見、よく聞く」 / 確かでないなら、もっと説明を聞く / 感じ取った気持ちを言語化する
- 相手の立場に立ってみる …… 想像力を使う / 心の中が見えるメガネをかけたつもりになる / 自分だったらどう思うかを考える
- 相手の状況を言葉にして伝える …… 相手の発言を繰り返す / 相手の考えや気持ちや必要を言葉にする / 手助けを申し出る
あとがき
まえがきを含めて、ミシェル・ボーバ『共感力を育む: デジタル時代の子育て』 (ひとなる書房、2021年)より。本文を要約してリスト化しました。
現代は “UnSelfie”。著者は『近年の自己没入型の熱狂を「セルフィ症候群」と呼んでいる。』と言い、子どもの共感力の衰退を危惧しています。
観察し、感じ取り、考え、伝える。具体的な行動にブレイクダウンされているので実践しやすいステップです。本書には子どもが実践できる(ように大人が教えやすい)こういったリストが数多く収められています。
- タイトル: 共感力を育む: デジタル時代の子育て
- 著者: ミシェル・ボーバ(著)、佐柳 光代(翻訳)、髙屋 景一(翻訳)
- 出版社: ひとなる書房
- 出版日: 2021-10-19