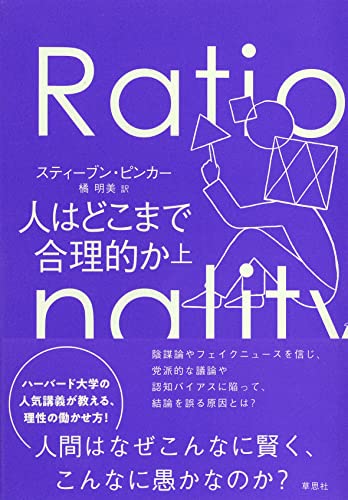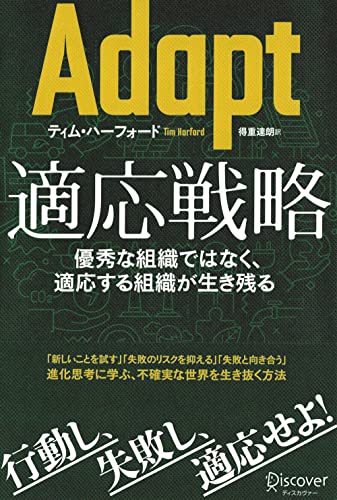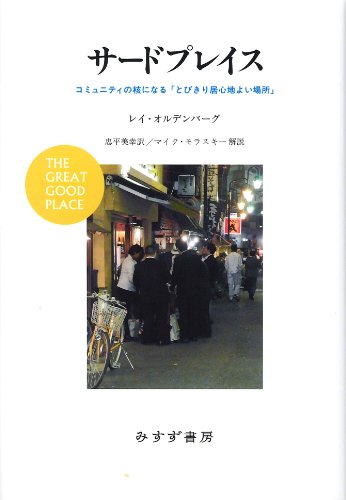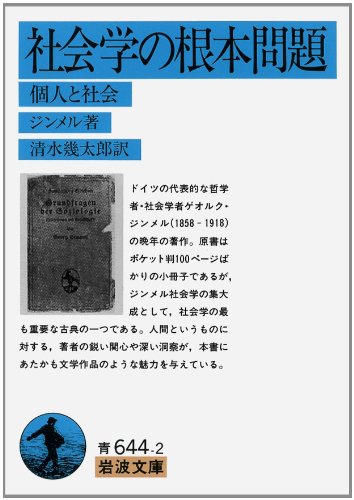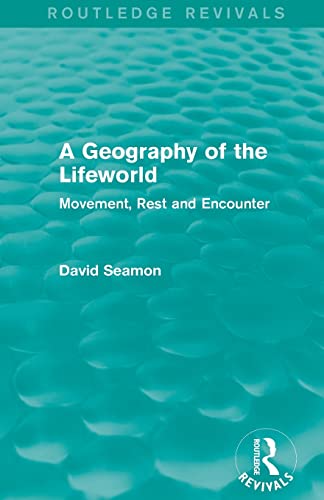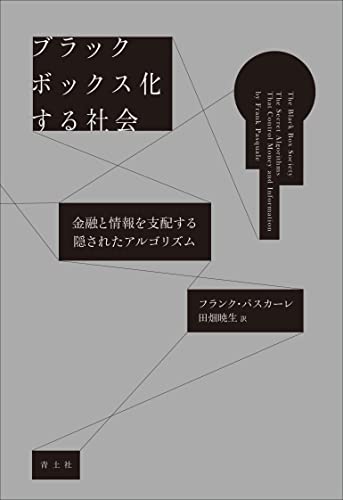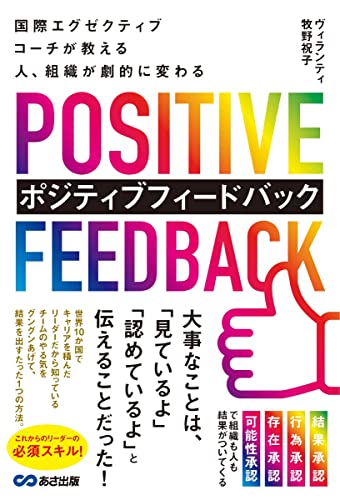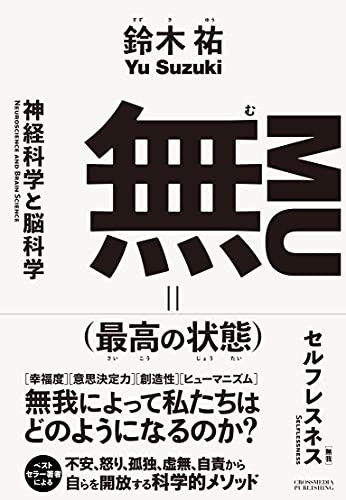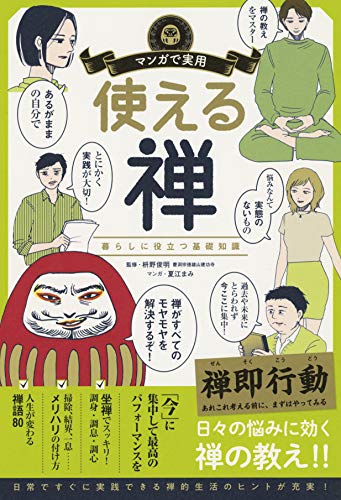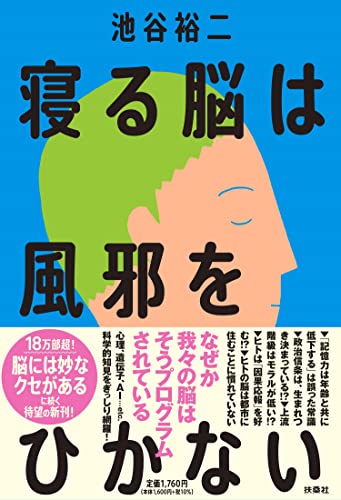まえがき
『ある種の考えは、口に出すのが憚られるばかりか、考えること自体が悪だとされる。それがタブー(略)と呼ばれる現象である。心理学者のフィリップ・テトロックは、(略)3つに分けて説明している。』
リスト
- 禁じられた基準率 (forbidden base rate): 基準率のタブー。何らかの統計を性別・人種・宗教などのサブグループに分けてプロファイリングする。「男(女)性はIQが低(高)い」
- タブー・トレードオフ (taboo tradeoff): 交換のタブー。命など神聖なものと金銭や利便性など低俗なものを交換する。「臓器を売買する」
- 異端視される反事実 (heretical counterfactual): 反事実のタブー。ある状況が真実でない場合に何が起こりうるかを考える。「もし聖典に誤りがあったら?」「もし人種差別をするならどの人種?」
あとがき
まえがきを含めて、スティーブン・ピンカー『人はどこまで合理的か 上』 (草思社、2022年)より。まえがきのテトロック氏の論文は、参考文献[1]。
タブーの種類など考えたこともなかったのでよい頭の体操になりました。経営におけるタブーやわが社におけるタブーなど、目に見えないルールを具体的に考える際に役立ちそう。
- タイトル: 人はどこまで合理的か 上
- 著者: スティーブン・ピンカー(著)、橘 明美(翻訳)
- 出版社: 草思社
- 出版日: 2022-07-12
参考文献
[1] Tetlock, Philip E. “Thinking the unthinkable: Sacred values and taboo cognitions.” Trends in cognitive sciences 7.7 (2003): 320-324.