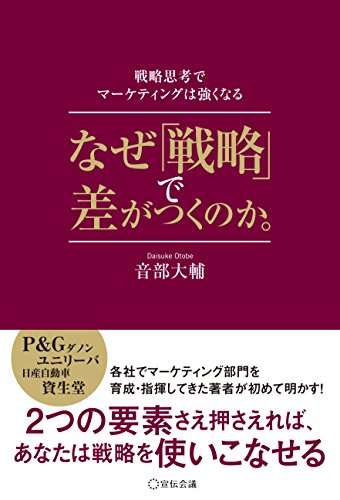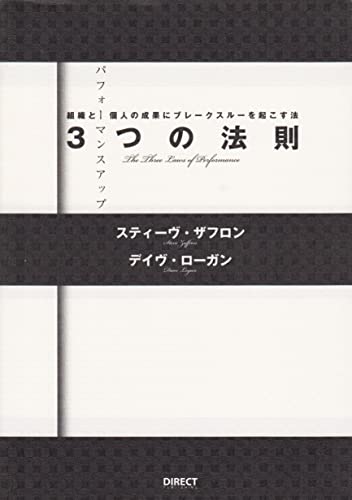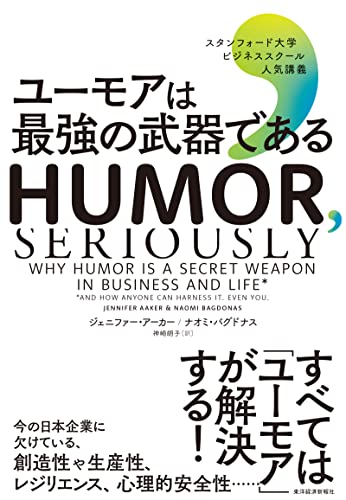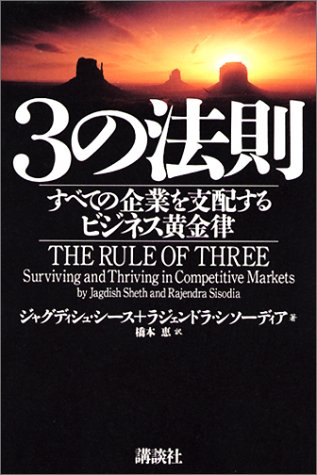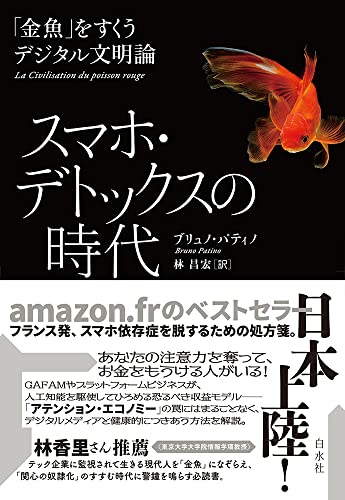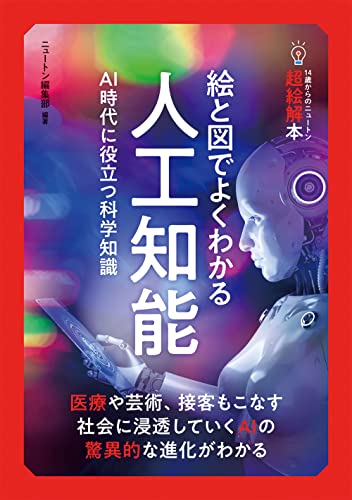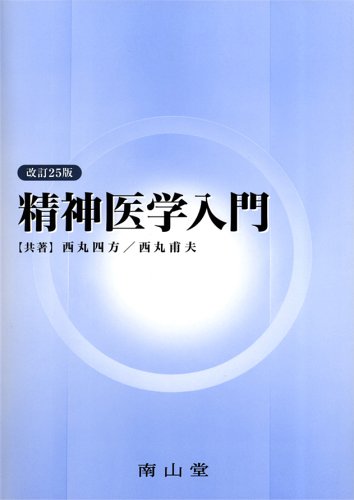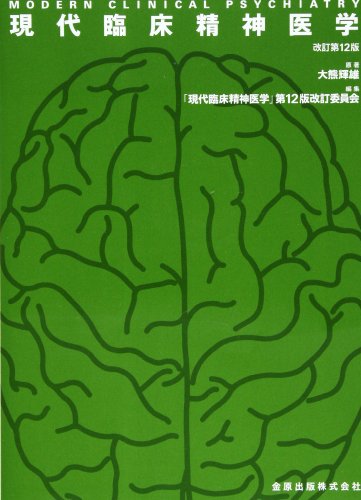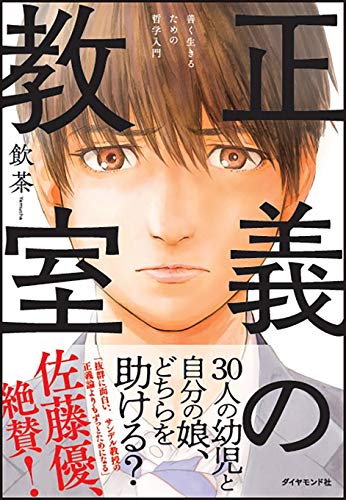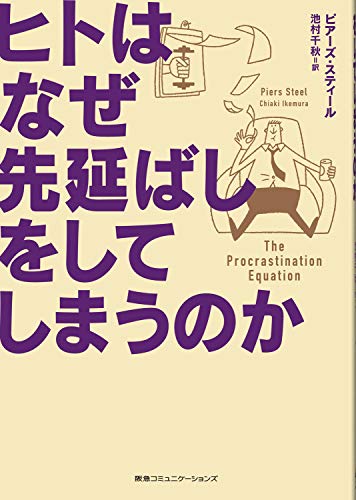まえがき
『競争市場も淘汰を繰り返して進化し、一番強くて、実力のある三社がトップグループを形成する――それが、〈3の法則〉というわけだ。』
リスト
- 業界トップ企業は、市場シェアが高く財務実績も良い。しかし、シェアが高すぎるとスケールメリットがなくなり、競争法の規制も厳しくなる。新技術は模倣するのが得策である。
- 業界二位企業は、市場シェアが低くても財務実績は良い。しかし、業界トップ企業に対抗するためには、革新的な戦略や製品を打ち出す必要がある。
- 業界三位企業は、市場シェアや財務実績が低く、不安定な立場にある。しかし、最も革新的な技術を開発することが多い。市場の溝〈ディッチ〉から離れることやスペシャリストに転換することで生き残りを図る。
あとがき
まえがきを含めて、ジャグディシュ・シース、ラジェンドラ・シソーディア『3の法則―すべての企業を支配するビジネス黄金律』 (講談社、2002年)より。リストは本書冒頭の「15の基本ルール」を要約して作りました。
ビジネス市場は、多様な商品を揃えて激しく競争するフルライン・ゼネラリスト3社と、そういった競争には参加せず専門的な商品を提供するスペシャリスト企業群からなる。著者は多くの市場がそのような状態になっていることを見い出し、「3の法則」と名付けています。
どの市場でもトップグループは、かならずといっていいほど三社に限られる。(略)〈3の法則〉がもっとも顕著なのは、アメリカの市場だ。ビール、清涼飲料水、航空機、長距離電話など、さまざまな分野で〈3の法則〉が生きている。
「はじめに」より
20年以上前の本ですが、現在の日本でもそういった構造は見受けられます。トヨタ・日産・ホンダ、ドコモ・AU・ソフトバンクなど。
本書ではトップグループの市場シェアが競争戦略に及ぼす影響や、市場内での順位に応じた戦い方のアドバイスなどを、具体例を挙げつつまとめています。日本のビール業界は長らくキリン・アサヒ・サッポロが大手三社でしたが、現在はサントリーがサッポロを抜いて三位につけています。この法則に従えばこの市場も三社に絞られていくわけで、四社の今後の戦略を予想しつつ読む楽しみがあります。
3ページにわたる「15の基本ルール」を3項目に圧縮したので、やや抽象化しすぎかもしれません。
- タイトル: 3の法則―すべての企業を支配するビジネス黄金律
- 著者: シース,ジャグディシュ(著)、シソーディア,ラジェンドラ(著)、Sheth,Jagdish(原名)、Sisodia,Rajendra(原名)、恵, 橋本(翻訳)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2002-06-15