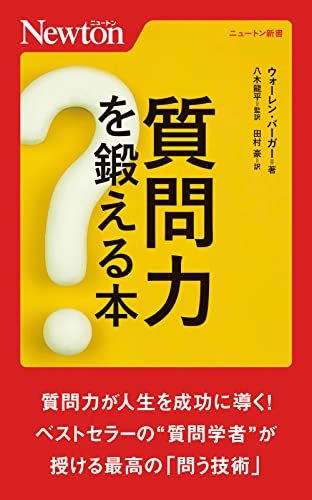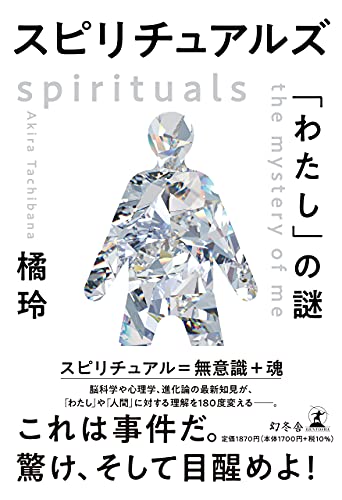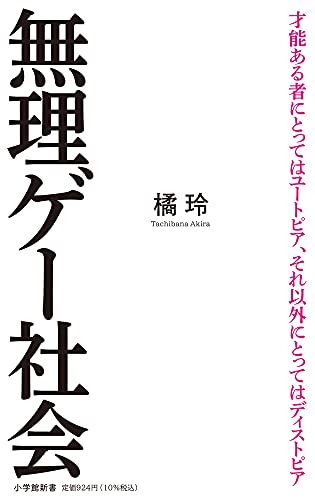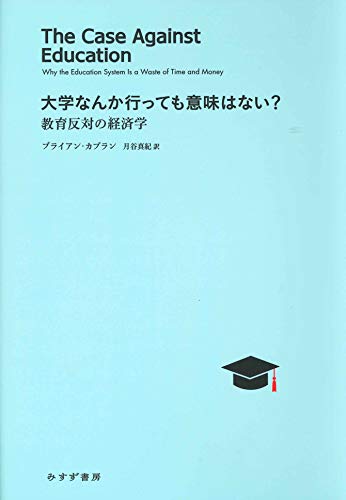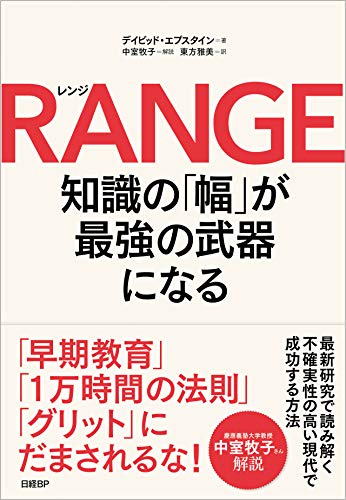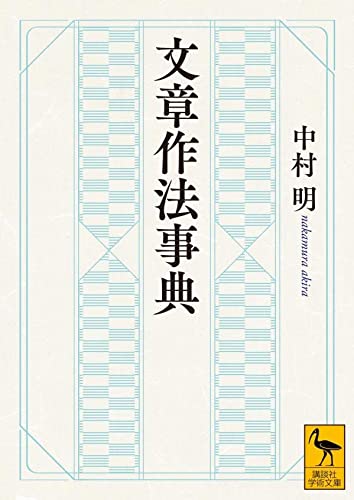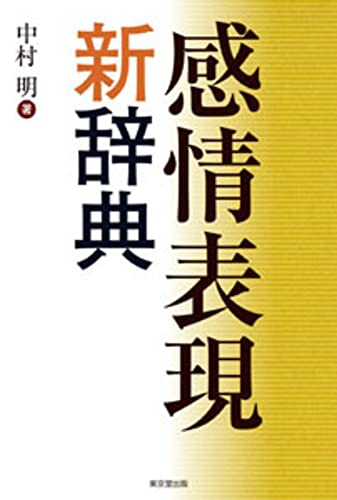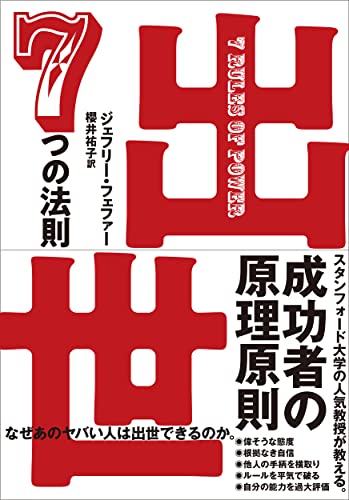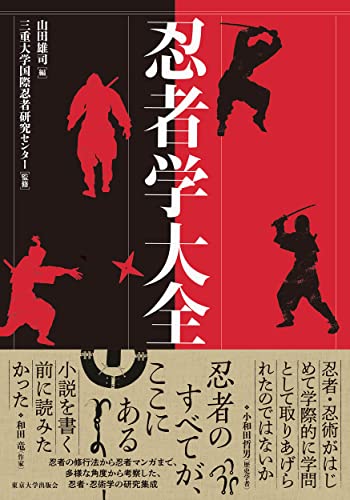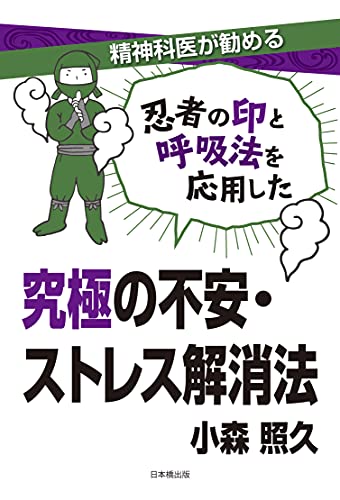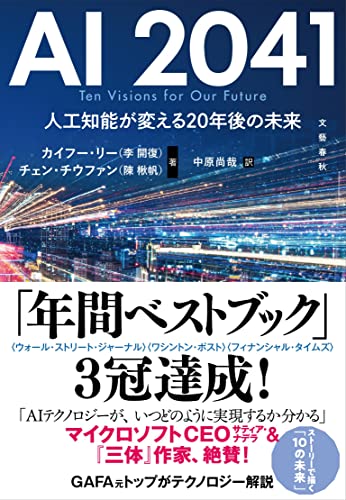まえがき
『MECSTAT は、ソリューション・フォーカスト・セラピーの技術が明確、簡潔、かつ順番に説明された唯一のモデルです。』
リスト
- Miracle questions(ミラクル・クエスチョン): 望む未来を描いてもらう。「寝ている間に奇跡が起きて問題が解決していたとする。あなたは何によって問題が解決していることに気づくだろうか?」
- Exception questions(例外探しの質問): 問題が発生しなかった状況を思い出してもらう。「問題が起きなかった、例外的・奇跡的な状況は? それを再現できるとしたら?」
- Coping questions(コーピング・クエスチョン): 問題にどう対処してきたかを思い出してもらう。「そんな大変な状況で、これまでどうやって対処してきたのか?」
- Scaling questions(スケーリング・クエスチョン): 問題の重要度を評価することで、問題解決に向けたクライアントの思考を促す。「1を最低、10を最高とすると、今日は?」「3を3.5にするためにできそうなことは?」
- Time-out(タイムアウト): たとえば相談に乗る側がいったん席を外すことで、相談する側は会話を振り返り内省できる。相談に乗る側も称賛の言葉をどうかけるかを考える時間が持てる。
- Accolades(称賛): これまで達成してきたことを確認し、その過程で発揮した強みや能力を見出す手助けをする。相手が発したポジティブな言葉を返す。
- Task(タスク): タイムアウトの後、セッションの最後に、クライアントが望むなら「宿題」を一緒に考える。「例外を探してメモする」など。
あとがき
まえがきを含めて、参考文献[1]より。まえがき及びリストは私訳です。
セラピーという言葉が入ると専門的なイメージが強く出てしまうので、一般的な会話でも使い得ることが伝わるようなタイトルにしました。またクライアントでなく相談する側、セラピストでなく相談に乗る側といった言葉づかいにしています。最初の4つの質問については具体的な質問の例がいくつか載っていましたので、こちらで意を酌んで一つに絞って付けました。
こういった解決志向の会話の進め方はいろいろな呼ばれ方をしています。引用元の論文では「ソリューション・フォーカス・セラピー (SFT)」。後から検索しやすいよう他の呼ばれ方を並べておくと、ソリューション・フォーカスト・ブリーフ・セラピー (Solution Focused Brief Therapy, SFBT)、ソリューション・フォーカスト・アプローチ (Solution Focused Approach, SFA)、解決志向アプローチ、など。
この7つはおおまかに会話の流れに沿っています。
参考文献
[1] Greenberg, Gail, Keren Ganshorn, and Alanna Danilkewich. “Solution-focused therapy. Counseling model for busy family physicians.” Canadian Family Physician 47.11 (2001): 2289-2295.