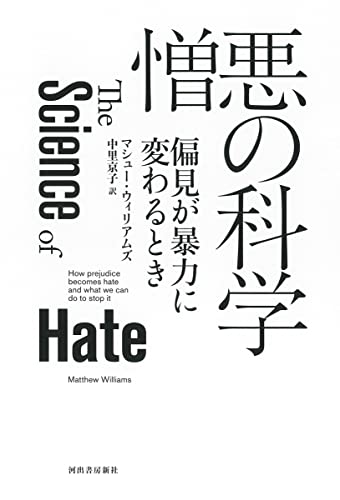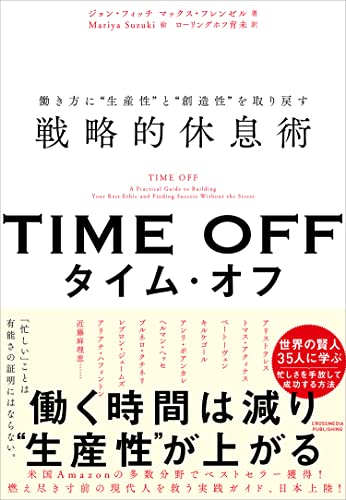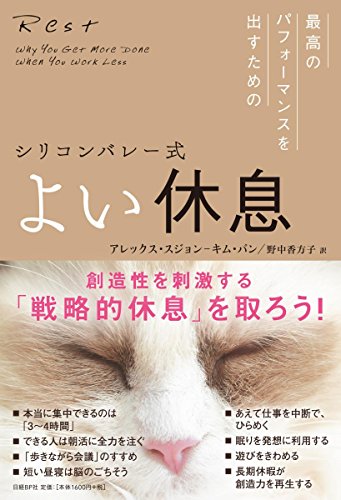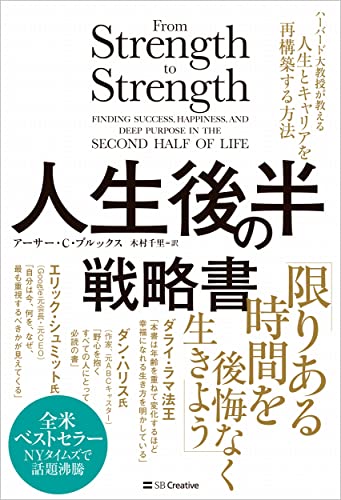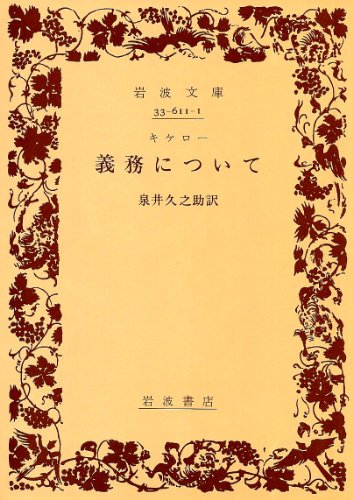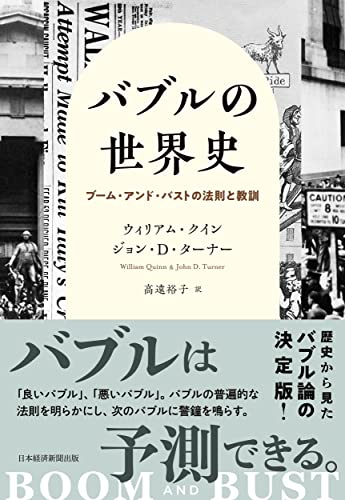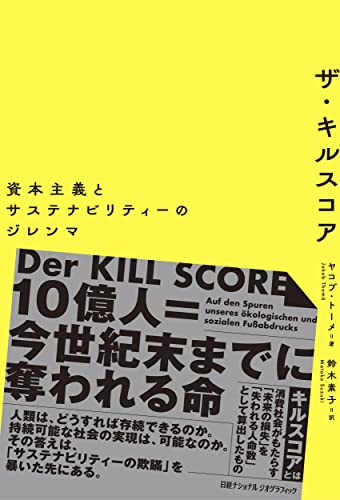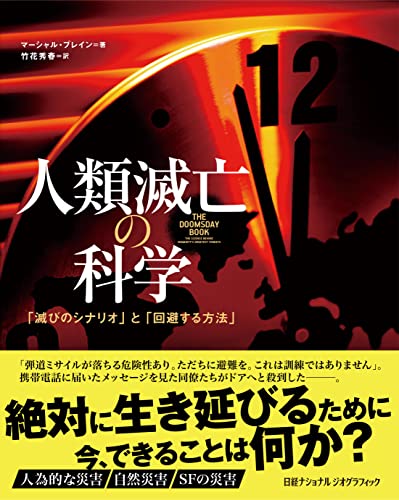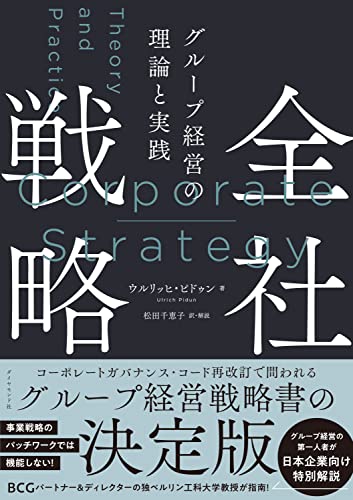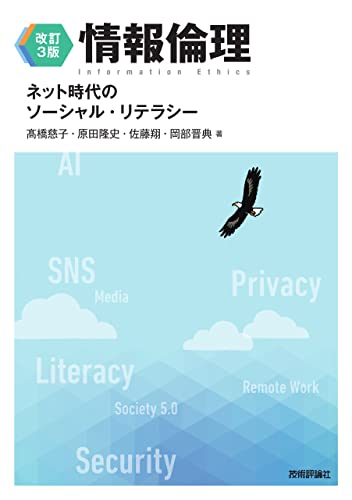まえがき
『これから紹介するのは、自分の偏見(その多くが無意識のものだ)が差別と憎悪に満ちた行動に代わるのを防ぐ一連のステップだ。』
リスト
- 誤報であると認識する
- 異なる他者に対する自分の予断を疑う
- 自分と異なる人と接触する機会を避けない
- 「他者」の立場に立って考える時間を持つ
- 分断を招く出来事に惑わされない
- フィルターバブルを破壊する
- 私たち全員が憎悪行為の第一対応者になる
あとがき
まえがきを含めて、マシュー・ウィリアムズ『憎悪の科学: 偏見が暴力に変わるとき』 (河出書房新社、2023年)より。本文の見出しを引用してリスト化しました。これらのステップは13~14ページにわたって詳細に解説されています。
わかりづらい部分をすこし補足します。1の「誤報」とは、人間の脳が脅威を感じたときに反射的に発する非常警報のうち、実際には脅威でないものに対する警報を指しています。
また6の「フィルターバブル」とは「エコーチェンバー」のオンライン版を指しています。エコーチェンバーとは、『個人が、同好の士の好む情報にさらされる現象』のこと。著者は、フィルターバブルという言葉にはアルゴリズムの関与が示唆されると述べています。
- タイトル: 憎悪の科学: 偏見が暴力に変わるとき
- 著者: マシュー・ウィリアムズ(著)、中里 京子(翻訳)
- 出版社: 河出書房新社
- 出版日: 2023-03-25