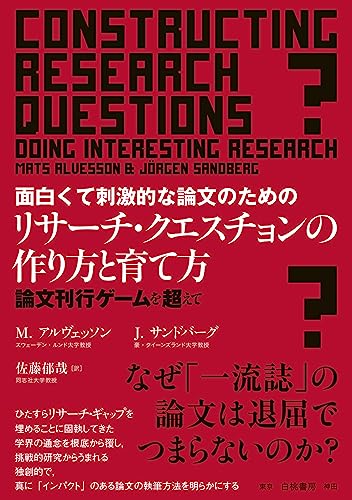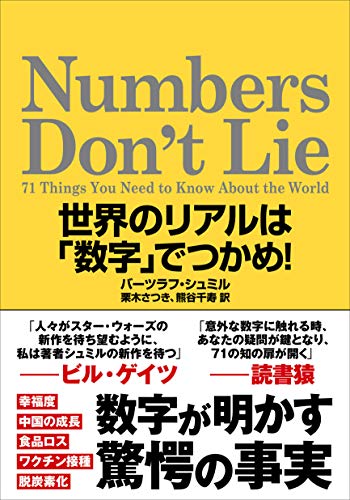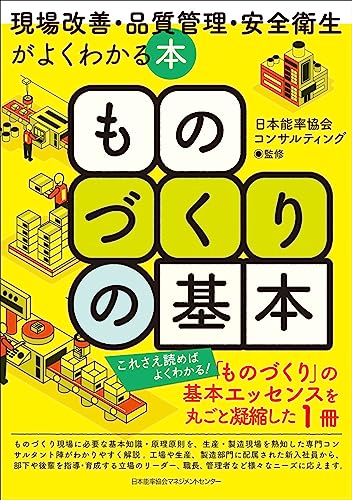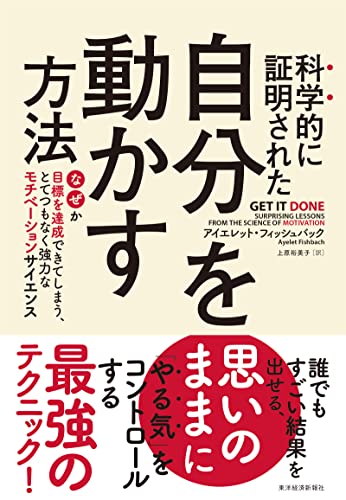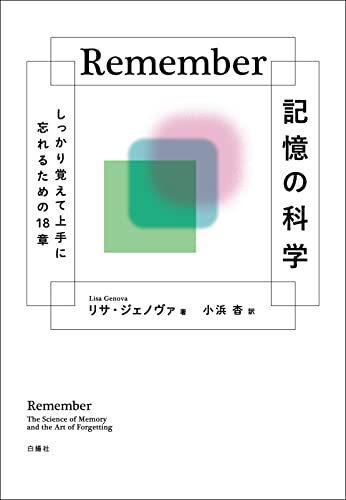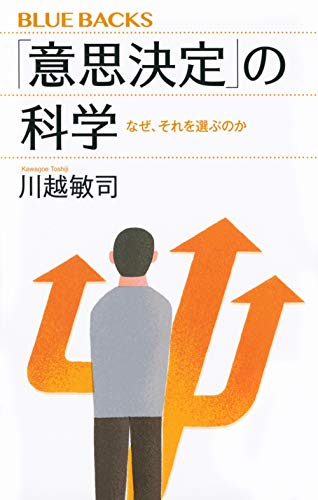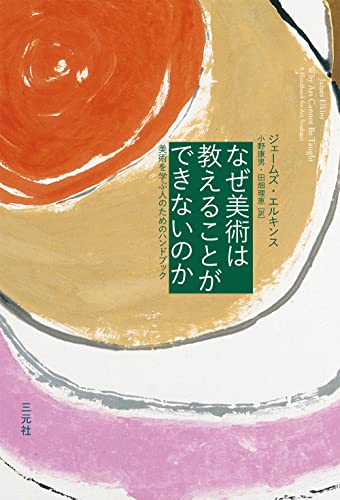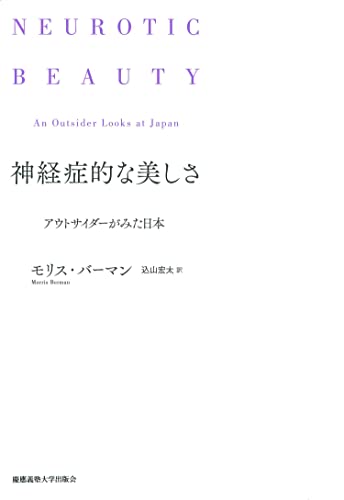まえがき
『(ギャップ・スポッティングとは)〈先行研究の中に従来見落とされてきた課題領域などをはじめとする各種のギャップ(隙間)を見出し、それらのギャップを踏まえて具体的なリサーチ・クエスチョンを作成する〉というやり方である。』
リスト
- 混乱スポッティング (Confusion Spotting): 先行文献に見られる混乱を整理し、それについて説明を行う。
- 軽視・無視スポッティング (Neglect Spotting): 先行研究で軽視ないし無視されている点について明らかにする。(1)見落とされていた研究領域、(2)十分に研究されてこなかった領域、(3)実証データによる裏づけの不足、(4)先行文献の知見をより完全なものにするために本来必要であるはずの検討の不足、といったサブタイプがある。
- 適用スポッティング (Application Spotting): 先行文献の検討を通して理論や概念の新しい適用可能性を明らかにする。先行文献は何らかの形で拡張または補完していく必要があると主張する。
あとがき
まえがきを含めて、マッツ・アルヴェッソン、ヨルゲン・サンドバーグ『面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方: 論文刊行ゲームを超えて』 (白桃書房、2023年)より。リストは本文を要約・編集して作成しました。
このリストは著者らがギャップ・スポッティングと名付けている、リサーチ・クエスチョンを構築する方法の類型です。著者らはギャップ・スポッティングによるリサーチ・クエスチョンの作成が社会科学系の論文においては主流の方法であると分析しています。
著者らはギャップ・スポッティングがリサーチ・クエスチョン構築法の主流だと述べているだけで、タイトルのように「面白くない」とまでは言っていません。「独創的になりづらいリサーチ・クエスチョンの構築法であるギャップ・スポッティングの類型」というあたりがより適切なタイトルかと思います。しかし長すぎるので、少々誇張気味ではありますが「面白くない研究の類型」としました。
ギャップ・スポッティングが不要だとか有害だとか述べているわけではありません、念のため。先行研究のギャップを探すという問いの立て方からは、面白く独創的な研究は生まれづらいと論じています。
- タイトル: 面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方: 論文刊行ゲームを超えて
- 著者: マッツ アルヴェッソン(著)、ヨルゲン サンドバーグ(著)、佐藤 郁哉(翻訳)
- 出版社: 白桃書房
- 出版日: 2023-07-18