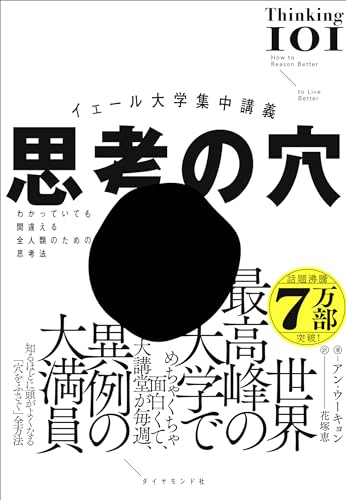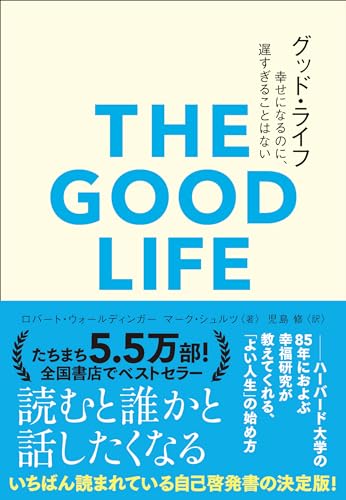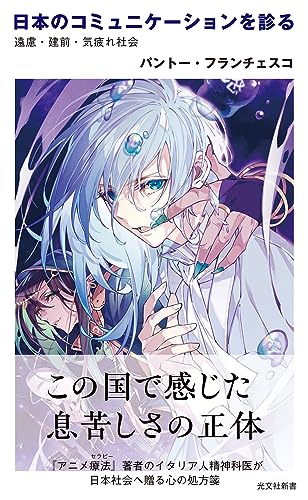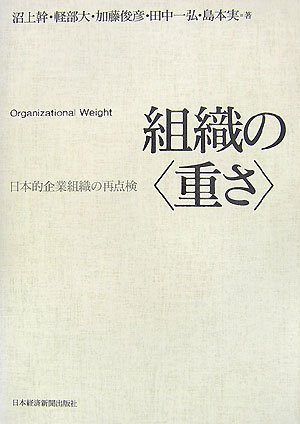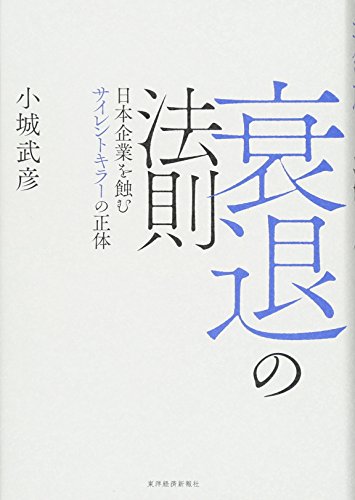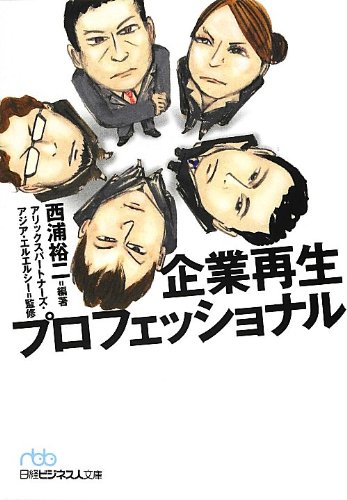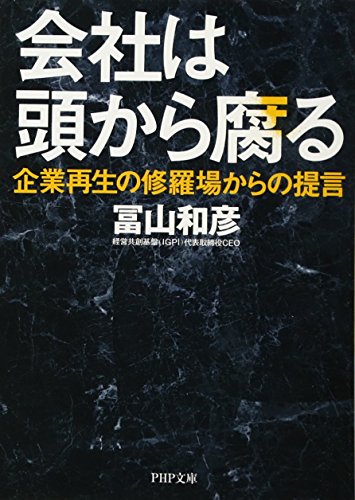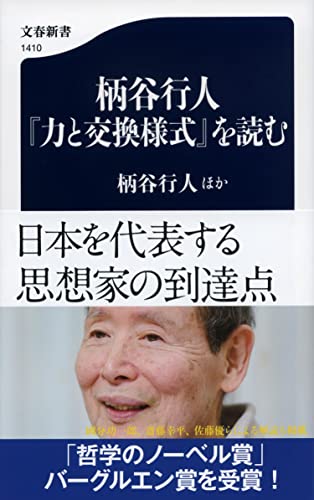まえがき
『この3つを学習するとデータ評価の正確さを高めることに実際につながると、調査で実証されている。』
リスト
- 大数の法則
- 平均への回帰
- ベイズの法則
あとがき
まえがきを含めて、アン・ウーキョン『イェール大学集中講義 思考の穴──わかっていても間違える全人類のための思考法』 (ダイヤモンド社、2023年)より。
見出しだけのリストには数十字の解説を添えることを常としていますが、本文にも抜き書きに適した部分がなく、ゼロからこしらえるのも大変なので、Wikipediaへのリンクをもって補足とします。
- タイトル: イェール大学集中講義 思考の穴──わかっていても間違える全人類のための思考法
- 著者: アン・ウーキョン(著)、花塚 恵(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2023-09-13