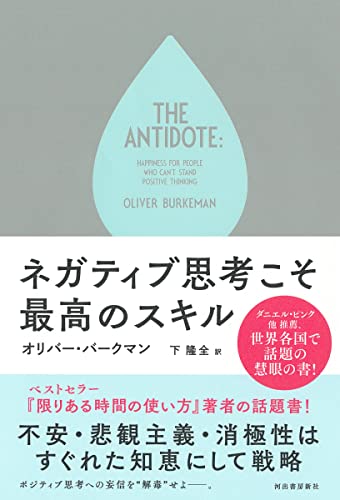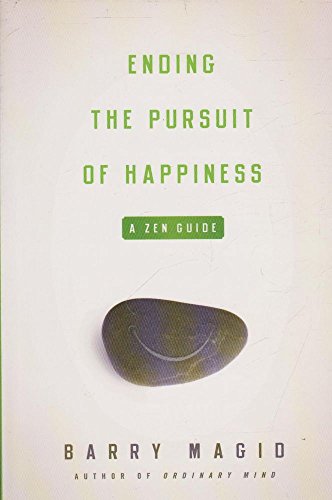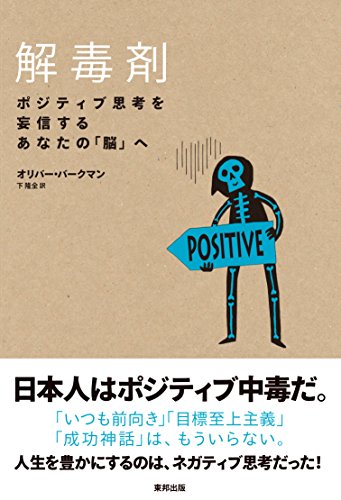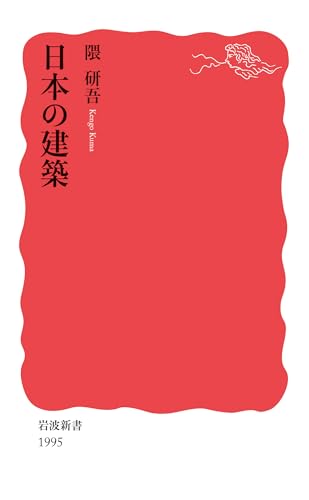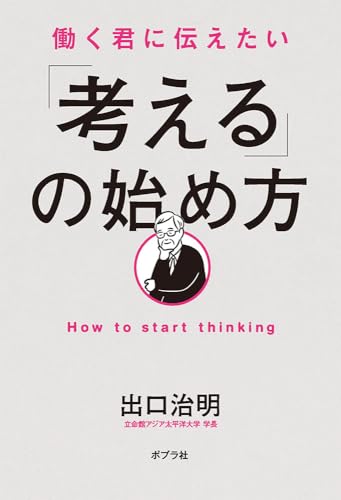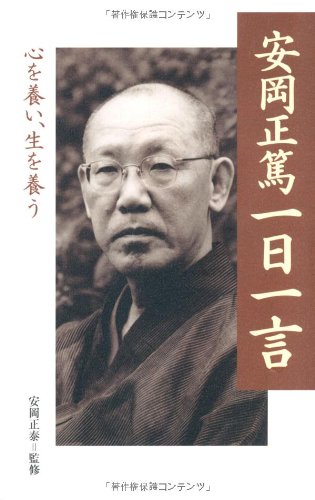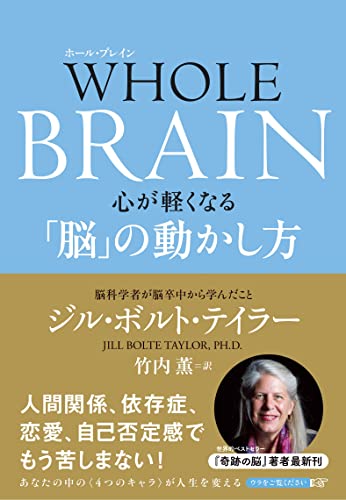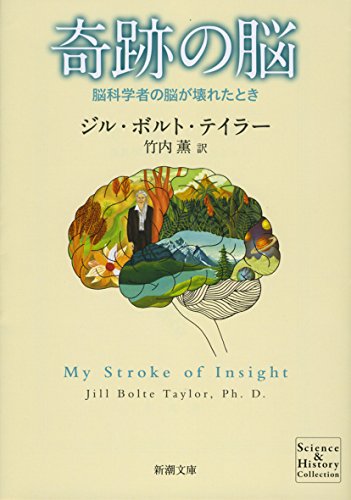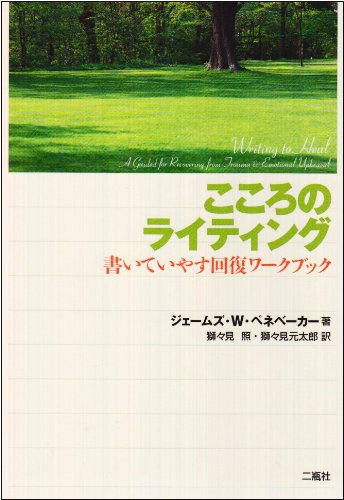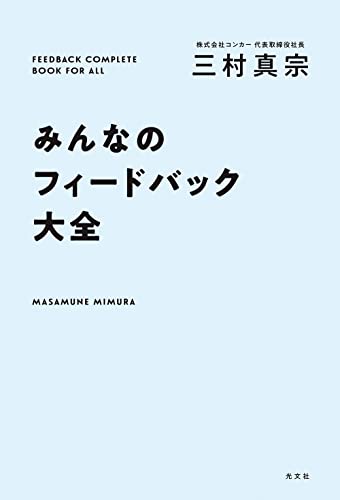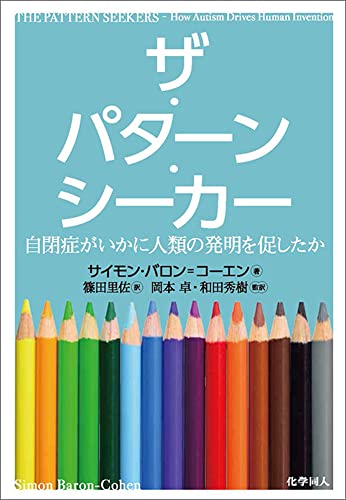まえがき
『バリー・マギッドは次のように主張している。「瞑想を利用して人生をより良く、より幸せにしようというのは、従来の常識からいって、考え違いである」と。しかし、マギッドの主旨は、瞑想の効果を否定することではなかった。』
リスト
- 周囲の事象を改善しようと試みない
- 自らの社会的行動を恣意的にコントロールしようと思わない
- 今現在不愉快に感じている物事を愉快なものに置き換えようとしない
- 「幸福の追求」をあきらめる
あとがき
まえがきを含めて、オリバー・バークマン『ネガティブ思考こそ最高のスキル』 (河出書房新社、2023年)より。
まえがきで引いたバリー・マギッド (Barry Magid) は『アメリカ人の禅僧でベテランの精神科医』。彼の著書 “Ending the Pursuit of Happiness” (Wisdom Publications、2008年)のメッセージをバークマンが要約した部分をリスト化しました。
今現在不愉快に感じている物事を愉快なものに置き換えようとしない。この第3項目に感じるものがあって収集したくなりました。
第4項目は文末を他の項目に合わせて『「幸福」を追い求めない』としたいところ。「あきらめる」という、ある意味で意志を込める動作よりも「追い求めない」という状態で表現したほうが趣旨にも合うように思います。せっかくなので原著をチェックしてみると、”dropping the ‘pursuit of happiness’” という表現でした。
The point, instead, was to learn how to stop trying to fix things, to stop being so preoccupied with trying to control one’s experience of the world, to give up trying to replace unpleasant thoughts and emotions with more pleasant ones, and to see that, through dropping the ‘pursuit of happiness’, a more profound peace might result.
Barry Magid, “Ending the Pursuit of Happiness”
なお本書は『解毒剤 ポジティブ思考を妄信するあなたの「脳」へ』として2015年に出版された本の復刊。よい本でユーザーレビューも高評価でしたがわたしのアンテナにはまったくかからず。復刊に感謝です。
- タイトル: ネガティブ思考こそ最高のスキル
- 著者: オリバー・バークマン(著)、下 隆全(翻訳)
- 出版社: 河出書房新社
- 出版日: 2023-03-25
- タイトル: Ending the Pursuit of Happiness
- 著者: Magid, Barry(著)
- 出版社: Wisdom Publications
- 出版日: 2008-03-17
参考文献
- タイトル: 解毒剤 ポジティブ思考を妄信するあなたの「脳」へ
- 著者: オリバー・バークマン(著)、下隆全(翻訳)
- 出版社: 東邦出版
- 出版日: 2015-10-21