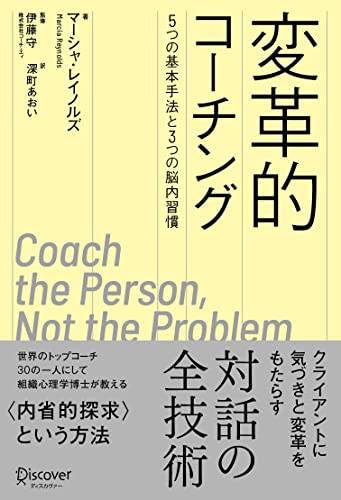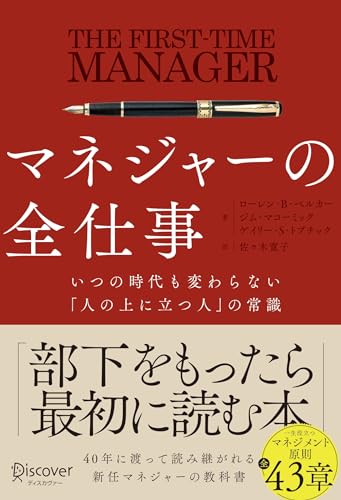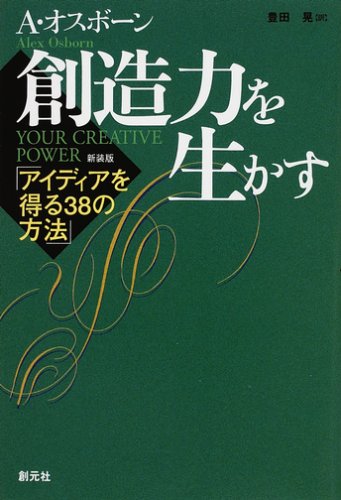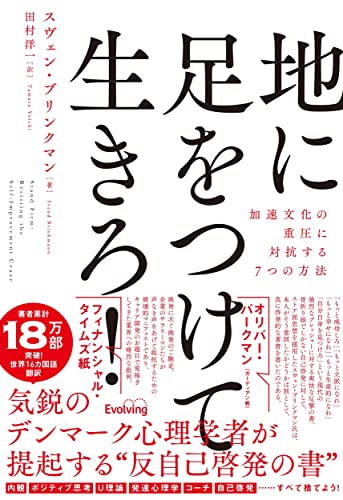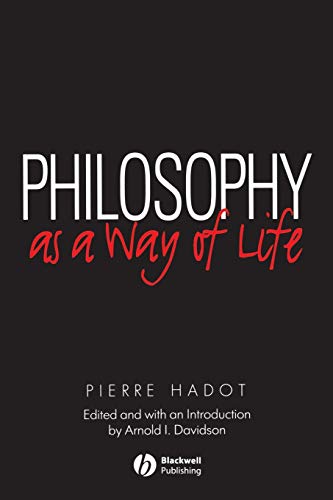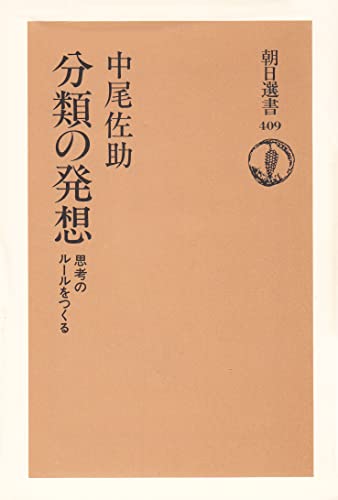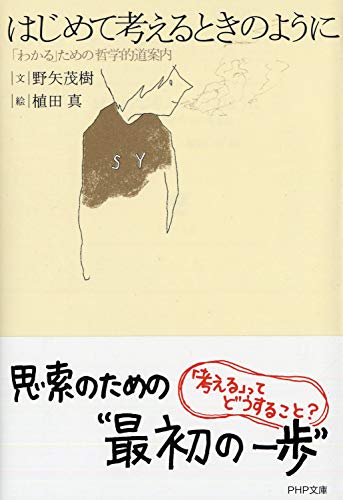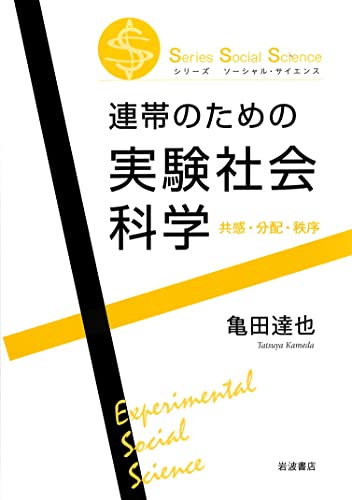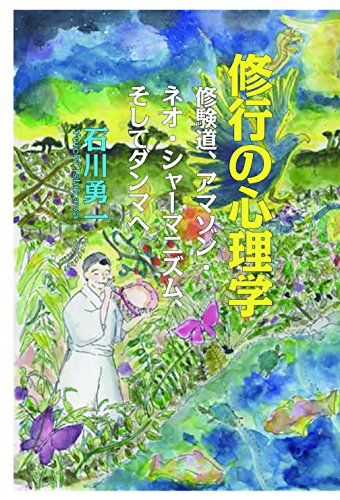まえがき
『人の話を「聞く」ことを「受け取る」と表現するのを、私はジュリアン・トレジャーによるTEDトーク「聞き上手になる5つの方法」で初めて知りました。人の話の聞き方として彼が提唱するのが、(略)「RASA」です。』
リスト
- Receive: 受け取る …… 相手に注意を払う
- Appreciate: 尊重する …… hmm(うん)、OK(なるほど)など相づちを打つ
- Summarize: 要約する …… so(つまり)はコミュニケーションにおいて重要な言葉である
- Ask: 質問する …… その後で質問する
あとがき
まえがきを含めて、マーシャ・レイノルズ『変革的コーチング 5つの基本手法と3つの脳内習慣』 (ディスカヴァー・トゥエンティワン、2023年)より。リストの「……」より後に、引用元であるTEDトーク[1]からの引用を含めた意訳を添えました。
要約してから質問するというのは、少しまどろっこしく感じることもあります。ただ、そもそも話者の言いたいことを理解していないこともあるので、たしかにきちんと話を聞いて会話を進めるうえで有益なステップだと思います
- タイトル: 変革的コーチング 5つの基本手法と3つの脳内習慣
- 著者: マーシャ・レイノルズ(著)、伊藤 守(監修)、深町 あおい(翻訳)
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 出版日: 2023-06-23
参考文献
[1] “5 ways to listen better” by Julian Treasure (TED talk)