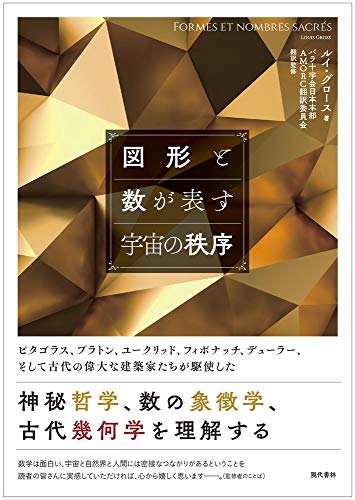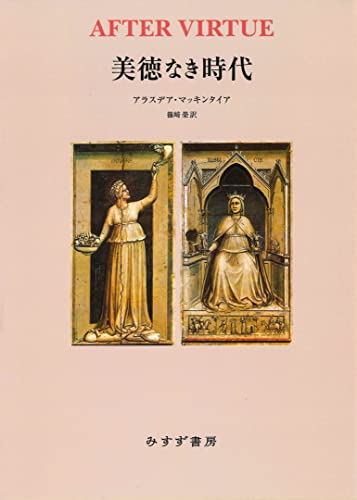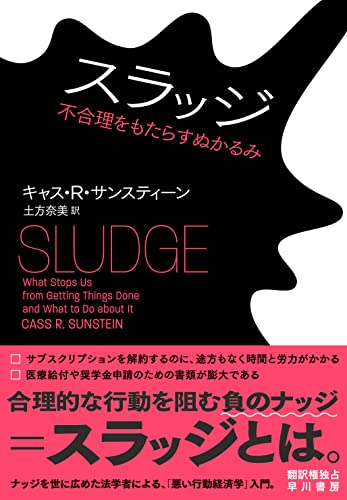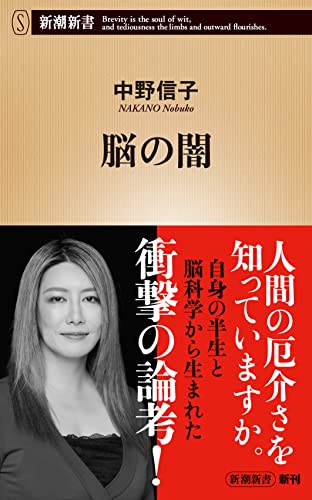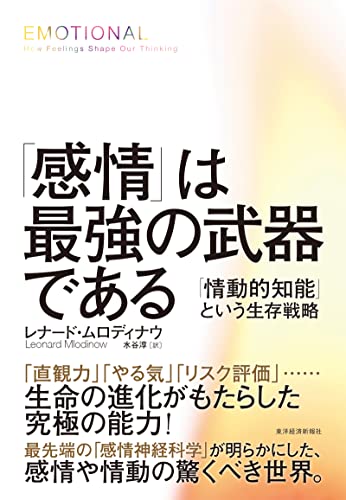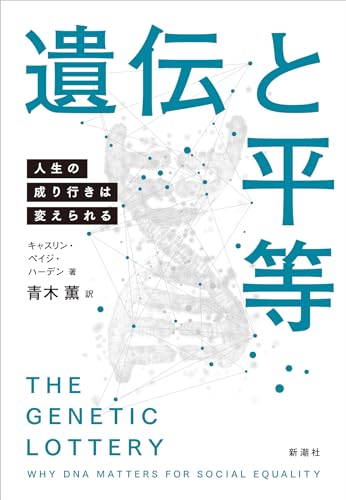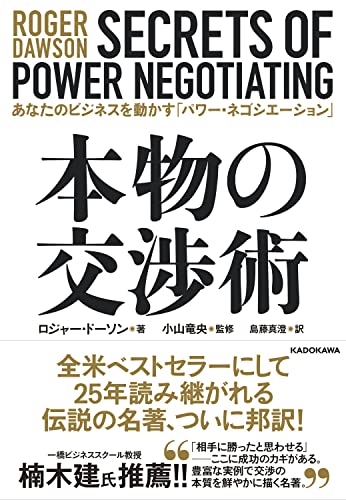まえがき
『ゼロは、個数を表すものではなく、物がないことを表しています。そこで、ゼロはむしろ、記号もしくは演算子のようなものとして考えることができます。(略)数学者にとって、ゼロには3つの働きがあります。』
リスト
- 印〈しるし〉としての役割: 記号(演算子)として、十進法の場合では、ある数字の後に配置されると、その数を10倍することを意味する。
- 数字としての役割: 区切りをあらわす記号であり、数字と数字の間に、数字が「ない」ことを示す。
- 数としての役割: ある単位が「ない」ことを表す。たとえば、100は、100という単位がひとつあり、10という単位がなく、1という単位もないことを表す。
あとがき
まえがきを含めて、ルイ・グロース 『図形と数が表す宇宙の秩序』 (現代書林、2020年)より。まえがきもリストも本文を少し編集のうえ引用しています。
このリストが文中にわりとポツンと置かれていました。これらの働きから何かの解釈が導かれていたわけではない(ように読めた)のですが、ゼロの特異さを説明していたのだと思います。
- タイトル: 図形と数が表す宇宙の秩序
- 著者: グロース,ルイ(著)、バラ十字会日本本部AMORC翻訳委員会(翻訳)
- 出版社: 現代書林
- 出版日: 2020-12-03