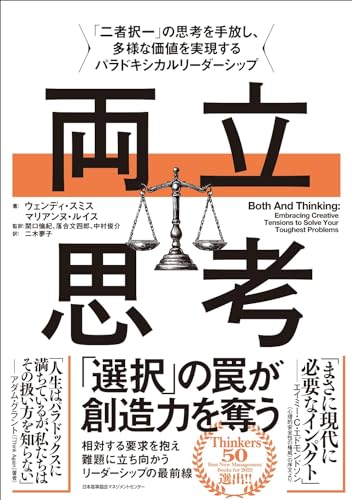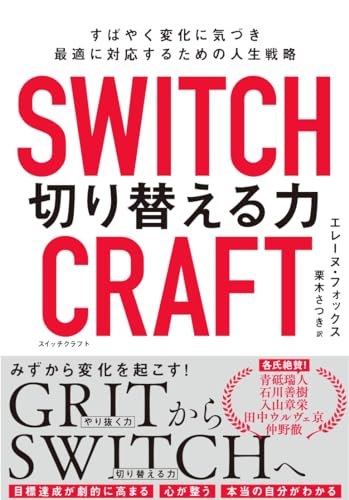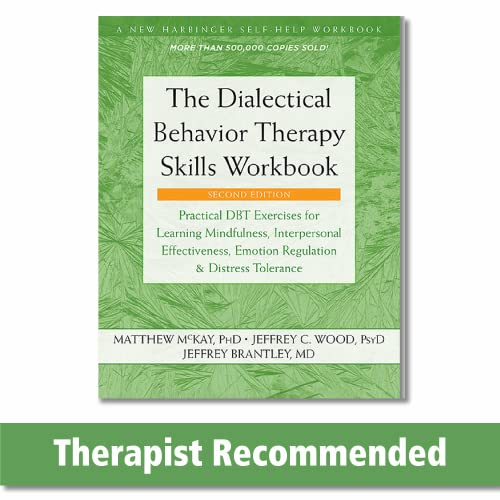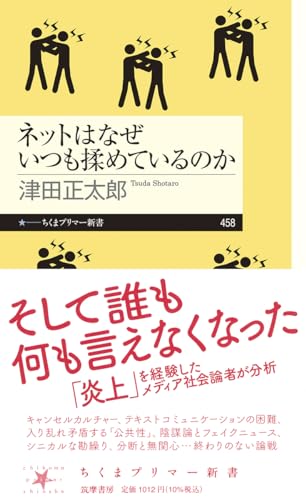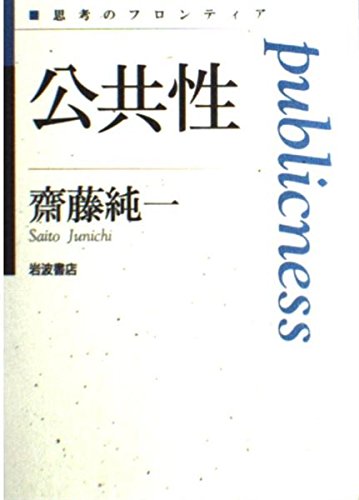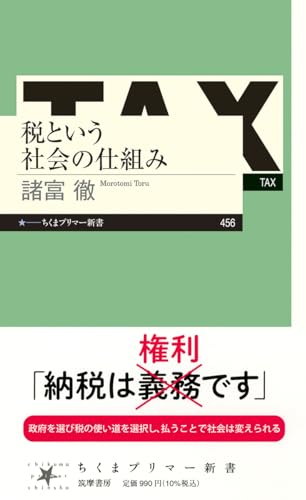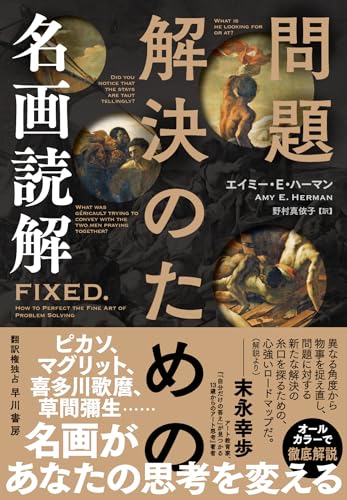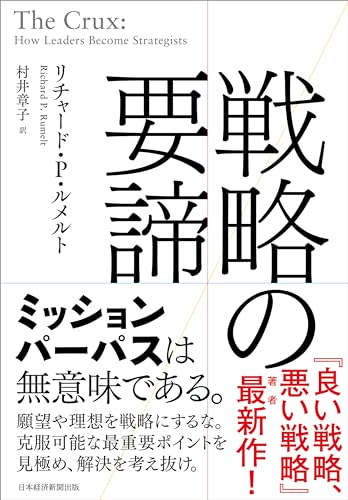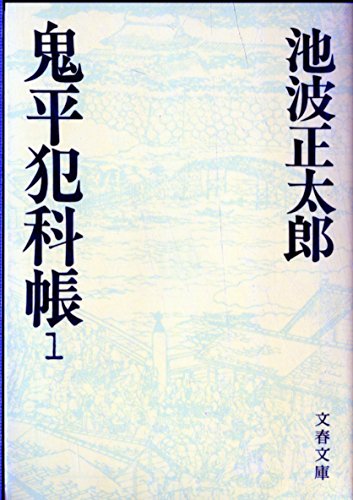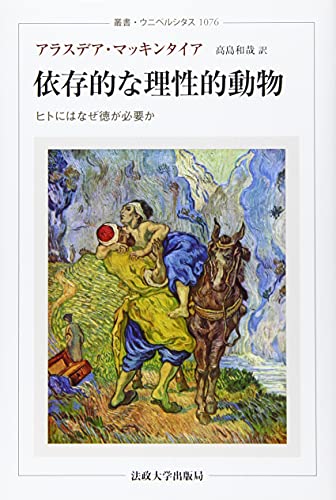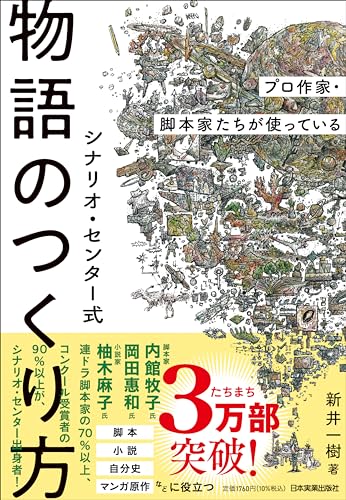まえがき
『(ポラリティ・パートナーシップスのバリー・ジョンソンは、ポラリティ(対立極)を分析するためのモデルを開発し、動詞の頭文字をとってSMALLモデルと名づけている。』
リスト
- ポラリティを認識する (See)
- ポラリティをマッピングする (Map)
- ポラリティを評価する (Assess)
- 評価から学ぶ (Learn)
- ポラリティをてこにする (Leverage)
あとがき
まえがきを含めて、ウェンディ・スミス、マリアンヌ・ルイス『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』 (日本能率協会マネジメントセンター、2023年)より。
ここでのポラリティは、人間関係における対立・分極といった意味合い。本書では「ポラリティ」と「パラドックス」を交換可能な形で用いるとして、SMALLモデルをパラドックス分析のステップとして援用しています。
SMALLモデルについては Polarity Partnerships のWebサイトにわかりやすく書かれていました。
- タイトル: 両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ
- 著者: ウェンディ・スミス(著)、マリアンヌ・ルイス(著)、関口 倫紀(その他)、落合 文四郎(その他)、中村 俊介(その他)
- 出版社: 日本能率協会マネジメントセンター
- 出版日: 2023-11-01