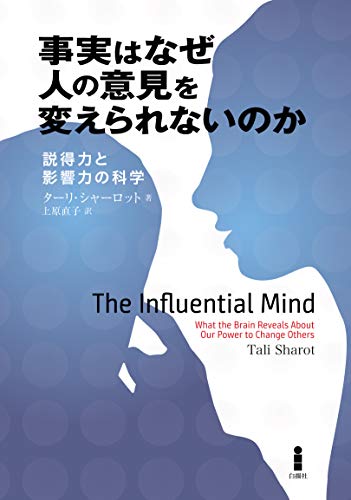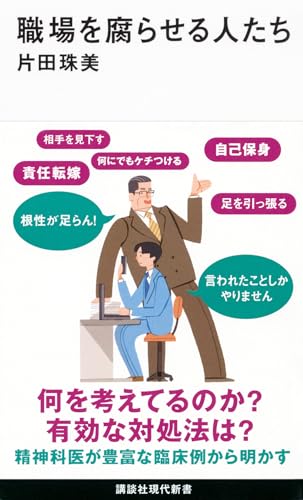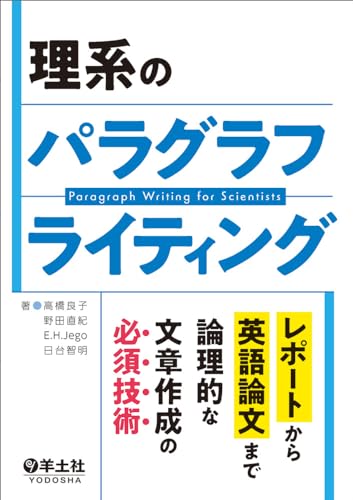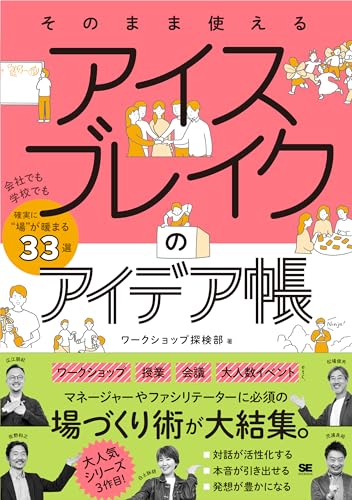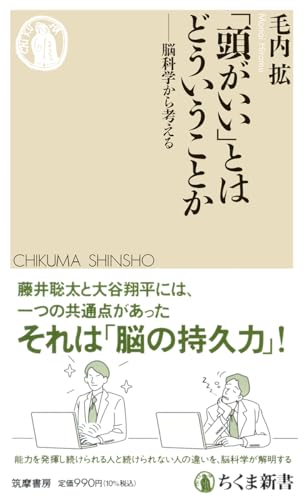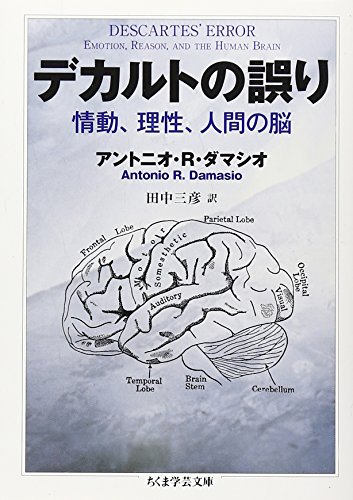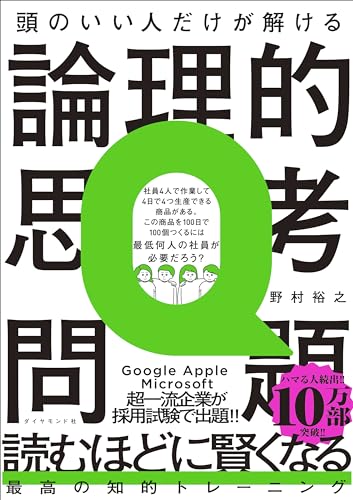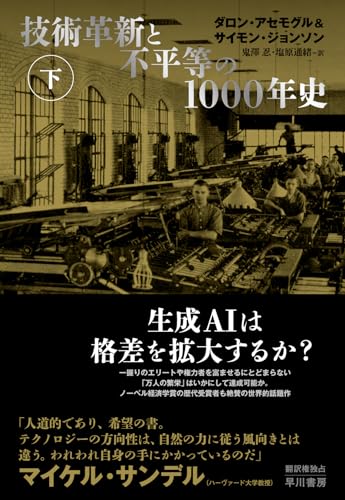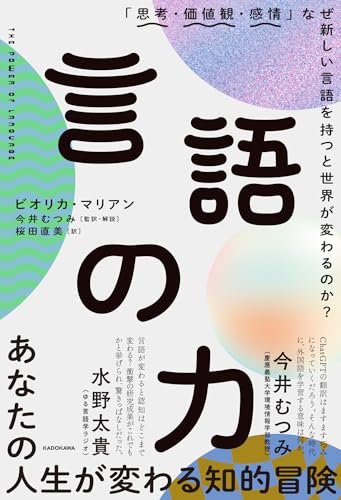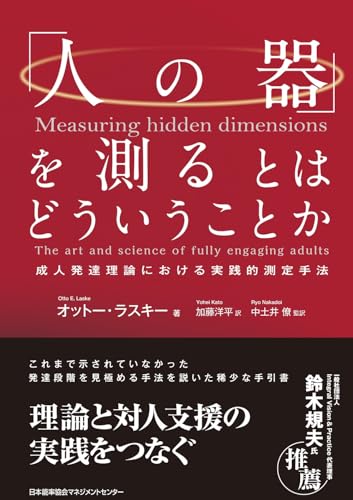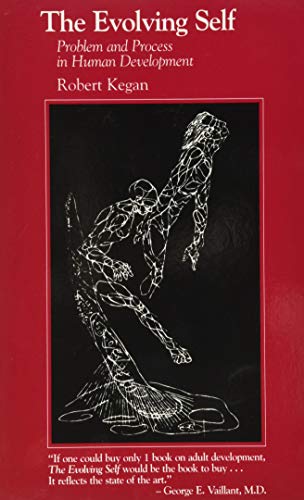まえがき
『私たちの思考プロセスにはいくつかの核となる要素があるが、相手の気持ちを変えられるのは、それらの要素と一致したときであるというのが、本書の主張である。』
リスト
- 事前の信念: 事前の信念に反する事実を突きつけられると、人は反論に出るかそっぽを向くかする → 相手の事前の信念を否定せず共通点に根ざした言い方を考えてみる
- 感情: 感情は伝染する。私的な感情を表しただけで他人の感情が誘発される → 感情を個人的なものと捉えない
- インセンティブ: 将来の危険を呼びかけても人は行動を変えない。恐怖や不安はやる気を失わせ人を固まらせてしまう → 即時の報酬や単純で肯定的なフィードバックを与えるなどポジティブな戦略をとる
- 主体性: 命令され主体性が制限されたと感じると、人は不安になり抵抗しやすくなる → 選択肢を与え主体性を高める
- 好奇心: たとえ重要でも、暗い見通しや気の滅入る内容の話は避けられる → 前向きな感情を誘発する、あるいはその話が物事を良くするために役立つことを明らかにする
- 心の状態: ストレスや恐れを抱えていると、安全策を取りがちになる → 自分の決断が他人や環境に無意識に影響されていることに留意し、状況を違った角度から見直す
- 他人1: 人は他人の判断に追従する傾向がある(社会的学習) → 過度の社会的学習が起きやすいことに留意する
- 他人2: 人は直感的に多数決を好む(平等バイアス)が、多数の人々が間違っていることもある → 集団内でその問題に長けている人を見極める
あとがき
まえがきを含めて、ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学』 (白揚社、2019年)より。タイトルは訳者あとがきの表現を借りました。リストは本文からの要約・引用です。
まえがきにある「核となる要素」は7つで、基本的には1要素につき1章ずつ割り当てられています。ただし他人は2章にわたって書かれているので、リストもそれを反映して8項目になりました。
こういった教養書の場合、特に洋書では、7要素の簡潔な定義や章ごとの要約があり、それを手掛かりにリスト化しています。しかし本書にはそういった手がかりが少なく、リスト化に時間がかかりました。
- タイトル: 事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学
- 著者: ターリ シャーロット(著)、上原 直子(翻訳)
- 出版社: 白揚社
- 出版日: 2019-08-11