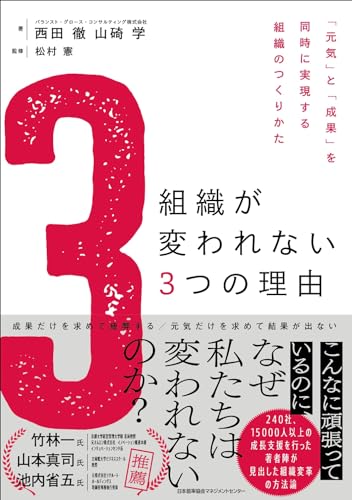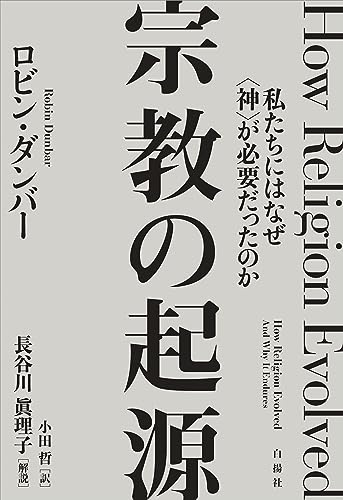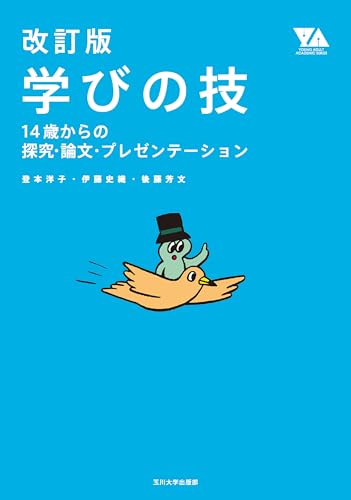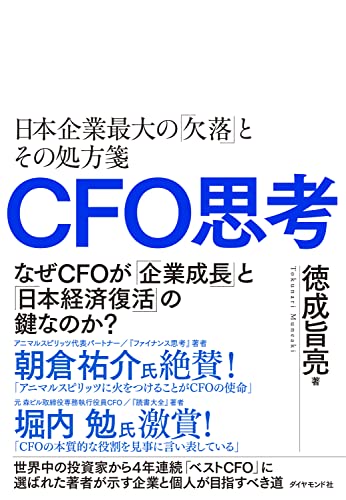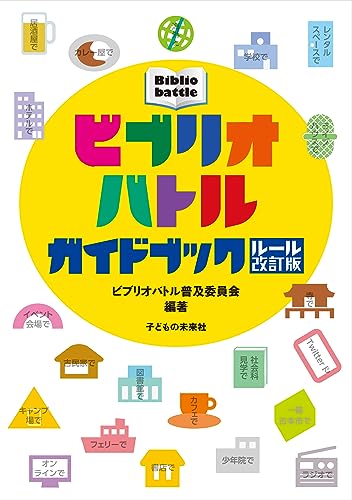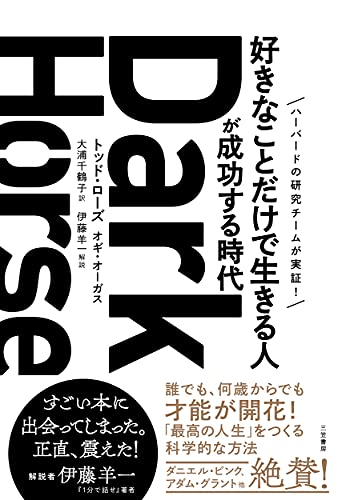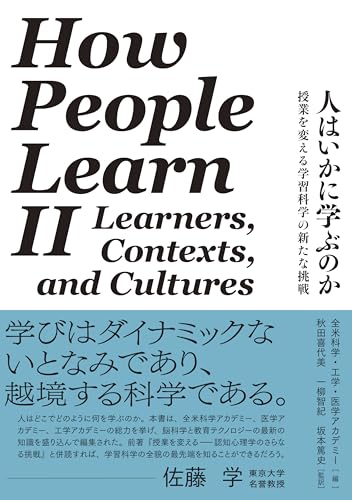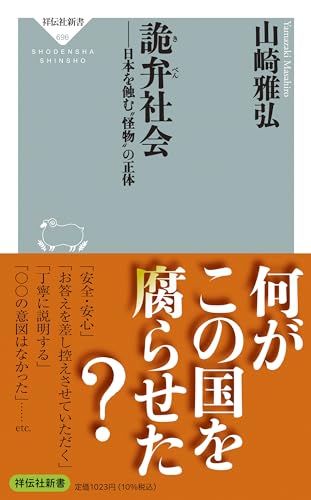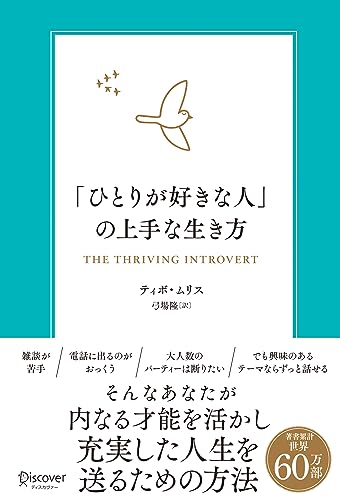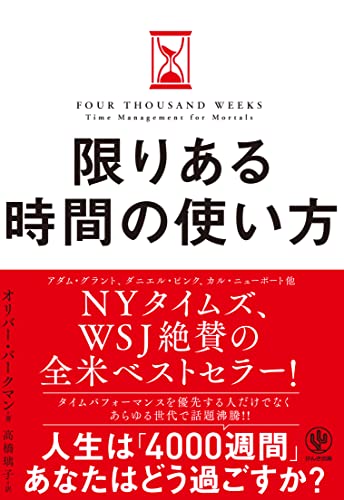まえがき
『著者らは、それぞれの数十年間にわたって組織変革に取り組んできましたが、様々な試行錯誤の中で、組織論における3つのコペルニクス的転回に気づきました。』
リスト
- 「対立」を力に変えられていない
- 「今、ここ」しか見えていない
- 実行するメンバーの内発的動機づけができていない
あとがき
まえがきを含めて、西田 徹、山碕 学『組織が変われない3つの理由 「元気」と「成果」を同時に実現する組織のつくりかた』 (日本能率協会マネジメントセンター、2023年)より。リストは目次からの引用です。
本書はこの3つの理由をそれぞれに掘り下げ、またそれぞれに解決する手段をていねいに紹介していきます。
- タイトル: 組織が変われない3つの理由 「元気」と「成果」を同時に実現する組織のつくりかた
- 著者: 西田 徹(著)、山碕 学(著)、松村 憲(監修)
- 出版社: 日本能率協会マネジメントセンター
- 出版日: 2023-12-27