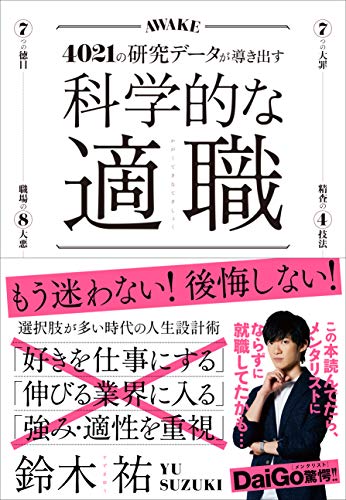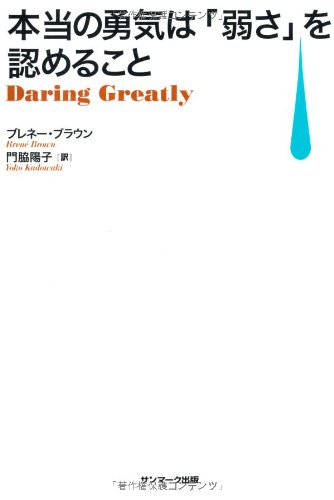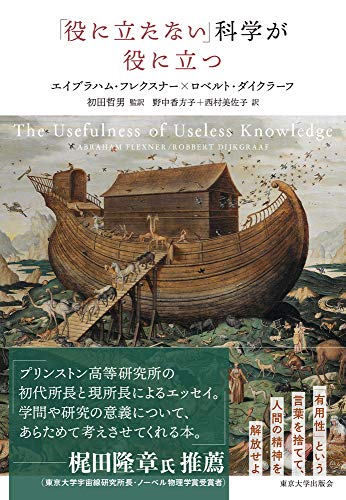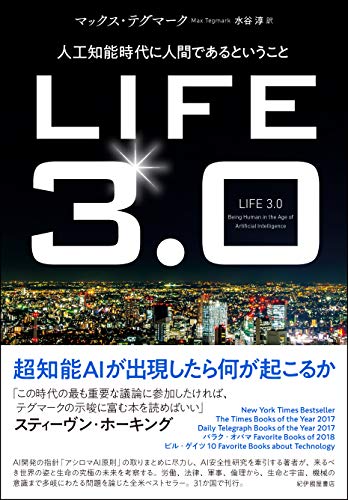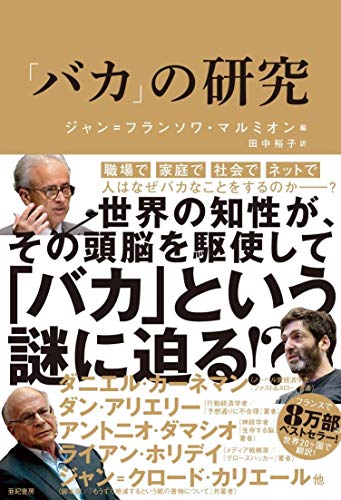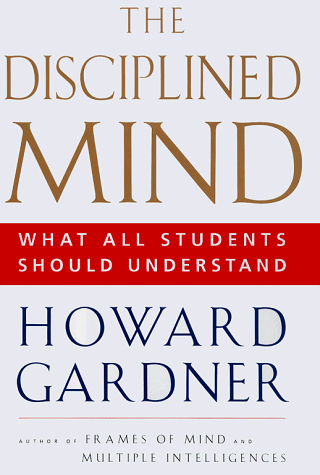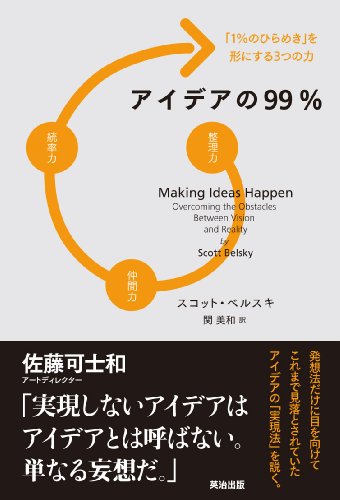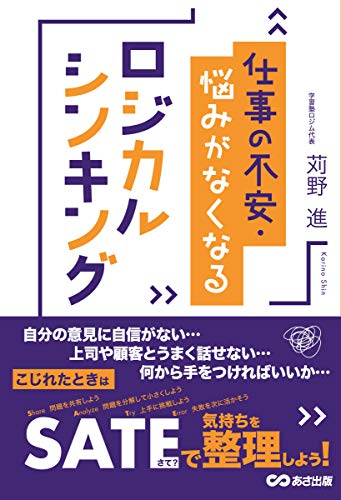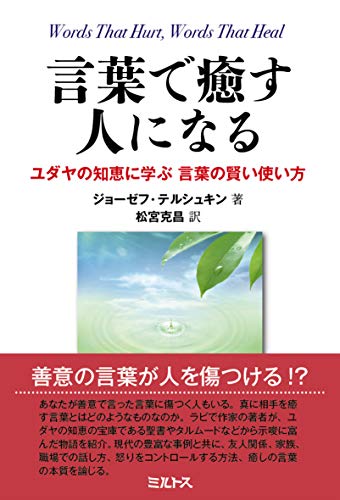まえがき
『これらの要素を満たさない仕事は、どれだけ子供のころから夢に見た職業だろうが、誰からもあこがれられる業種だろうが、最終的な幸福度は上がりません。逆に言えば、これらの要素がそろった仕事であれば、どんなに世間的には評価が低い仕事でも幸せに暮らすことができるわけです。』
リスト
- 自由: 仕事内容や働き方に裁量権がある
- 達成: 前に進んでいる感覚を得られる
- 焦点: モチベーションタイプに合っている
- 明確: なすべきこと、ビジョン、評価軸が明確である
- 多様: 作業内容にバリエーションがある
- 仲間: 組織内に助けてくれる友人がいる
- 貢献: どれだけ世の中の役に立っているかわかる
あとがき
まえがきを含めて、鈴木 祐 『科学的な適職 4021の研究データが導き出す、最高の職業の選び方』(クロスメディア・パブリッシング、2019年)より。リストは本書冒頭の表からの引用です。
- タイトル: 科学的な適職【ビジネス書グランプリ2021 自己啓発部門 受賞! 】
- 著者: 鈴木 祐(著)
- 出版社: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 出版日: 2019-12-13