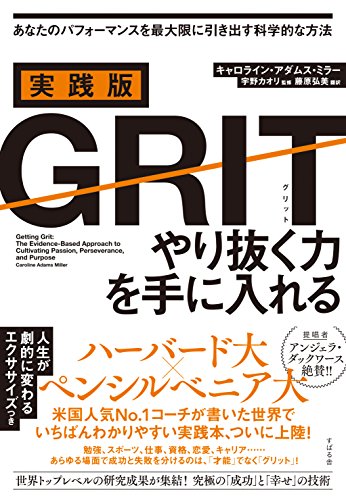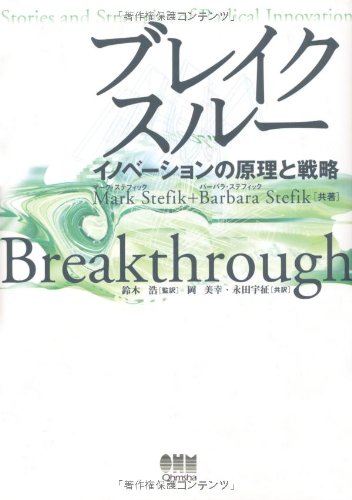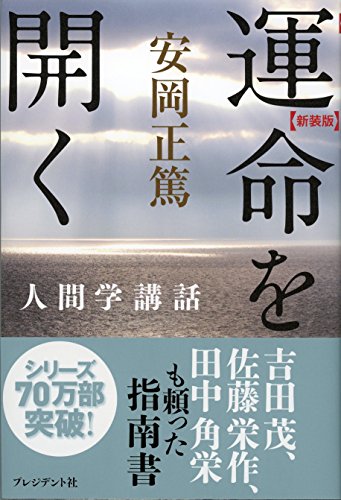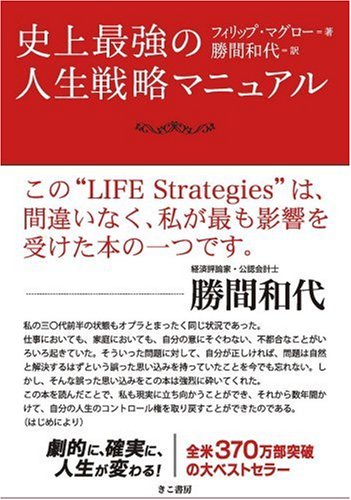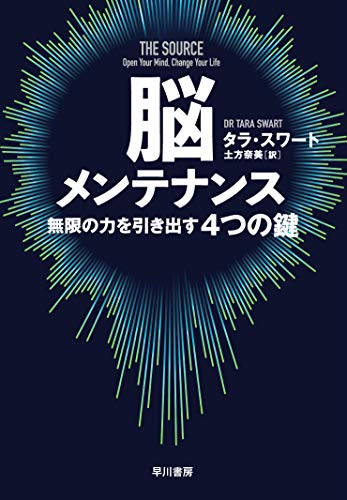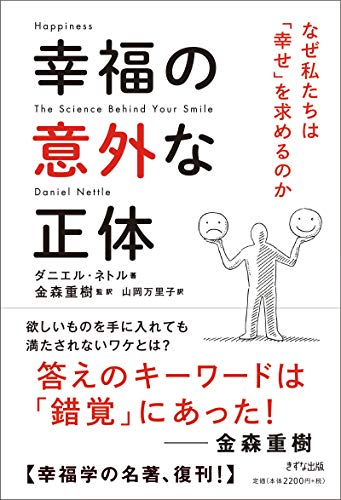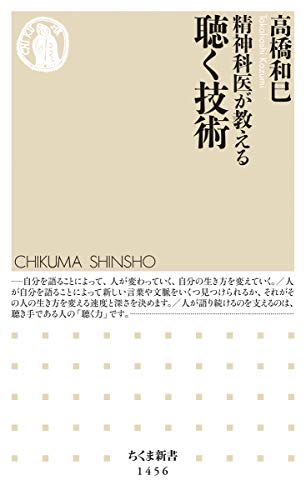まえがき
『自己効力感を持てるようになるには、バンデューラが発見した次の4つの戦略が役立つ。』
リスト
- 大きな最終目標につながる小さな目標を達成することで、何かを習得する経験を積んでいく。
- 達成したいと思う目標を実際に実現している人の近くに身を置くか、ロールモデルを持つ。
- あなたの能力を本気で信じてくれる、あなたにとって大きな存在となる人を持つ。
- ストレスに対する良い手段を持つ。瞑想、運動、ユーモア、コミュニティ参加など。
あとがき
まえがきを含めて、キャロライン・アダムス・ミラー 『実践版GRIT(グリット) やり抜く力を手に入れる』(すばる舎、2018年)より。リストは本文を編集して作成しました。
本書では 4→2→3→1 の順で紹介されていましたが、「自己効力感(セルフ・エフィカシー)の先行要因」の「経験→モデリング→社会的説得→生理的因子」に沿うように並べ替えました。
実際、本書でも「小さな目標を達成する」の項で『4つの戦略の中で、圧倒的に大きな効力を発揮するのがこの4番目の方法だ』と書かれています。
項目として自己効力感の先行要因をおさえてはいますが、バンデューラ自身が実際に瞑想が有効だとかの研究をしたわけではないと思いますので、著者の意見が紛れ込んでいる模様。文献が明示されていないので、もし見つけたら追記します。
- タイトル: 実践版GRIT(グリット) やり抜く力を手に入れる
- 著者: キャロライン・アダムス・ミラー(著)、宇野 カオリ(監修)、藤原 弘美(翻訳)
- 出版社: すばる舎
- 出版日: 2018-02-21