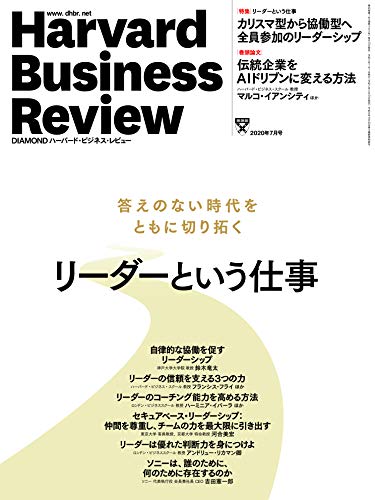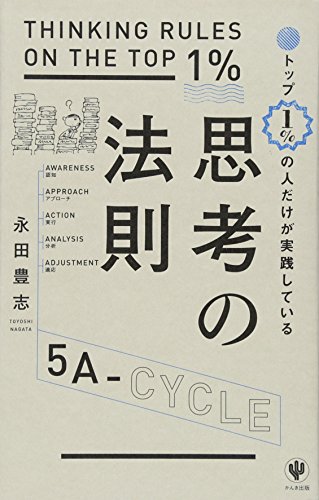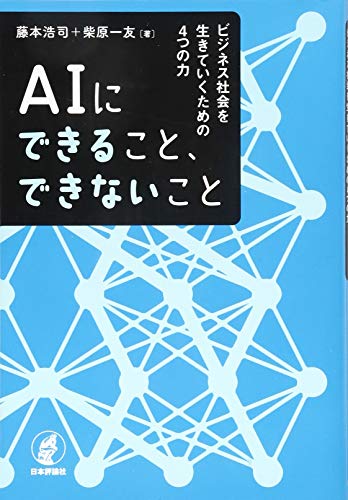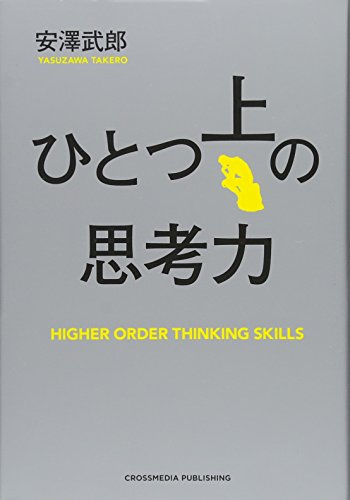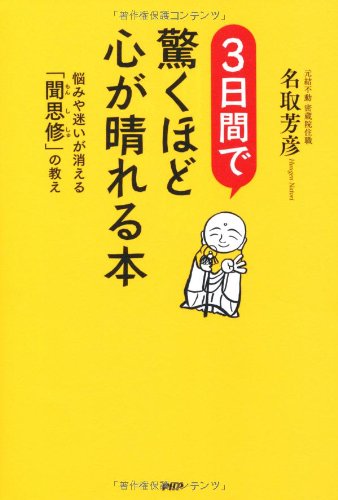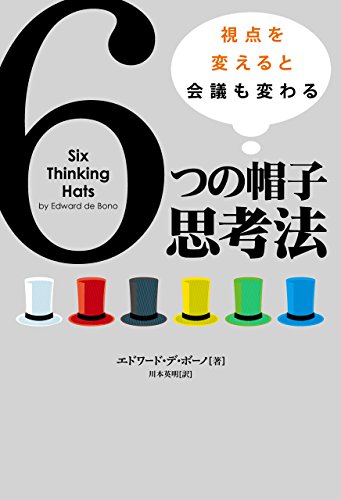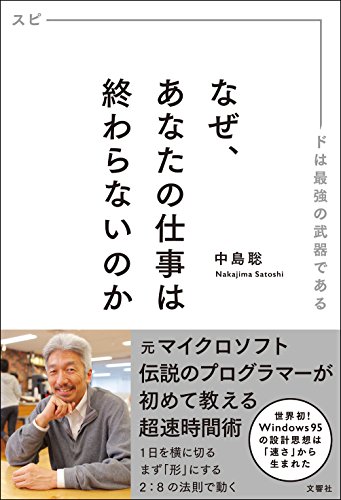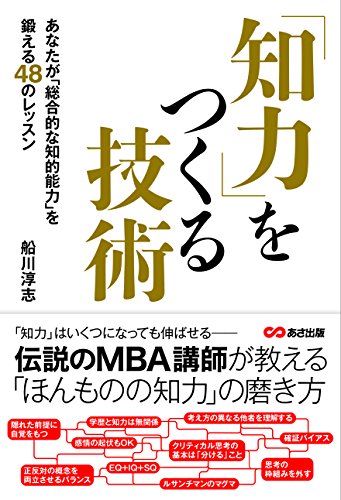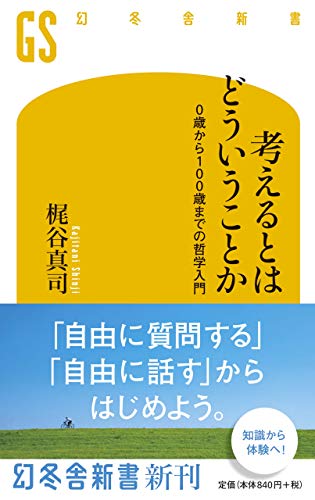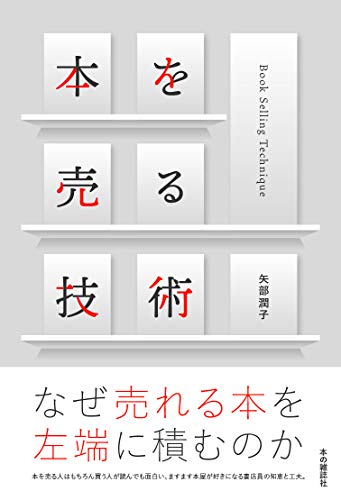まえがき
『みんな承知しているし既にやっていることという前提を外して、ずっと腰に提げていた袋を開陳したつもりです。』
リスト
- 新聞を読むこと
- 売り場にいること
- 品出しを優先すること
- 考えて並べること
- 本をよく見ること
- 手を動かすこと
- 売場とお客様に教わること
- 棚で語ること
- 本を売ること
- そして本を愛し過ぎないこと
あとがき
まえがきを含めて、矢部 潤子 『本を売る技術』(本の雑誌社、2020年)より。まえがきは、本書あとがきより。リストは、本書のまえがきと第一講のあいだに掲げられています。
著者は36年間の経験を持つベテラン書店員。本書は出版元である「本の雑誌社」営業部の杉江 由次さんによる矢部さんへのインタビュー集で、矢部さん自身の肉筆はあとがきのみです。
このあとがきが名文。本エントリのまえがきで引用した「腰に提げていた袋」とは、現役時代に言語化しそこねたノウハウの隠喩です。職人は自分の経験から得たものをこのような心持ちで言語化し、後進に託していけばよいのではと感じ入りました。
当初、リストの10ヶ条が36年間腰に提げていた袋のエッセンスであると思い吟味していたのですが、どうも違和感があります。
最終項目に「そして」とあるので、項目の順序に意味を持たせていらっしゃることが察せられます。しかしそうすると、「新聞を読むこと」が1番で、「売場とお客様に教わること」は7番めという順序が、ご本人の語られている内容と合致しないように思えます。また『本を売る技術』を語りつつ「本を売ること」を9番め、最終項目の前に置かれたことにはどんな含意があるのか。
検索してみると、インタビュアーである杉江さんのブログの2019年1月7日のエントリに、2019年の個人的な目標としてよく似たリストが掲げられています。ブログゆえいつか逸失してしまうかもしれないので引用しておくと:
2019年10ヶ条
本を読む
人に会う
話を聞く
口を噤む
心を鎮める
集中する
手を動かす
足を運ぶ
本を売る
感謝を伝える
1月7日(月) – 帰ってきた炎の営業日誌|WEB本の雑誌
全体によく似ていますし、どちらにも本を売るが9項めにあります。
杉江さんが本書を編集している間に矢部さんから10ヶ条を教えてもらい、自分向けにしつらえ直した可能性もあります。杉江さんがこのエントリをふくらませるかたちで「本屋で働く新しい人たちへの10ヶ条」をこしらえたのかもしれません。
経緯はともかく、本書で語られる「本屋に並べる本」への圧倒的なこだわりに比べると、「リストに並べる心得」へのこだわりはそれほどないのかなと、ちょっと残念に思いました。本好きのリストフリークとして。
- タイトル: 本を売る技術
- 著者: 矢部 潤子(著)
- 出版社: 本の雑誌社
- 出版日: 2020-01-23