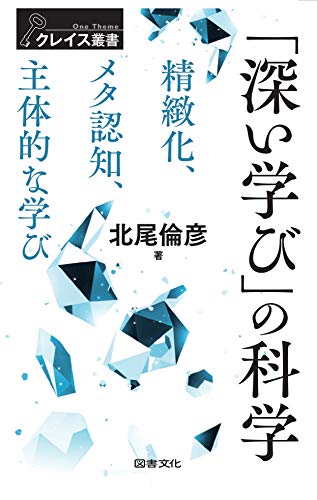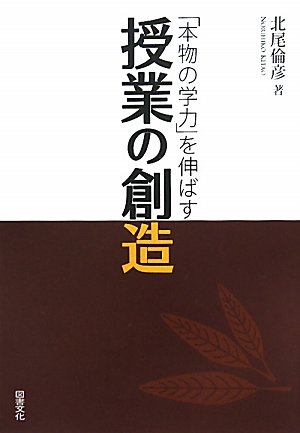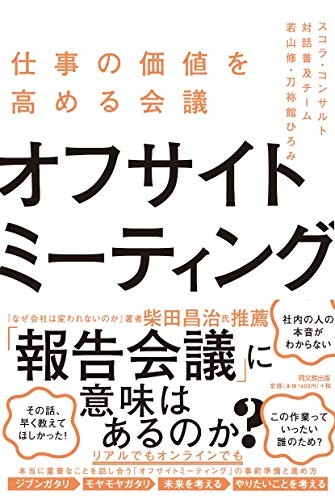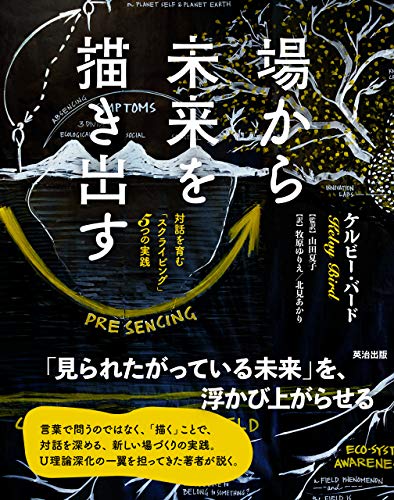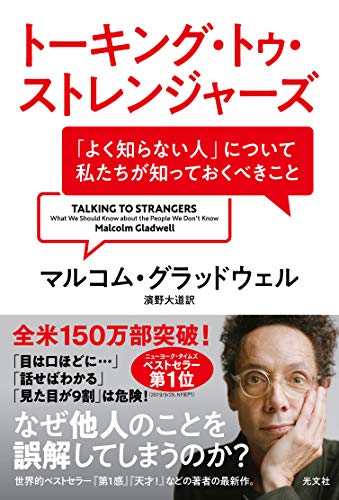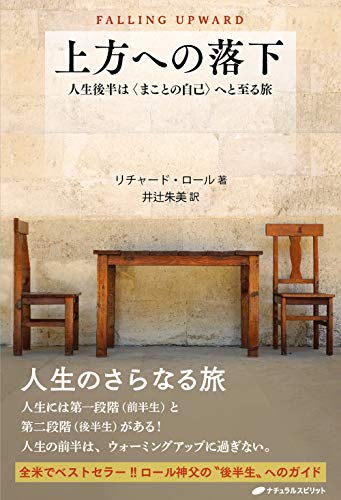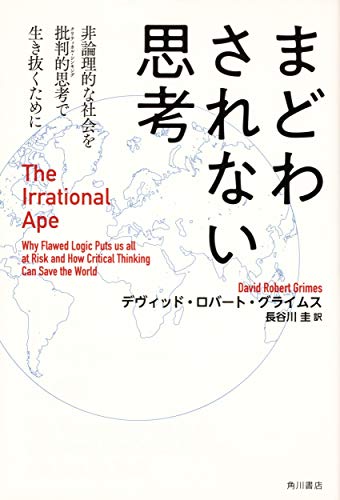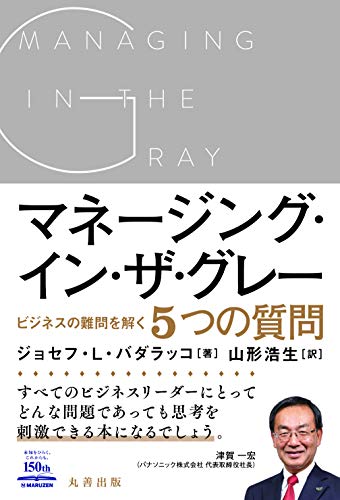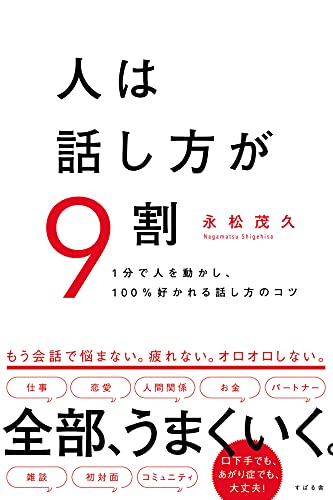まえがき
『(対話的な学びにおいては)形よりも中味が大切であるが、その中味について筆者は前著で次の三点を指摘した。』
リスト
- テキストとの対話:情報を集め、問題を考え、ノートに書いておく。
- 自己との対話:ノートを参照しながら自分はこう主張したいという想いを抱く。
- 他者との対話:対話において、他者の考えや主張を受け止めつつ、自分の考えや主張と突き合わせて練り上げる。
あとがき
まえがきを含めて、北尾 倫彦 『「深い学び」の科学: 精緻化・メタ認知・主体的な学び』(図書文化社、2020年)より。
まえがきの「前著」は『授業の創造―「本物の学力」を伸ばす』。同書から『学びを深めるという観点に絞って』その三点の要点を述べるという部分を要約してリスト化しました。
深い学びや主体的な学びは、「平成29・30年改訂学習指導要領」(文部科学省)で掲げられたスローガンで、本書はその解説書といった趣です。ですのでここでの「対話」は、文脈としては子供たちによる授業の中での対話を指しています。
引用元では「対話のための3つのステップ」という項で紹介されていましたが、タイトルにはその文脈がわかるように「的な学び」を入れました。
社会人教育でも、テキスト、自己、他者との対話という流れは援用できそうなので収集しました。
- タイトル: 「深い学び」の科学: 精緻化・メタ認知・主体的な学び
- 著者: 北尾 倫彦(著)
- 出版社: 図書文化社
- 出版日: 2020-01-30
- タイトル: 授業の創造―「本物の学力」を伸ばす
- 著者: 北尾 倫彦(著)
- 出版社: 図書文化社
- 出版日: 2011-07-01