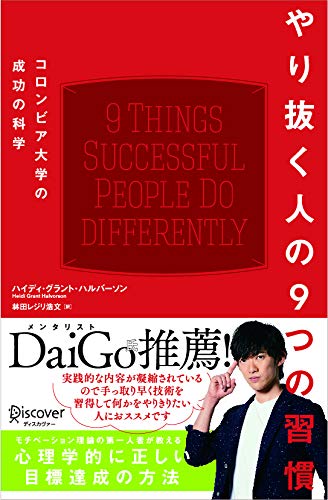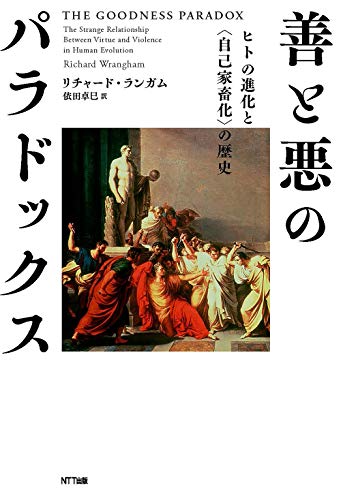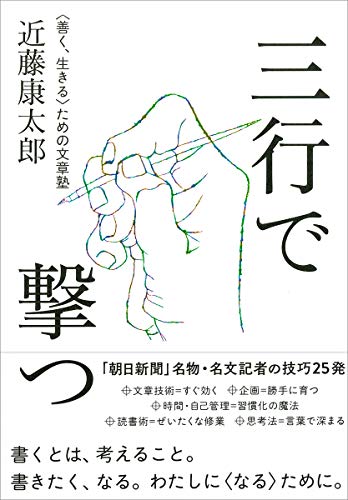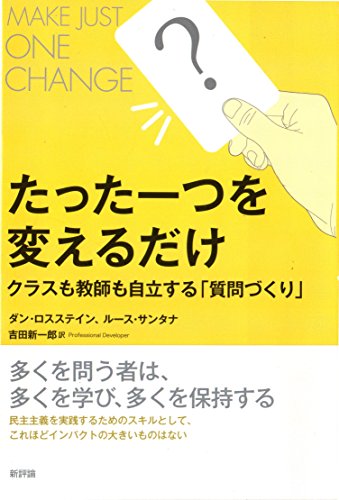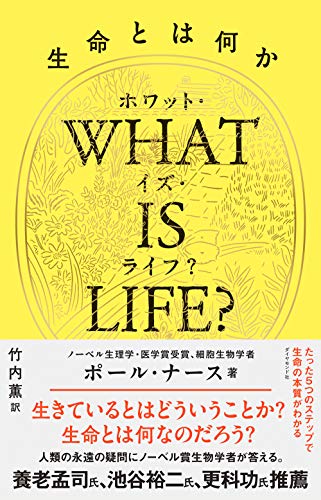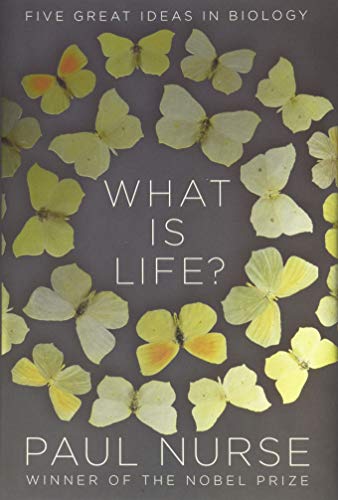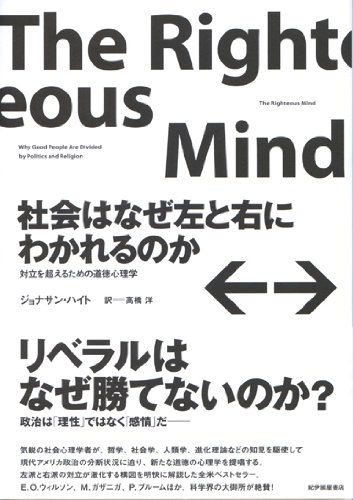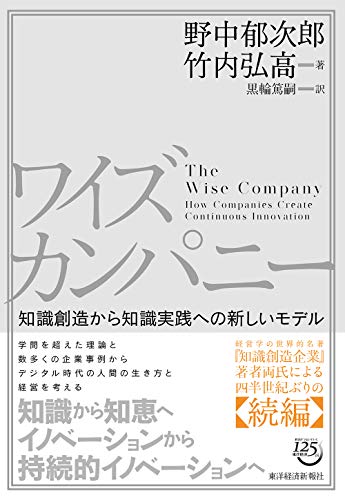まえがき
『「才能が成功に導いた」のではなく、彼らは「ある種の思考や行動によって、自らを成功に導いている」のです。』
リスト
- 目標に具体性を与える(メンタル・コントラスト)
- 目標達成への行動計画をつくる(if-thenプランニング)
- 目標までの距離を意識する(フィードバック、これから思考>これまで思考)
- 現実的楽観主義になる(成功体験の想起、ビジュアリゼーション、プランB)
- 「成長すること」に集中する(成長ゴール>証明ゴール、興味を持つ>ご機嫌でいる)
- 「やり抜く力」を持つ(グリット、拡張的知能観>固定的知能観)
- 筋肉を鍛えるように意志力を鍛える(意志力は有限、定期刺激で鍛錬)
- 自分を追い込まない(意志力を試さない、やめるときはすっぱり)
- 「やめるべきこと」より「やるべきこと」に集中する(シロクマ、代替if-thenプラン)
あとがき
まえがきを含めて、ハイディ・グラント・ハルバーソン 『やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2017年)より。リストは目次より。カッコ内は本文中のキーワードです。
ポジティブ心理学系の本に書かれていることが凝縮された感じ。必要最低限の文献に絞ったと思われる参考文献リストを含めてコンパクトな良書でした。
- タイトル: やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)
- 著者: ハイディ・グラント・ハルバーソン(著)、林田レジリ浩文(翻訳)
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 出版日: 2017-06-22