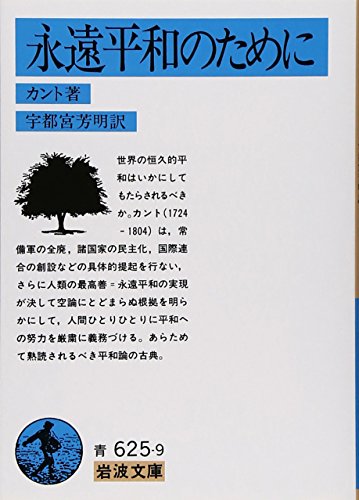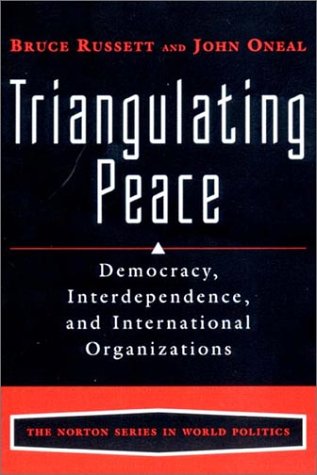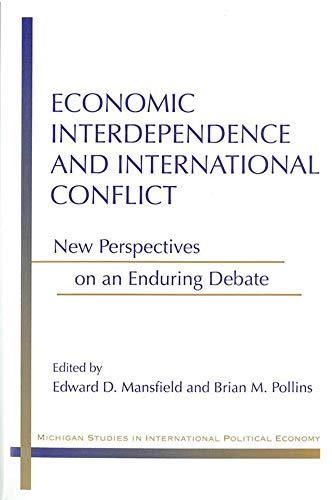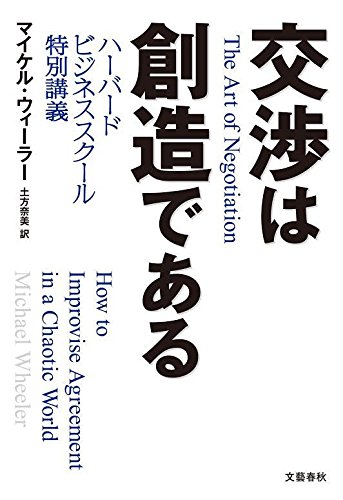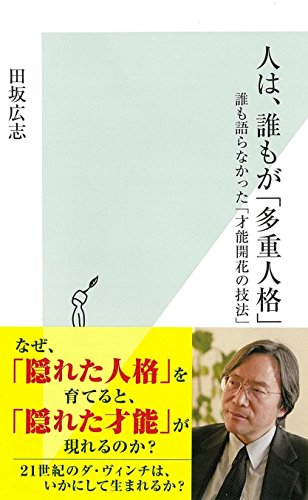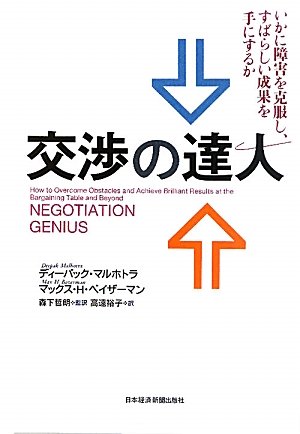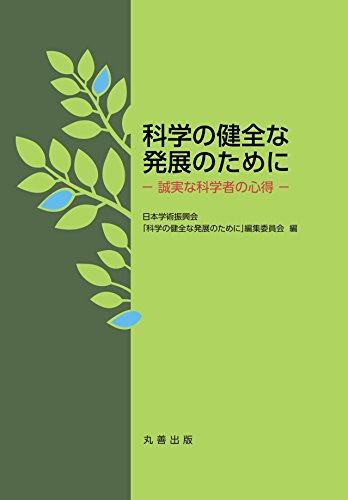まえがき
戦争のリスクを減らす5つの要件。
リスト
- 同盟関係をむすぶ
- 互いの相対的な軍事力が均衡する
- 互いに民主主義の程度が増す
- 互いの経済的依存関係が増加する
- 互いに加入している国際的組織が増加する
あとがき
高橋洋一『集団的自衛権巡る愚論に終止符を打つ! 戦争を防ぐための「平和の五要件」を教えよう』(現代ビジネス)より、やや編集しつつ引用。
リストはブルース・ラセットとジョン・オニール “Triangulating Peace”からの引用。著者らは過去の戦争データを分析し、リストの要素はそれぞれ40、36、33、43、24パーセント戦争のリスクを減らすことを見いだしたそうです。
5項目のうち、前2項目が『軍事力によるバランス・オブ・パワー論に依拠するリアリズム』、後3項目が『軍事力以外にも貿易などの要素を考慮し平和論を展開するリベラリズム』が重視する要素とのこと。後3項目はイマニュエル・カントが『永遠平和のために』で(たぶん)提唱した要素で、著者らは「カントの三角形」と呼んでいます。ちなみに “Triangulating Peace” の副題は “Democracy, Interdependence, and International Organizations” 。タイトルを見るかぎりは、著者らはリベラリズム派のようですね。
5つの要件が実際にどう書かれているか、原著をあたっていませんが、ラセットが寄稿した別の本 “Economic Interdependence and International Conflict” での紹介によれば、第2項目は “a wide imbalance of power between two states” となっています。つまり戦争リスクを下げるのは「2国間の力のアンバランス」(が解消されること)。軍拡方向であれ軍縮方向であれバランスが重要だとすると、記事の『相対的な軍事力(標準偏差分)が一定割合増す』という言葉では誤読を招きそうなので、編集を加えました。
- タイトル: 永遠平和のために (岩波文庫)
- 著者: カント(著)、Kant,Immanuel(原著)、芳明, 宇都宮(翻訳)
- 出版社: 岩波書店
- 出版日: 1985-01-16
- タイトル: Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations (The Norton World Politics)
- 著者: Russett, Bruce(著)、Oneal, John R.(著)
- 出版社: W W Norton & Co Inc
- 出版日: 2001-01-01
- タイトル: Economic Interdependence and International Conflict: New Perspectives on an Enduring Debate (Michigan Studies In International Political Economy)
- 著者: Mansfield, Edward Deering(編集)、Pollins, Brian M.(編集)
- 出版社: University of Michigan Press
- 出版日: 2003-05-12