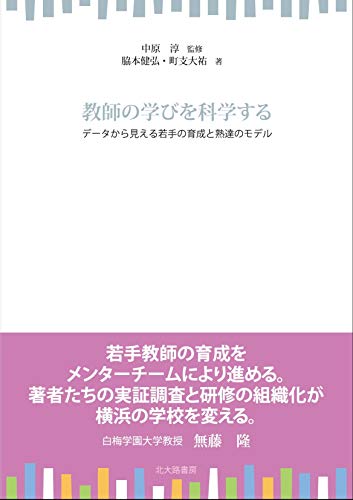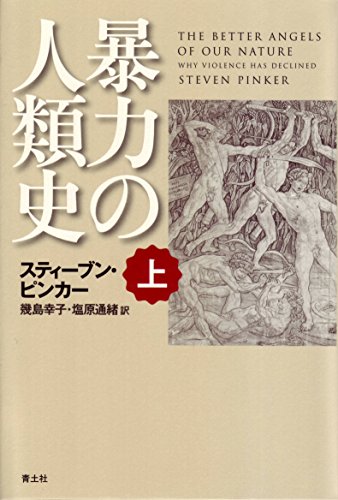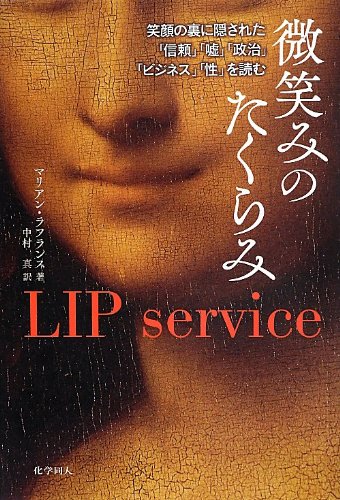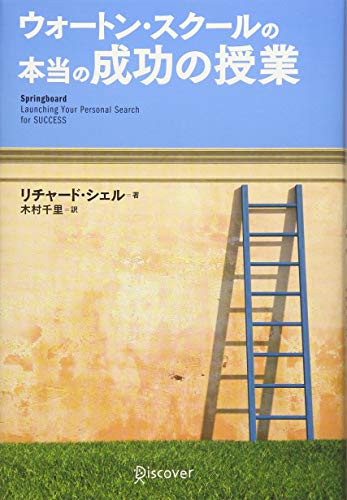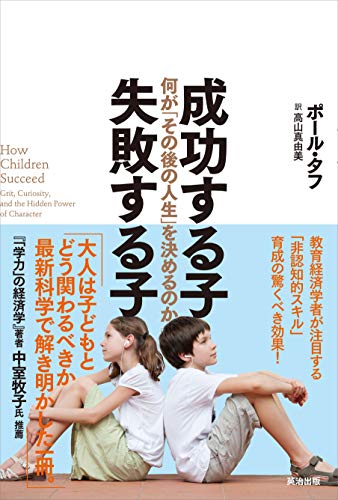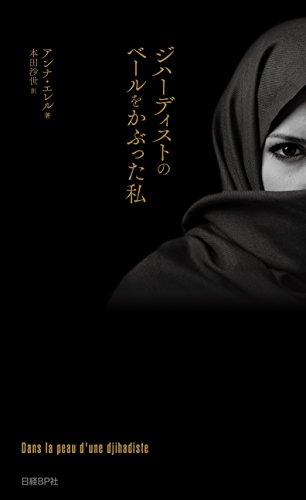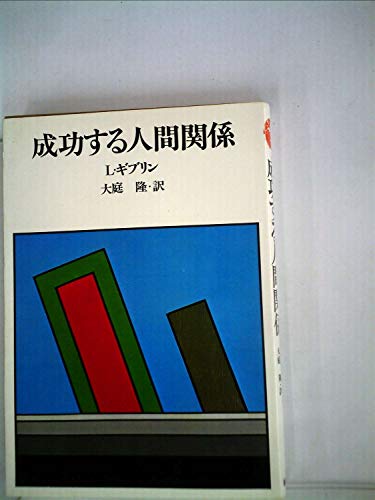まえがき
『Korthagenらは、理論と実践を繋ぐことの重要性を指摘し、リアリスティック・アプローチというアプローチを提案した。リアリスティック・アプローチにおいては、教師の経験を基盤に学習が行われるが、その学習の具体的方法とされているのがALACTモデルである。』
リスト
- Action (行為)←有益な経験を見い出す支援
- Looking back (振り返り)← 受容・共感・誠実・具体性
- Awareness of essential aspects (本質的への気付き)←受容・共感・誠実・具体性・対立の概括・「今ここ」の利用・物事を明確にする支援
- Creating alternative methods of action (新しいやり方の考案)←これまでのスキルの全て+解決策を発見・選択する支援
- Trial (試み)←学習プロセスを継続する支援
あとがき
脇本 健弘ほか『教師の学びを科学する: データから見える若手の育成と熟達のモデル』より。リストは参考文献(1)からの編集・引用です。
各項目の先頭が、学習者である教師が踏むステップ。『←』より後は、そのステップにいる学習者に対して教育者(教師の教師)が発揮すべきスキルです。
Kolbの経験学習モデルとほとんど同じですが、Actionに戻す前にTrialという重複するように見えるステップを敢えて置いているところに特徴があります。
- タイトル: 教師の学びを科学する: データから見える若手の育成と熟達のモデル
- 著者: 中原 淳(著)、脇本 健弘(著)、町支 大祐(著)、中原 淳(監修)
- 出版社: 北大路書房
- 出版日: 2015-05-18
(1) Korthagen, F. “Reflective thinking as a basis for teacher education.” Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (69th, Chicago, IL, March 31-April 4, 1985).