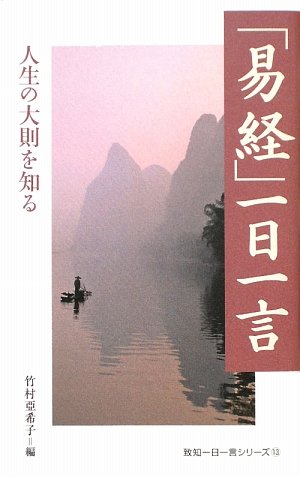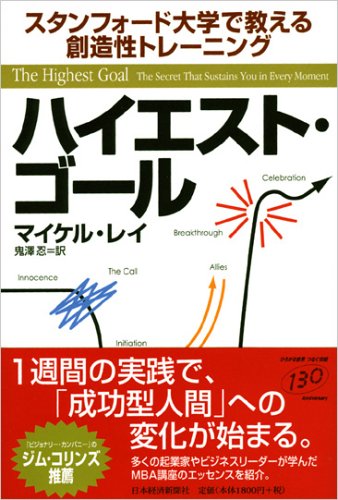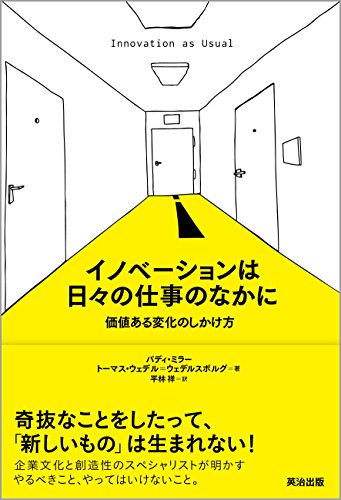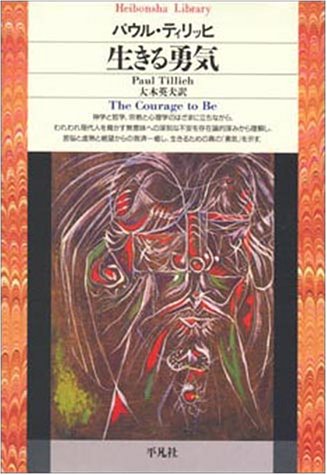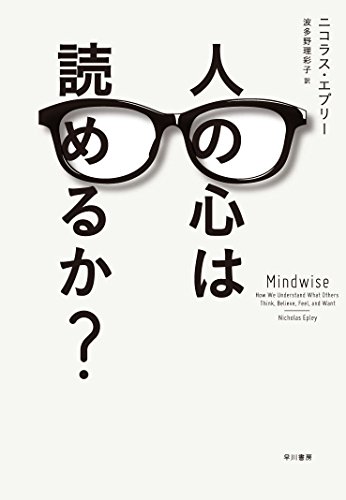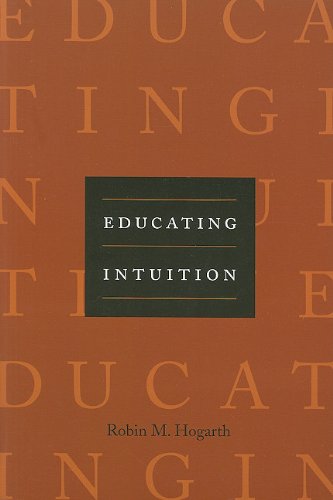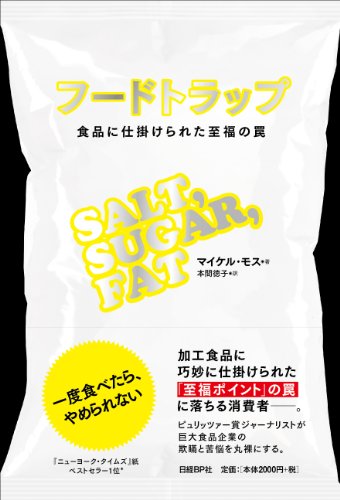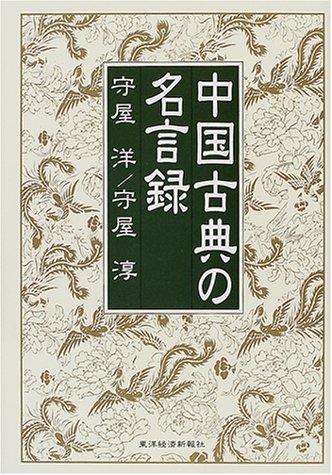まえがき
『易経六十四卦の乾為天の卦には、龍になぞらえて、志の達成までの変化の過程が次の六段階で記されている。この六段階を「
リスト
- 【
潜龍 】 高い志を描き、実現のための力を蓄える段階。 - 【
見龍 】 基本を修養する段階。 - 【君子終日
乾乾 】 創意工夫し、独自性を生み出そうとする段階。 - 【
躍龍 】 独自の世界を創る手前の試みの段階。 - 【
飛龍 】 一つの志を達成し、隆盛を極めた段階。 - 【
亢龍 】 一つの達成に行き着き、窮まって衰退していく段階。
あとがき
まえがきを含めて、竹村 亞希子『「易経」一日一言』(致知出版社、2009年)より。著者の別の著書(『リーダーの易経』)によると、躍龍は龍の名前としては易経本文に出てくるものではなく、著者が読者の便宜のために添えたとのこと。
「飛躍」という言葉はここから来ているのかな。「躍」でもまだ飛び上がっていないわけで、実質的には「飛」の段階だけが飛翔フェーズということになります。6段階の時間的な関係は明らかではありませんが、なんだか短そうです。
ちなみに原文はこんな感じ。
潜龍勿用。
見龍在田。利見大人。
君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。
或躍在淵。无咎。
飛龍在天。利見大人。
亢龍有悔。
- タイトル: 「易経」一日一言 (致知一日一言シリーズ)
- 著者: 竹村 亞希子(著)、竹村 亞希子(編集)
- 出版社: 致知出版社
- 出版日: 2009-02-25