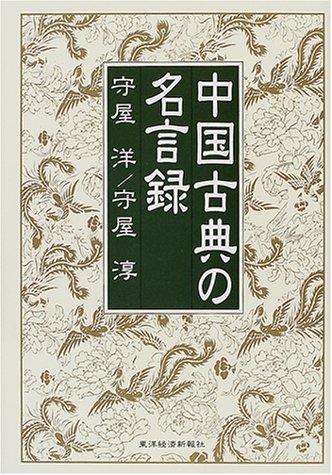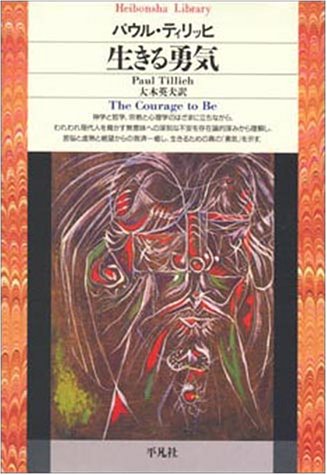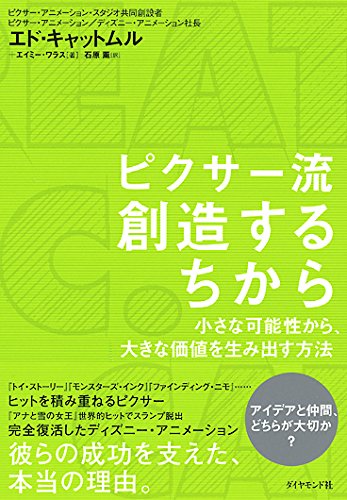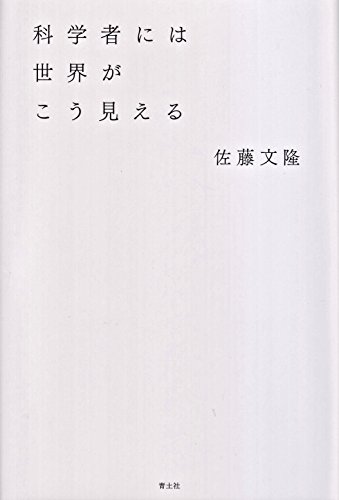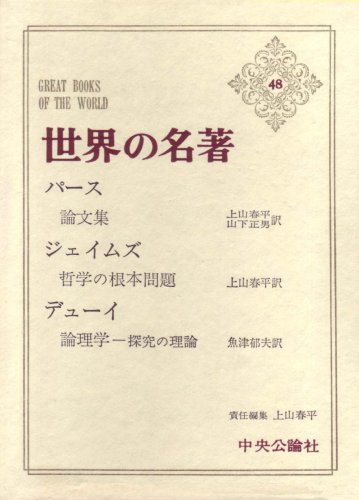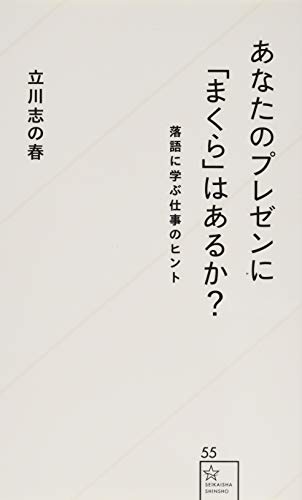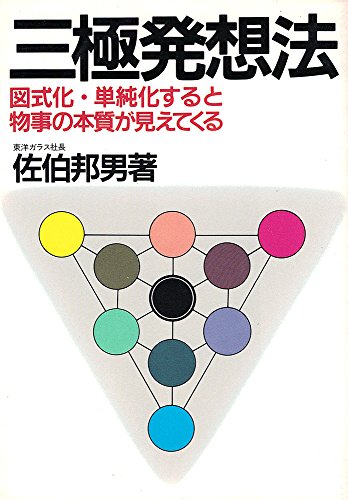まえがき
君子に九思(きゅうし)あり(君子は、つねに九つのことを肝に銘じていなければならない)。
リスト
- 視(み)るは明(めい)を思い(物を見るときは明らかに)、
- 聴(き)くは聡(そう)を思い(物を聴くときは神経をとぎすまし)、
- 色(いろ)は温(おん)を思い(顔色は穏やかに)、
- 貌(ぼう)は恭(きょう)を思い(容貌は慎み深く)、
- 言(げん)は忠(ちゅう)を思い(発言は誠実に)、
- 事(こと)は敬(けい)を思い(行動は慎重を旨とし)、
- 疑(うたが)わしきは問(と)うを思い(疑問を感じたら相手に尋ね)、
- 忿(いか)りには難(なん)を思い(腹が立ったときは後難に思いを致し)、
- 得(う)るを見ては義(ぎ)を思う(利益を見たら道義を忘れないことである)。
あとがき
まえがきを含めて守屋 洋、守屋 淳『中国古典の名言録』(東洋経済新報社、2001年)から編集のうえ引用。リストは『論語』季氏篇からの採録。
いいリストですが、いかんせん項目が多くて覚えられそうにない。君子の道は四易ではなかったのか。それとも当時の人は、これくらいの文章はすぐに覚えられたのかな。