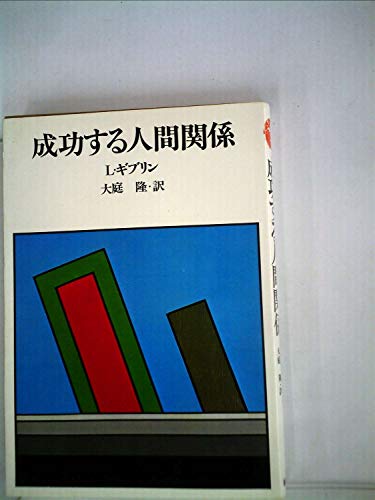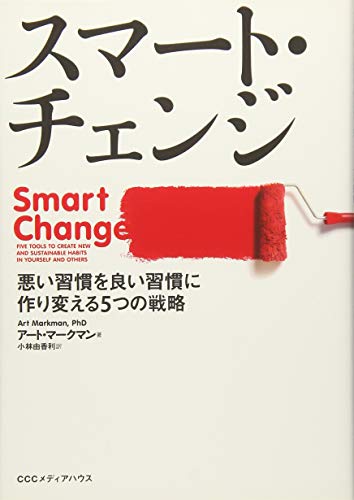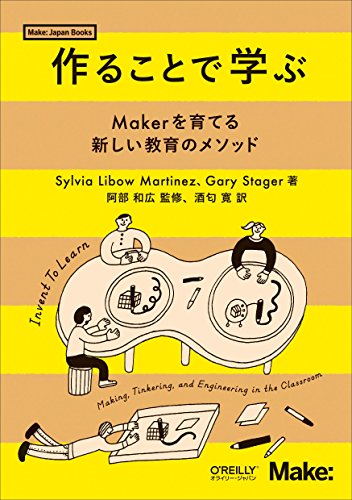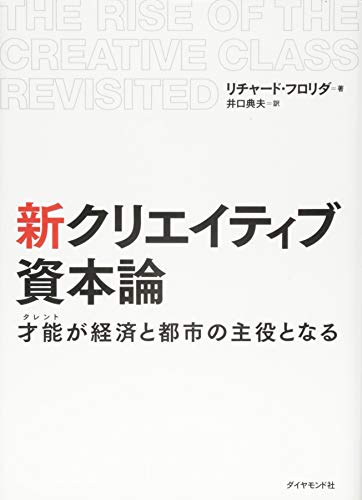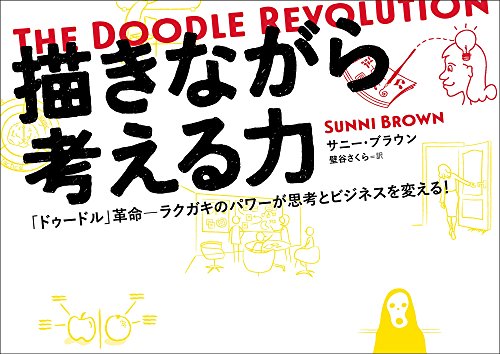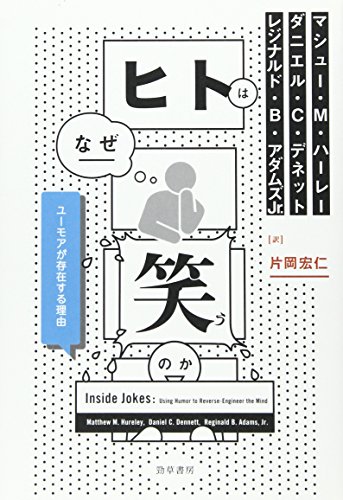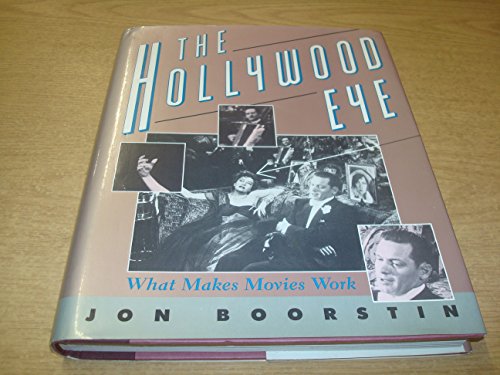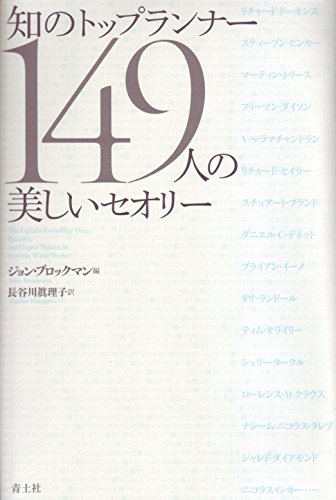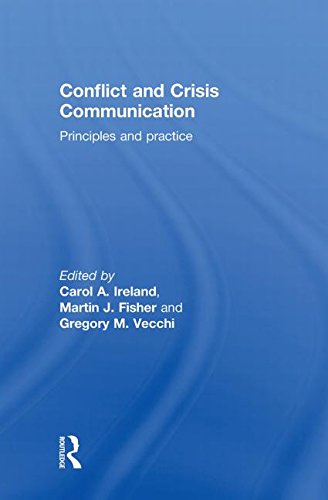まえがき
FBI(アメリカ連邦捜査局)のCNU(危機的状況における交渉ユニット)が定義した、交渉相手(たとえば誘拐犯)に行動を促すにいたるステップとは。
リスト
- 【アクティブ・リスニング】 相手の話を聞き、問いかけ、促し、理解する。(active listening)
- 【共感】 相手の感情を理解する。これは効果的なリスニングの副産物でもある。(empathy)
- 【相互信頼】 一方的に話を聞く状態から、話を聞いてもらえる状態になる。(rapport)
- 【影響】 問題を平和的に解決できる現実的な策を共に検討し、示唆する。(influence)
- 【行動変容】 相手が示唆を受け容れ、行動を変える。(behavioral change)
あとがき
岡本 純子『ハーバードとFBIで習う「最強の説得法」とは?』(東洋経済オンライン、2015/06/16)で『FBIで開発された「魔法のテクニック」』として紹介されていました。ホントかいなと思って調べてみたところ、Gregory M. Vecchiらの”Conflict and Crisis Communication: Principles and Practice”という本を経由して、参考文献(1)にたどりつきました。本当みたいです。FBIの交渉術というキャッチが使えるせいか、多くのブログで紹介されていました。
リストは参考文献(1)を要約しつつ翻訳したもの。アクティブ・リスニングのスキルなどをていねいに紹介してくれる、読みやすく興味深い論文でした。
ステップ1と2の「行動」により、3、4、5の「状態」へと、階段を上るように進んでいくべしという感じです。なおタイトルのBCSMは”Behavioral Change Stairway Model”。
(1) Vecchi, Gregory M., Vincent B. Van Hasselt, and Stephen J. Romano. “Crisis (hostage) negotiation: Current strategies and issues in high-risk conflict resolution.” Aggression and Violent Behavior 10.5 (2005): 533-551.