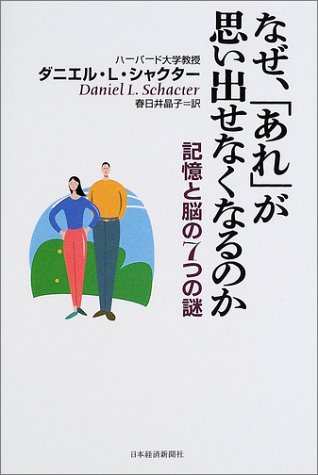まえがき
『記憶のエラーは、基本的に7つのパターンに分類することができる。』
リスト
- 物忘れ (Transience) …… 時間がたつにしたがって記憶が弱まったり失われたりする
- 不注意 (Absent-mindedness) …… 記憶すべきときに注意が別の何かに向けられていたために、もともと記憶されなかったり必要な時に思い出せなかったりする〈上の空〉
- 妨害 (Blocking) …… 知っていることなのに必要なときに思い出せない〈度忘れ〉
- 混乱 (Misattribution) …… 幻想と現実を勘違いして記憶したり、新聞で読んだことを友人から聞いたものとして記憶してしまう。デジャ=ヴュ、無意識の盗作、目撃者による犯人の誤認など
- 暗示 (Suggestibility) …… 過去の出来事を思い出そうとしているときに、誘導尋問や示唆によって誤った記憶が植えつけられる
- 書き換え (Bias) …… 無意識のうちに、あるいは意図的に、過去の経験を現在の知識に基づいて編集したり書き換えたりする
- つきまとい (Persistence) …… 忘れてしまいたい不快な情報や経験が繰り返し思い出される
あとがき
まえがきを含めて、ダニエル L.シャクター『なぜ、あれが思い出せなくなるのか: 記憶と脳の7つの謎』 (日経BPマーケティング(日本経済新聞出版、2002年)より。リストは本文を編集・引用して作成しました。英語は原著からの引用です。なお文庫版が出ています。
原著のタイトルは “The Seven Sins of Memory” なので、直訳すれば「記憶の7つの大罪」でしょうが、訳書に従いました。
7つの罪は大きく2つのカテゴリに分けられます。
これら七つのエラーのうちの最初の三つ――物忘れ、不注意、妨害は、記憶が抜け落ちること、つまりなにかを思い出そうと努力しても、ある特定の事実、出来事、考えを思い出せない現象のことである。注意散漫なときにしたことが後で思い出せなくなったり、なにかが邪魔をして、思い出したいことがどうしても出てこない状態である。これに対して残りの四つ――混乱、暗示、書き換え、つきまといは、どれも脳の指令が原因で起こる。つまり、記憶が不正確なものに変わってしまったり、忘れたいと思っても忘れることができなくなるケースである。
タイトル: なぜ、あれが思い出せなくなるのか: 記憶と脳の7つの謎
著者: ダニエル L.シャクター(著)、春日井 晶子(翻訳)
出版社: 日経BPマーケティング(日本経済新聞出版
出版日: 2002-04-01
#デジャヴ #デジャブ