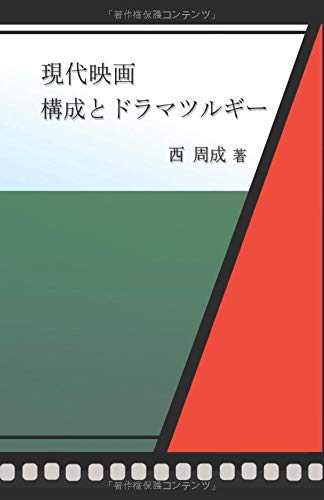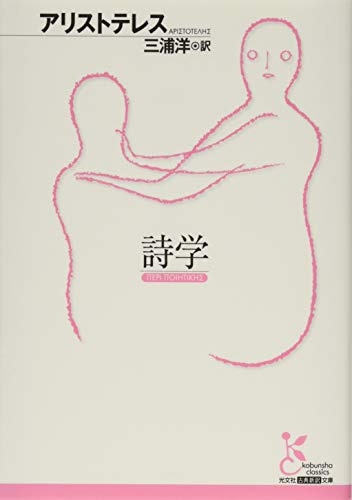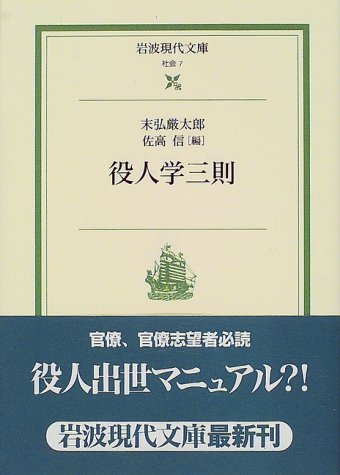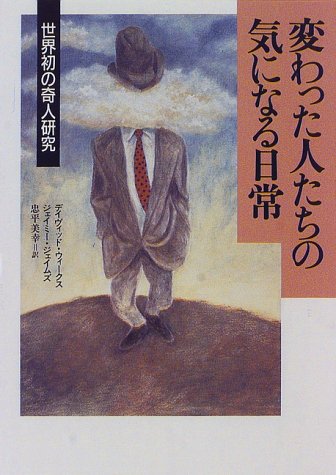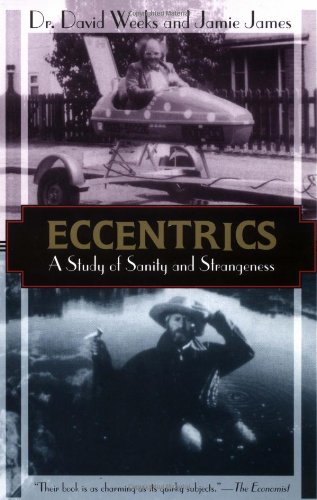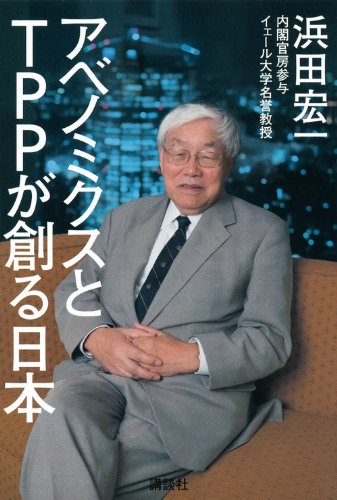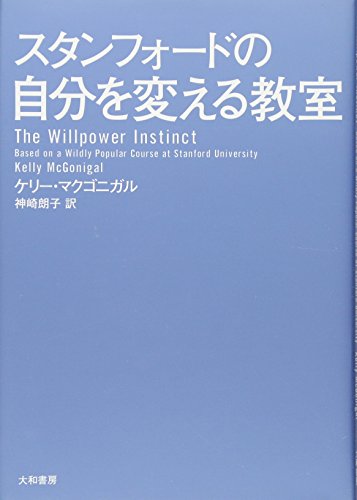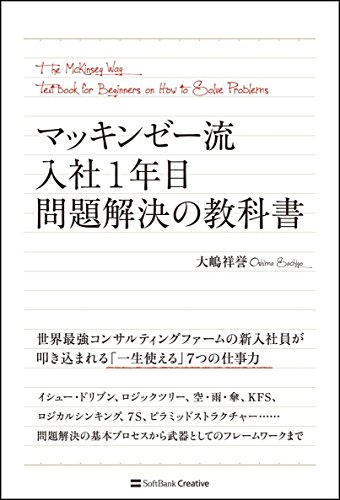まえがき
『フランスの古典主義演劇では、三一致の法則(三単一の法則)が規範とされた。これは時間と場所と筋の一致(略)を理想とする。』
リスト
- 【時間の一致】一日以内にすべての事件が終わる
- 【場所の一致】 場所は一つ
- 【筋の一致】 主筋だけで副次的な筋はない
あとがき
まえがきを含めて、西 周成 『現代映画 構成とドラマツルギー』(合同会社アルトアーツ、2016年)より。リストは本文を編集して作成しました。
Wikipedia(日本語版)、日本大百科全書(ニッポニカ)などにも項目がある、演劇界では知られた要素の模様。引用元によれば〈アリストテレスの『詩学』における優れた悲劇のあり方を拡大解釈したものである〉とのこと。
なお『詩学』 (光文社、2019年)では、この法則が拡大解釈というより曲解であることが丹念に述べられていました。『詩学』 はカテゴリ分けや列挙が論理的なので、『詩学』に書いてあるのなら、という感じで受け取ってしまいやすいかも。
たとえ曲解であってもそれだけ影響力を持ったということは、枠組みとしての妥当性が高いのでしょうね。「時間と空間ともう一つ」という類型は比較的よく見かける気がします。
- タイトル: 現代映画 構成とドラマツルギー
- 著者: 西 周成(著)
- 出版社: 合同会社アルトアーツ
- 出版日: 2016-03-18