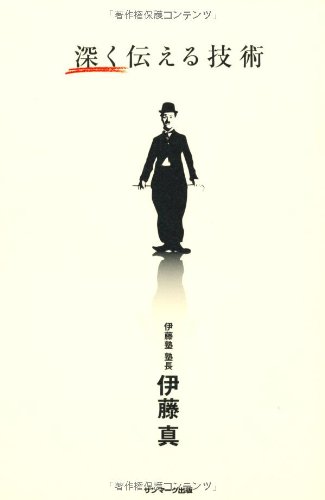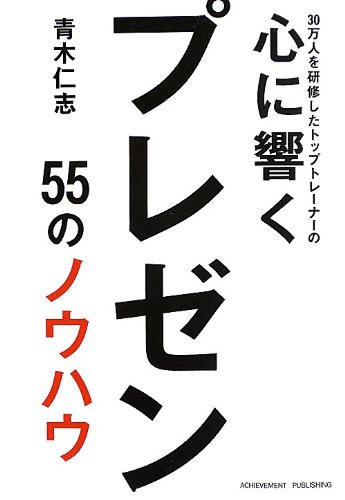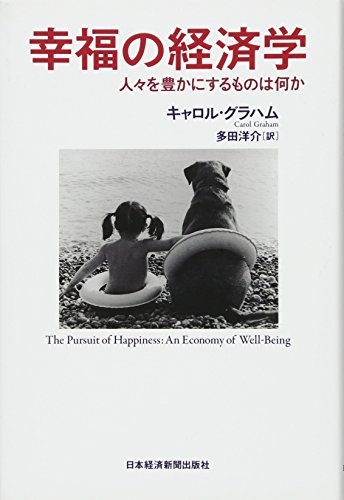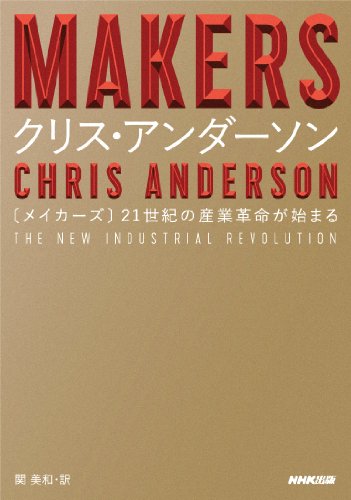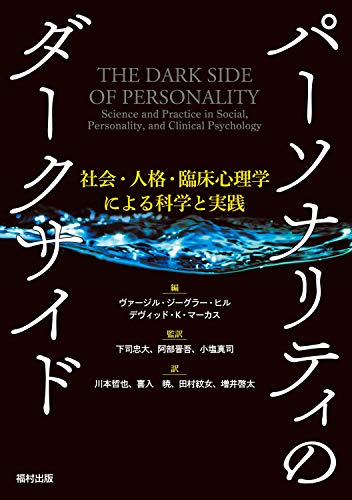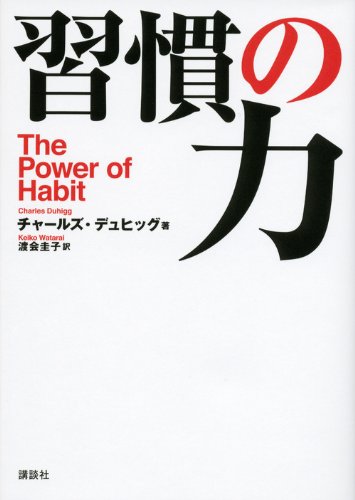まえがき
『保証しよう。これらを1日の終わりに問えば、人生がさらによくなると。』
リスト
- 大切にしている人たちが大切にされていると感じているか、確かめたか。
- 世界を善くする何かをしたか。
- 自分の体をより強くしなやかにするように整えたか。
- 将来の計画を見直し、磨きをかけたか。
- 独りのときでも、人に見られているときと同じように行動したか。
- 不親切な言動を避けたか。
- 価値のある何かを成し遂げたか。
- 恵まれていない人を助けたか。
- 素晴らしい思い出を作ったか。
- 生きているという驚くべき贈り物に感謝したか。
あとがき
Geoffrey James “10 Questions That Create Success” | Inc.com より。まえがきも本文からの翻訳・引用です。1年半も前のエントリなので、ライフハッカー[日本版]とかに転載されているかと検索してみましたが見当たらなかったので翻訳。直訳と意訳の中間くらいです。