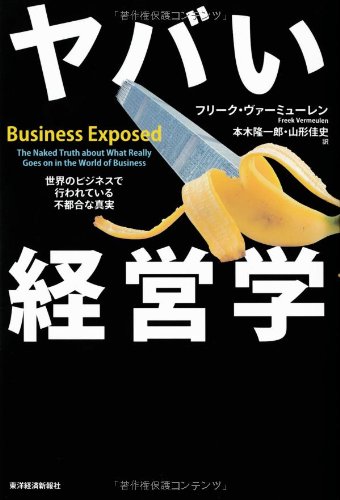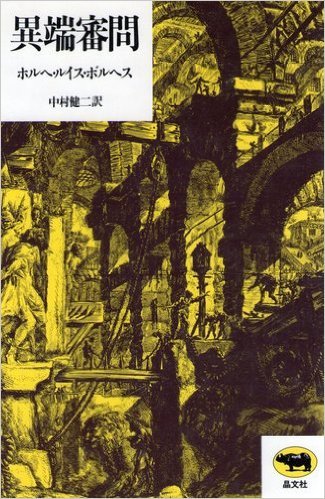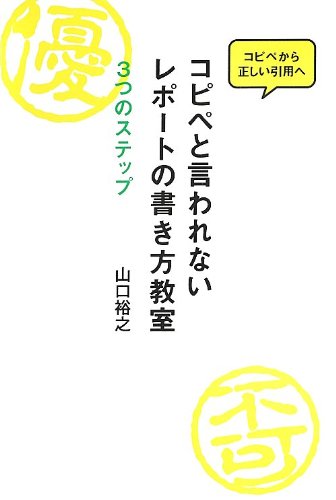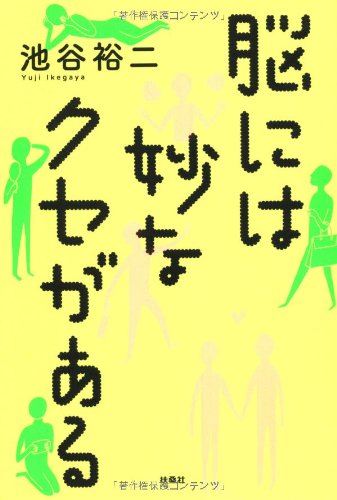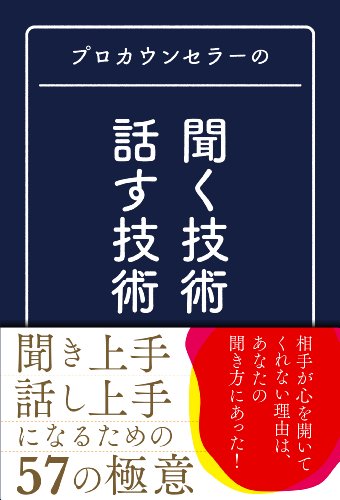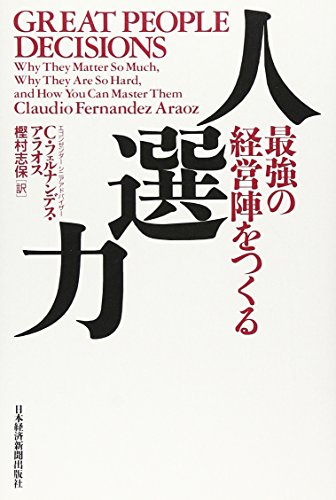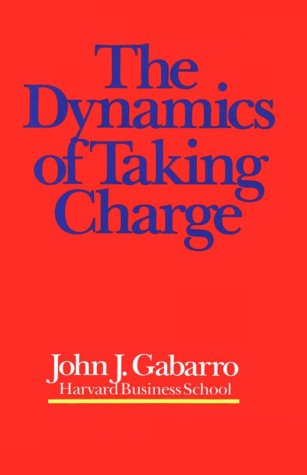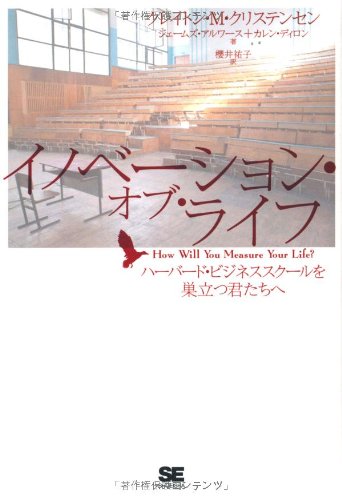まえがき
動物とは次のように分類できる。
リスト
- 皇帝に属するもの
- 香の匂いを放つもの
- 飼い馴らされたもの
- 乳呑み豚
- 人魚
- お話に出てくるもの
- 放し飼いの犬
- この分類自体に含まれているもの
- 気が違ったように騒ぐもの
- 算え切れぬもの
- ラクダの毛のごく細の毛筆で描かれたもの
- その他
- 今しがた壷を壊したもの
- 遠くからハエのように見えるもの
あとがき
まえがきを含めて『ヤバい経営学: 世界のビジネスで行われている不都合な真実』より。
“これは、ホルヘ・ボルヘスの『続審問』に出てくる分類で、中国の古い百科事典にも出てくる。”とありますので、これは孫引き。以前にどこかで見かけて、次に見かけたら収集しようと思っていたのでした。
調べてみるとホルヘ・ルイス・ボルヘス 『異端審問』という本に載っている模様。この気が狂いそうな分類を巧みに使った短編小説とか、誰か書かないかしら。
- タイトル: ヤバい経営学―世界のビジネスで行われている不都合な真実
- 著者: フリーク ヴァーミューレン(著)、Vermeulen,Freek(原著)、隆一郎, 本木(翻訳)、佳史, 山形(翻訳)
- 出版社: 東洋経済新報社
- 出版日: 2013-03-01
- タイトル: 異端審問
- 著者: ホルヘ・ルイス・ボルヘス(著)、中村 健二(翻訳)
- 出版社: 晶文社
- 出版日: 1982-05-01