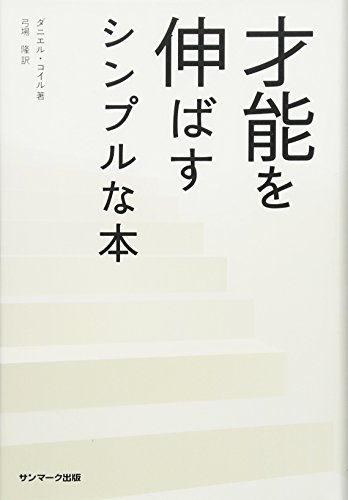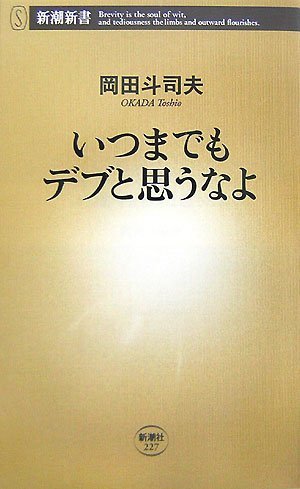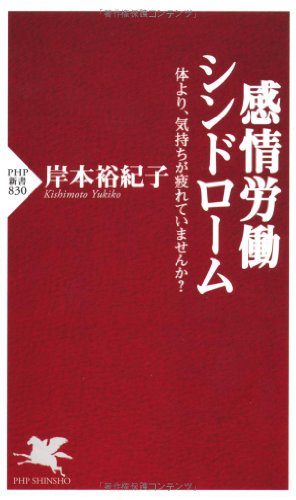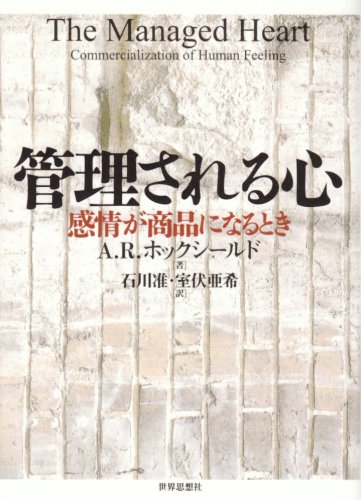まえがき
『最善の練習法を選択するには(略)次の4つの要素を検証すればよい。』
リスト
- 【背伸びと繰り返し】練習中に能力の限界まで背伸びをし、それを繰り返しているか
- 【意識の集中】練習に意識を集中し、目標達成のために気合いを入れているか
- 【明確な目的意識】練習が、身につけたいスキルと直結しているか
- 【強力で迅速なフィードバック】自分の出来ばえ(どこがうまくできて、どこでミスをしたか)について正確な情報を得ているか
あとがき
まえがきを含めてダニエル・コイル『才能を伸ばすシンプルな本』より。【】内は見出しから、その後の解説文は本文からすこし編集のうえ引用しました。
『「究極の鍛錬」の特徴』とかなり重なっていますね。王道はあるが近道はない、ということか。
- タイトル: 才能を伸ばすシンプルな本
- 著者: ダニエル・コイル(著)、弓場 隆(翻訳)
- 出版社: サンマーク出版
- 出版日: 2013-06-03