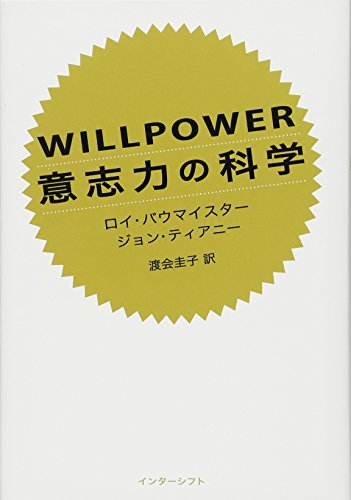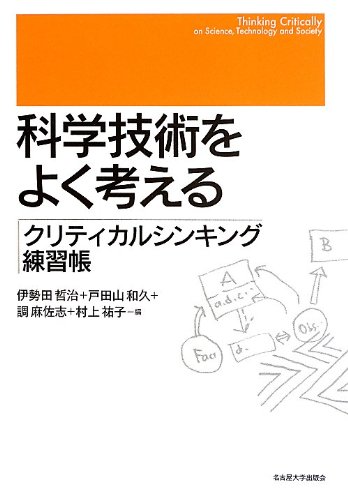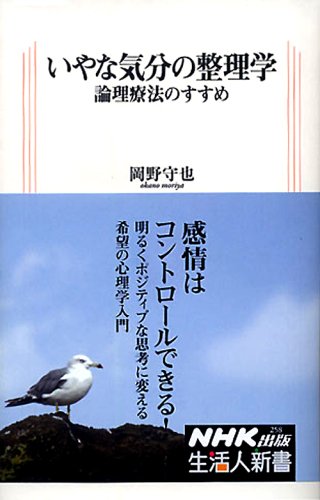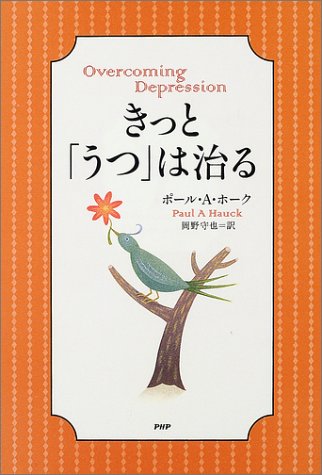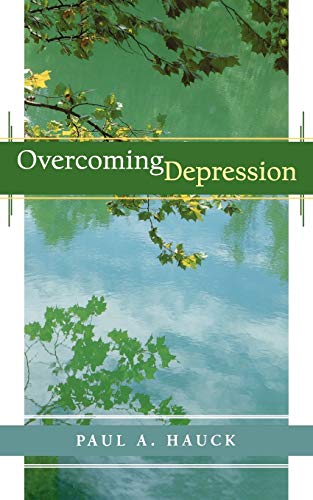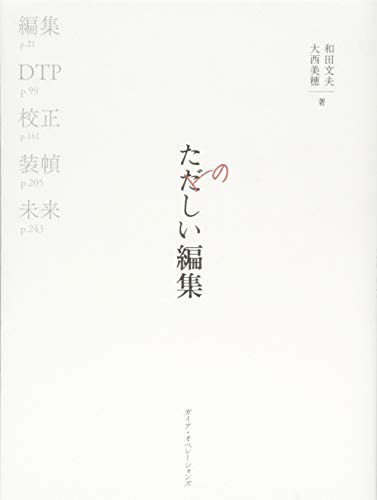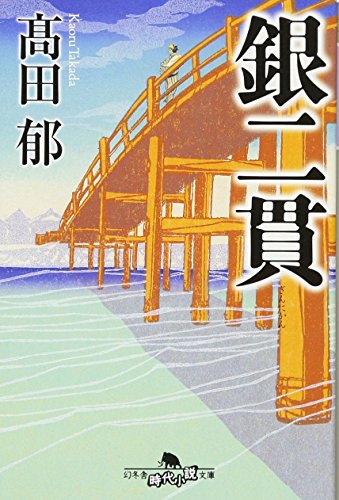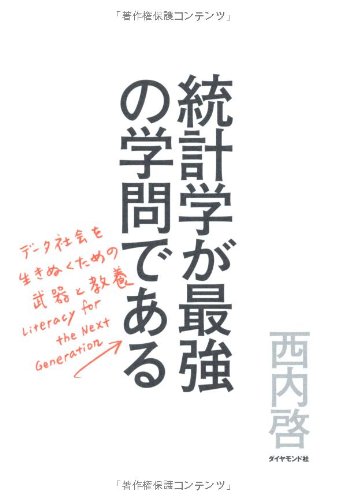まえがき
『どんなものでも罰には三つの基本的な面がある。』
リスト
- 【厳しさ】罰の重さは問題ではない。厳しい罰は逆効果になる場合がある。
- 【スピード】すぐに罰を与えることが重要である。遅くなればなるほど、過ちそのものや、そこに至るまでの心理プロセスを忘れてしまう。
- 【一貫性】理想的には、親は子供が悪さをしたら、そのたびに言い聞かせるべきだ。簡潔で冷静で一貫していれば、子供たちは叱責をきちんと受け止める。
あとがき
まえがきを含めて、ロイ・バウマイスター、 ジョン・ティアニー『WILLPOWER 意志力の科学』より。本文を編集のうえリスト化しました。スピードと一貫性は「ある」ほうが望ましいのですが、厳しさは「問題ではない」ので、ややわかりづらいかも。
- タイトル: WILLPOWER 意志力の科学
- 著者: ロイ・バウマイスター(著)、ジョン・ティアニー(著)、渡会圭子(翻訳)
- 出版社: インターシフト
- 出版日: 2013-04-22