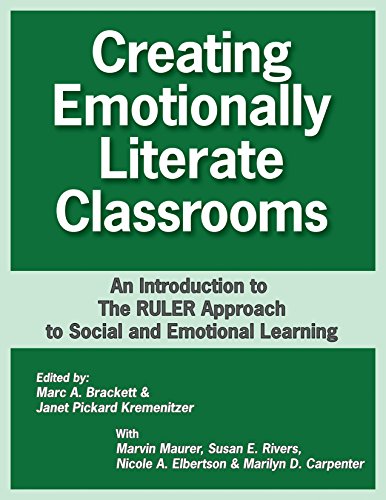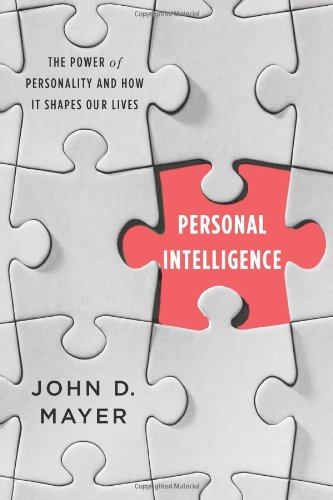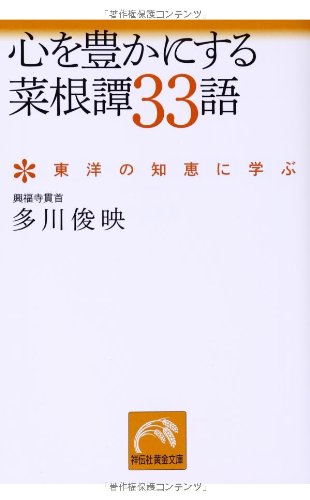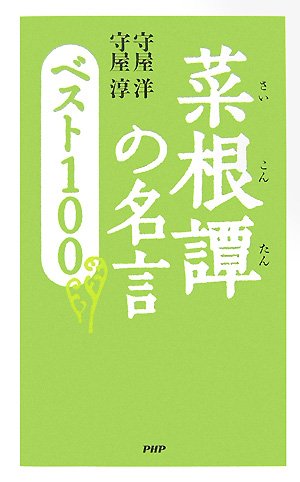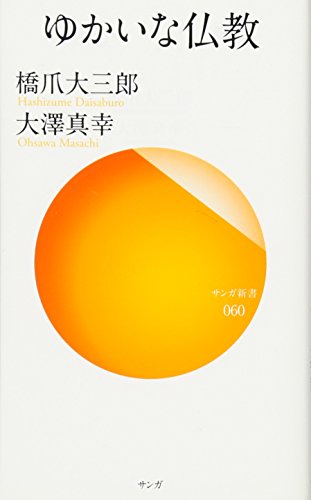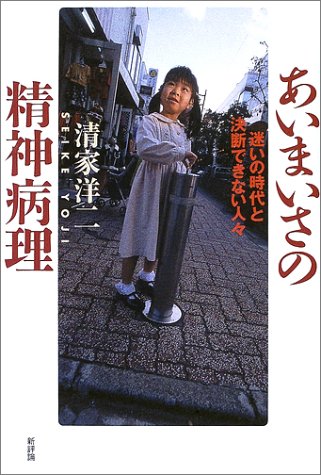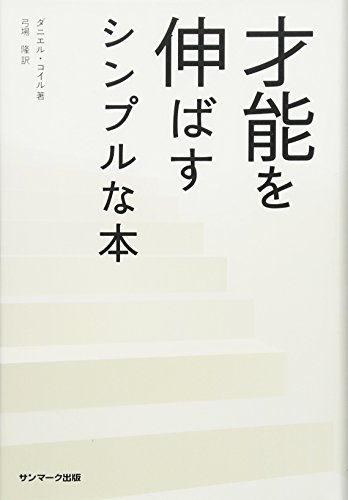まえがき
『われわれは、日々無数の意思決定をしていく必要があります。限られた時間のなかで効率よく「疑う」方法を、自分のクセに合わせて開発していかなければなりません。たとえば、こんなリストはどうでしょうか。』
リスト
- 【感情の存在に気づく】完全な合理主義者であれば、どのような意思決定をするか。自分がそうしないのは、なぜか。
- 【論理の存在に気づく】完全な温情主義者であれば、どのような意思決定をするか。自分がそうしないのは、なぜか。
- 【相手の立場に立つ】相手の立場でこの意思決定を受け止めてみる。相手にとっても最善といえる意思決定にするために、なにかを変える余地はないか。
- 【組織の外から見る】後日この意思決定を分析する評論家は、何と言うか。内部の事情を酌まない外野ならではのシンプルさで考えたら、どのような意思決定になるか。
あとがき
『「罪を憎んで人を憎まず」はどこまで正しいのか』 | 起-動線 より。