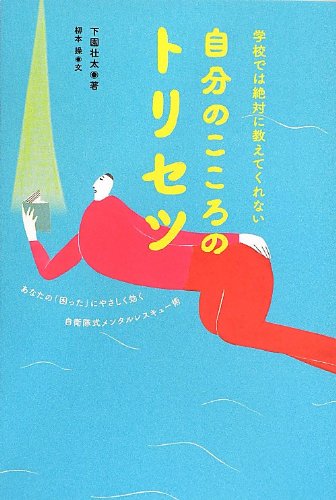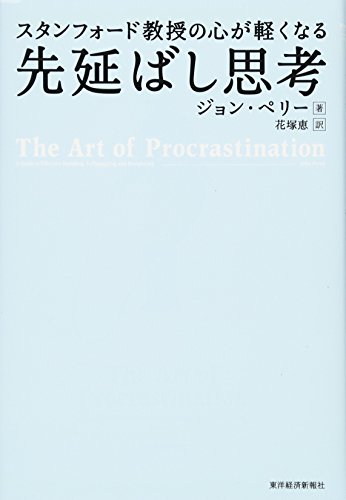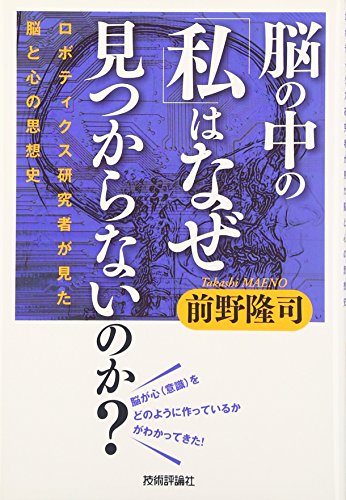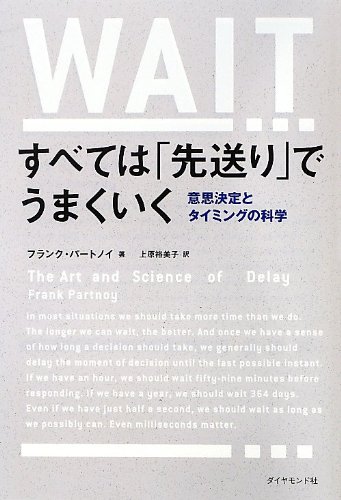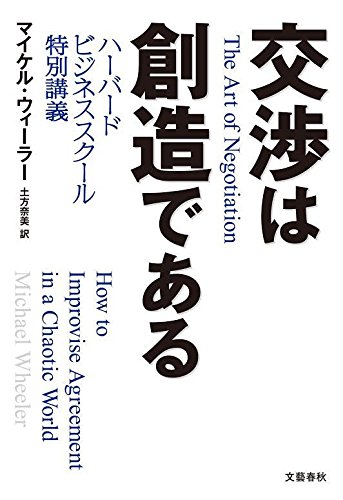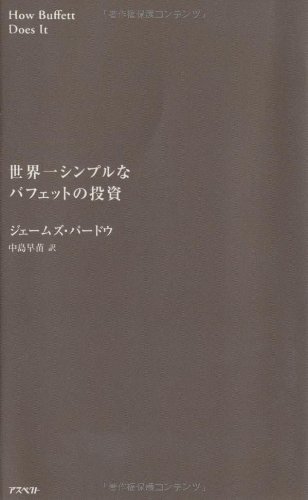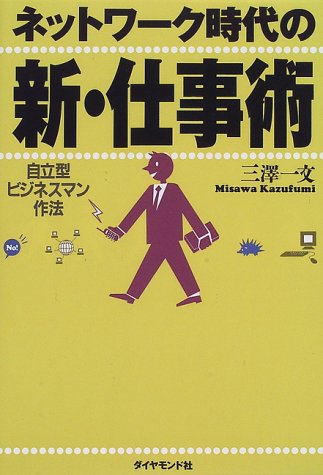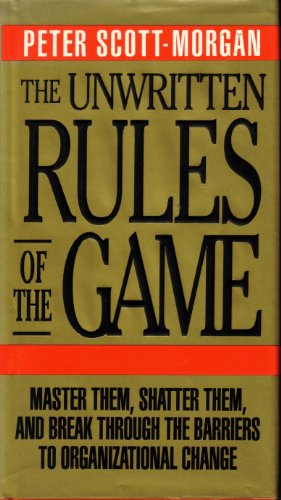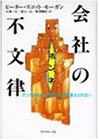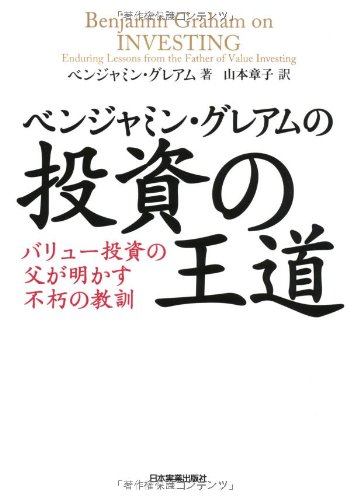まえがき
かつて原始人として「生き延び、子孫を残す」という最終目標のために置いた中間目標に、われわれは今も苦しめられている。その中間目標とは。
リスト
- 【仲間を作ること】原始人が、外敵の襲来に備えるためには仲間が必要
- 【愛されること】子孫を残すには、異性に愛されなければならない
- 【能力をつけること】厳しい自然の中で常に食糧難に直面し、生活する原始人は、狩りや釣り、料理、衣服作りなど何かに秀でることが自分と仲間の命をつなぐための重要な要素になる
- 【群れの中で一番になること】その能力が群れの中で一番であれば、より仲間として尊重され、異性からも愛された
あとがき
下園 壮太、柳本操 『学校では絶対に教えてくれない 自分のこころのトリセツ』より。本文を編集してリスト化しました。
・原始人の最終目標は「生き延びて子孫を残す」ことだった
・最終目標達成のために4つの中間目標(本リスト)に向かって行動するようになった
・しかし今や、最終目標より中間目標を達成するほうが難しい
・その結果、現代人は不要な悩みを抱えている
というのが、引用部分のロジックでした。
- タイトル: 学校では絶対に教えてくれない 自分のこころのトリセツ
- 著者: 下園壮太(著)、柳本操(著)
- 出版社: 日経BP
- 出版日: 2013-09-25