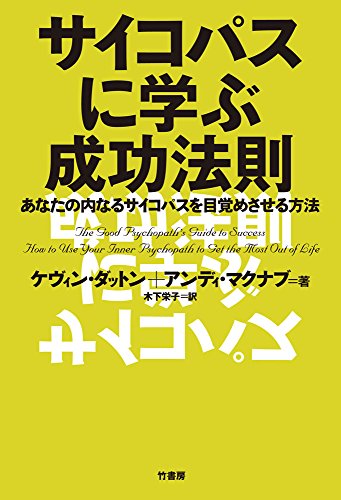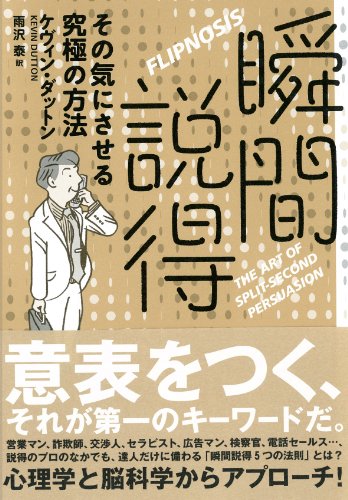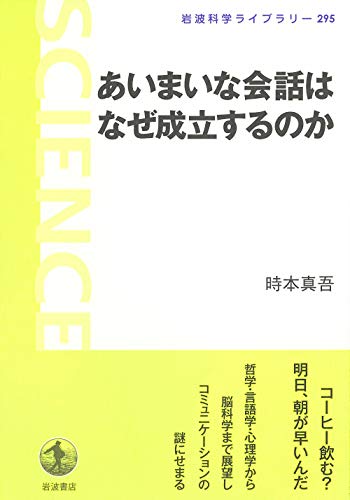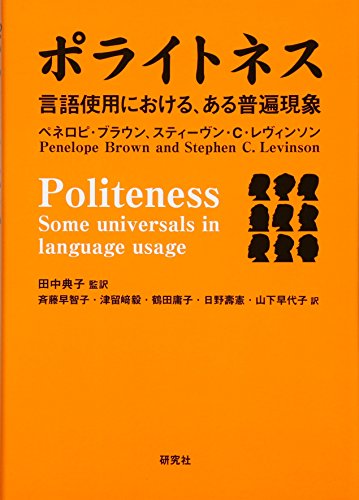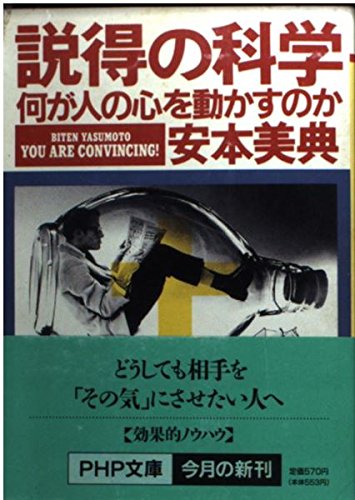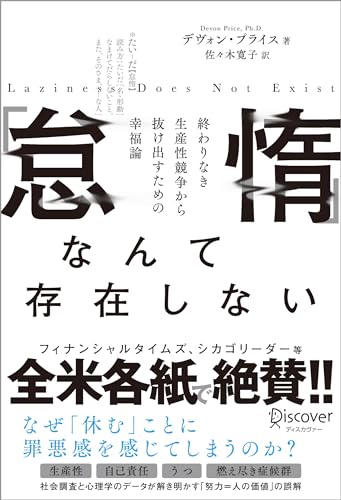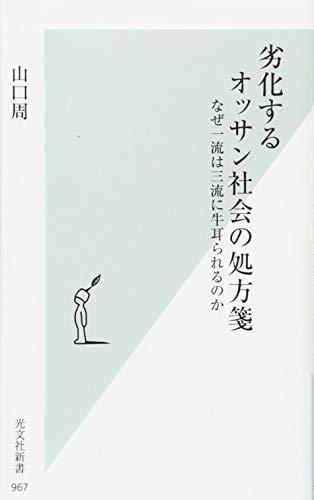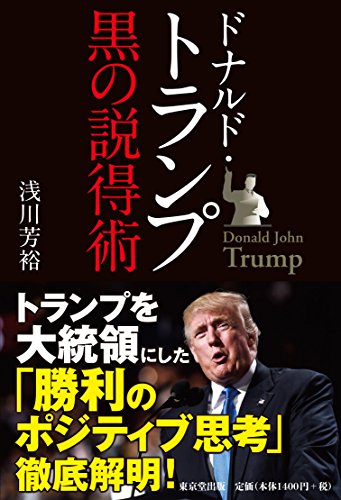まえがき
『もし次回、あなたがやるべき難しい何かに悩んで怖じ気づいていたら、こう自問してほしい。(略)そして、あなたがこの問いへの答えを出すことができたら……それをただ実行すればいい。』
リスト
- もしこんなふうに感じていなかったら、私はどうするだろうか?
- もし他人がどう思うかを気にしなかったら、私はどうするだろうか?
- もしいま悩んでいることがどうでもよければ、私はどうするだろうか?
あとがき
まえがきを含めて、ケヴィン・ダットン、アンディ・マクナブ『サイコパスに学ぶ成功法則』 (竹書房、2016年)より。第十章「心のスイッチをオフにして動く――考えるのはそのあとでいい」の、章題と同じ題が付けられた項からの引用です。
この問いが有用なのは、人には次のような傾向があるからでしょう。
- 感情に重きを置きすぎる
- 他人がどう思うかを気にしすぎる
- 目の前の決断の対象を重大視しすぎる
なので、リストの自問で偏りチェックをしてみるのは良いアイディアですね。
- タイトル: サイコパスに学ぶ成功法則
- 著者: ケヴィン・ダットン(著)、アンディ・マクナブ(著)、木下 栄子(翻訳)
- 出版社: 竹書房
- 出版日: 2016-07-22