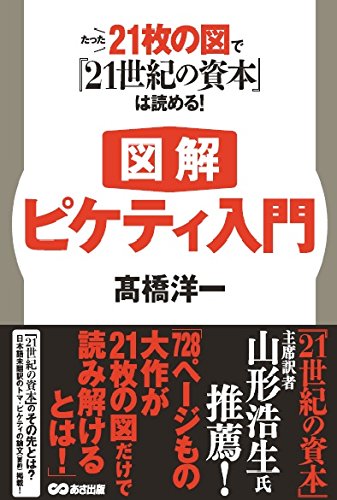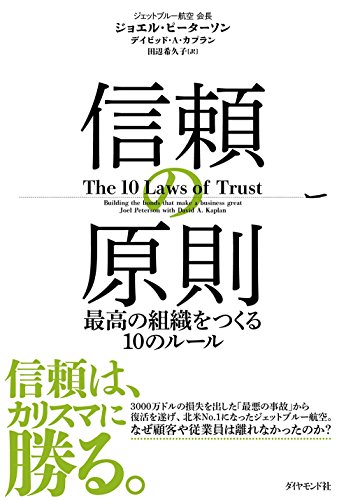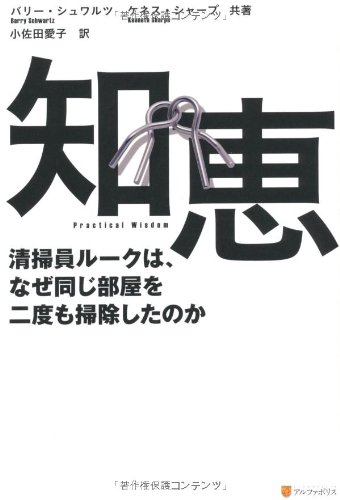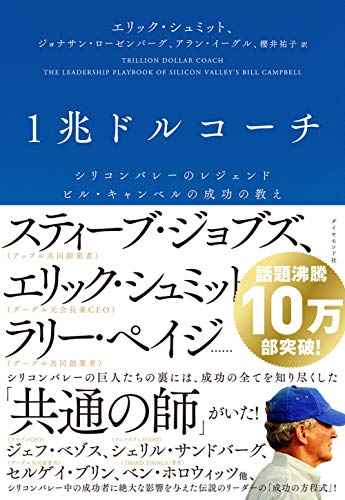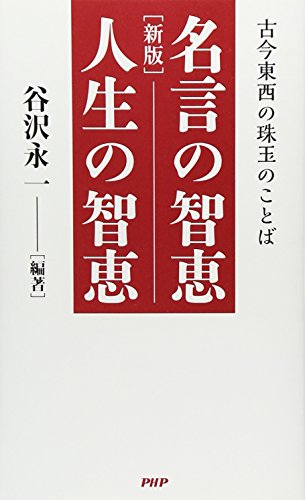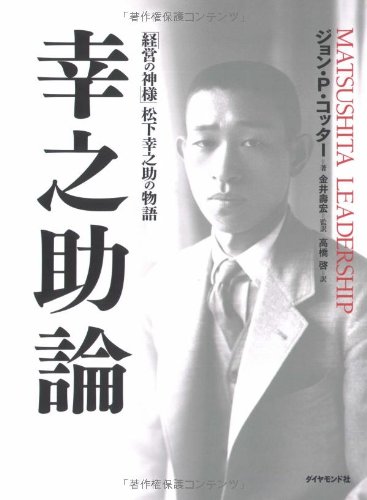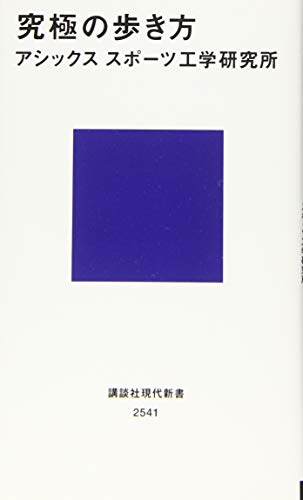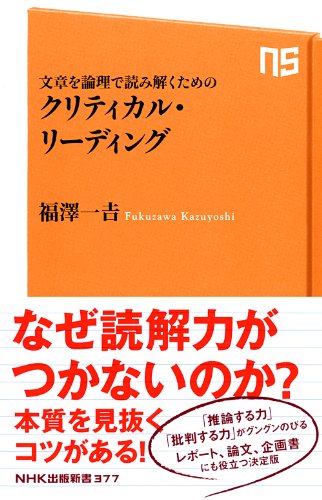まえがき
『これは大学の経済の授業でも最初のほうに教える、経済学の「初歩中の初歩」の知識である。 三面等価とは、「生産面」「分配面」「支出面」の三つが、概念としては同じ値になるという経済論理だ。 』
リスト
- 【生産面】 生産の段階で生じる付加価値の総計。モノを作って売った売上から、仕入れなどの経費を引いたもの。
- 【分配面】 作って売って得た利益を分配したもの。社員への給料や株主への配当などの、要するに「所得」の統計。
- 【支出面】 働いて得た給料や株の配当を、モノを買うことで消費する。余ったお金は貯金するかもしれないが、銀行は預金を企業に貸し付けるので、これも支出にカウントされる。
あとがき
まえがきを含めて、高橋洋一 「【図解】ピケティ入門 たった21枚の図で『21世紀の資本』は読める!」(あさ出版、2015年)より。
[もし『21世紀の資本』をより効率的に読みたいと思うのなら、ぜひ「三面等価の原則」を知っておいてほしい。]とのことですが、興味深いことにWikipedia(日本語版)によればこの原則は日本人が考案し、日本でしか使われていない概念のようですね。
- タイトル: 【図解】ピケティ入門 たった21枚の図で『21世紀の資本』は読める!
- 著者: 高橋 洋一(著)、 (監修)
- 出版社: あさ出版
- 出版日: 2015-02-20