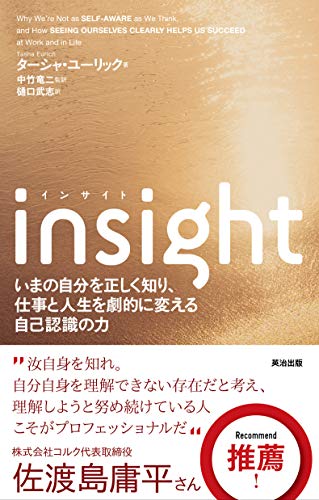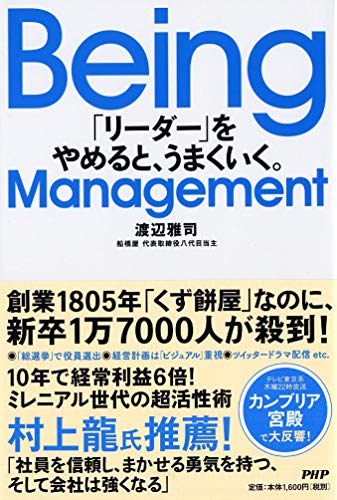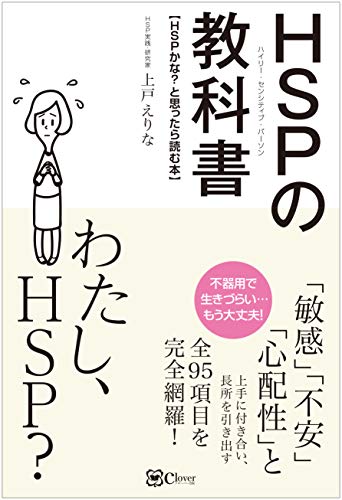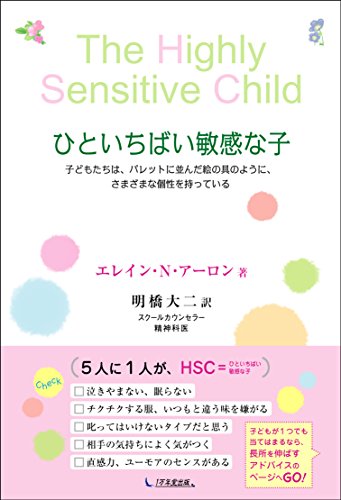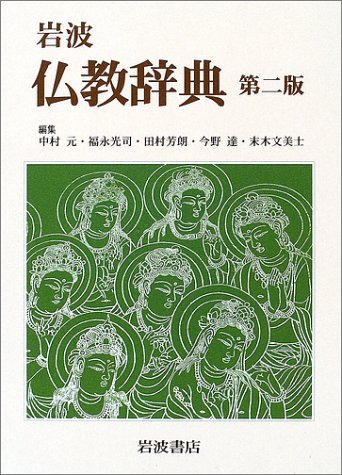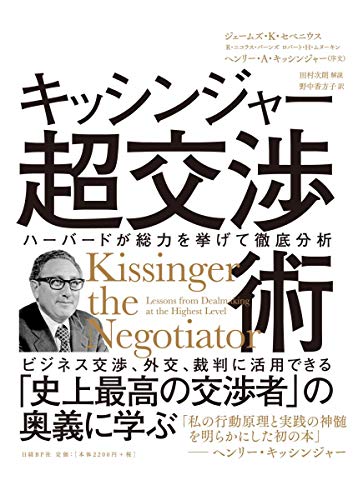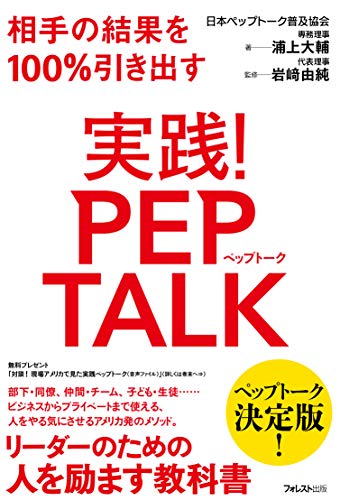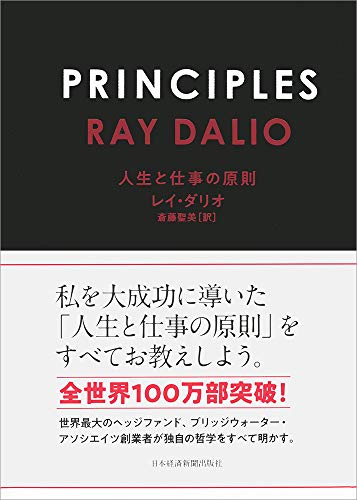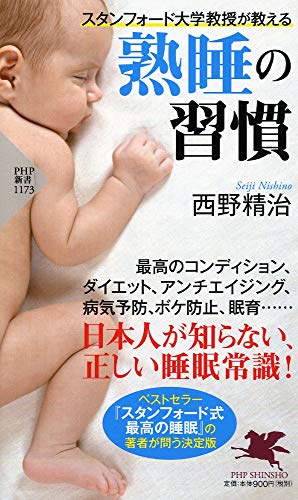まえがき
自己認識(自分自身と、他人からどう見られているかを理解しようとする意志とスキル)の構成要素とは。
リスト
- 【価値観 (values)】 自らを導く行動指針
- 【情熱 (passions)】 愛を持っておこなうもの
- 【願望 (aspirations)】 経験し、達成したいもの
- 【フィット (fit)】 自分が幸せで存分に力を尽くすために必要な環境
- 【パターン (patterns)】 思考・感情・行動の一貫した傾向
- 【リアクション (reactions)】 強みや弱みが表れる思考・感情・行動
- 【インパクト (impact)】 周りの人への影響
あとがき
ターシャ・ユーリック 『insight(インサイト)――いまの自分を正しく知り、仕事と人生を劇的に変える自己認識の力』(英治出版、2019年)より。まえがきとリストは本文を編集のうえ引用しました。ただしリストの文言は原著と照らし合わせて一部を訳し変えました。リスト中の英単語は原著からの引用です。
自己認識の構成要素をていねいに洗い出したリスト。
『七つの柱すべてにとって、一番大切なのは内側の視点と外側の視点の両方を持つことだ。それができて初めて、自分自身のことや、自分がどう見られているかを真に理解することができる。』
- タイトル: insight(インサイト)――いまの自分を正しく知り、仕事と人生を劇的に変える自己認識の力
- 著者: ターシャ・ユーリック(著)、中竹竜二(監修)、樋口武志(翻訳)
- 出版社: 英治出版
- 出版日: 2019-06-26