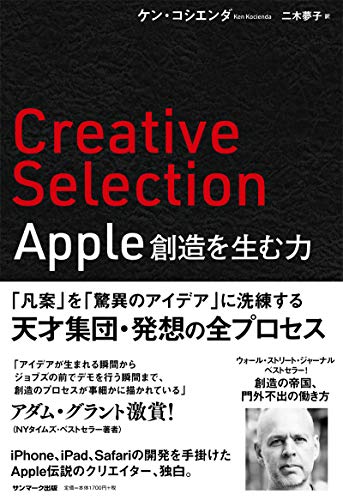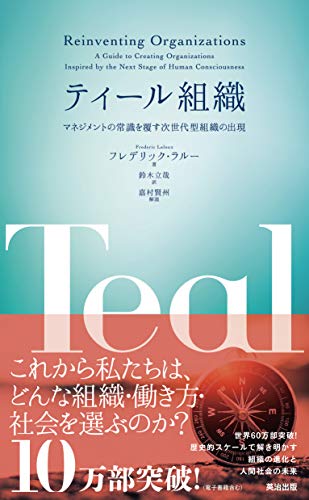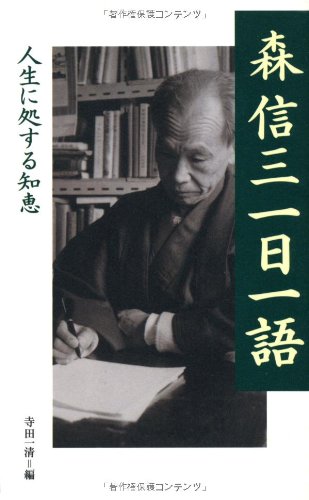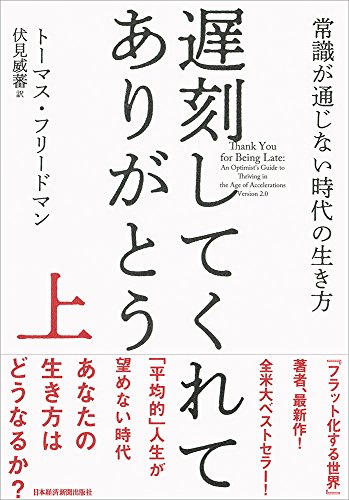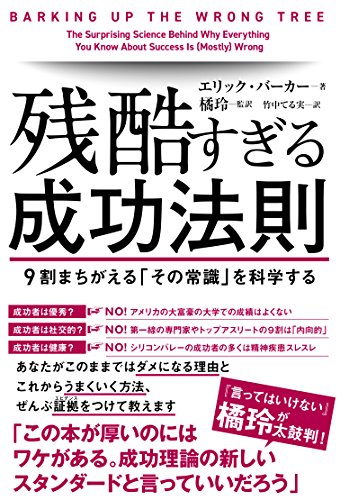まえがき
『アップルのソフトウェア部門での成功に欠かせない要素を7つにまとめてみた。』
リスト
- インスピレーション ―― 着想。広い視野をもって発想し、様々な可能性を考える
- コラボレーション ―― 他者と協力し、互いの強みを活かし補完し合う
- テクニック ―― スキルを使って質の高い結果を得る。そして、常により良い仕事ができるように励む
- 勤勉さ ―― つまらない仕事でも、必要なら手抜きや妥協をせずにやり抜く
- 決断力 ―― 難しい選択を、遅れたり、引き延ばしたりせずに行う
- テイスト ―― 感性。見る目を養い、「魅力的でありながらまとまりのあるもの」をつくるバランスを見つける
- 共感力 ―― 他者の視点から世界を見、彼らの生活とニーズに適応するものをつくる
あとがき
まえがきを含めて、ケン・コシエンダ 『Creative Selection Apple 創造を生む力』(サンマーク出版、2019年)より。まえがき及びリストは「プロローグ」から、タイトルは本文からの引用です。
本書のタイトルにつながる、プロローグのおしまいの部分も引用します。
このように7つの要素を混ぜ合わせ、合体させつつ、人間味、つまり「私たちらしさ」を、8番目の要素として加えた。
明確なゴールとすぐれたアイデアの実現に取り組みながら、7つの要素を活用し、さらに人間味を加えたアプローチ。
これらを積み重ねて成り立つアップルの創造法を、私は「クリエイティブ・セレクション」(創造的選択)と呼んでいる。
- タイトル: Creative Selection Apple 創造を生む力
- 著者: ケン・コシエンダ(著)、二木夢子(翻訳)
- 出版社: サンマーク出版
- 出版日: 2019-03-11