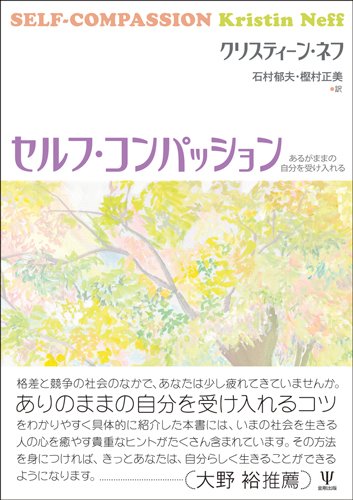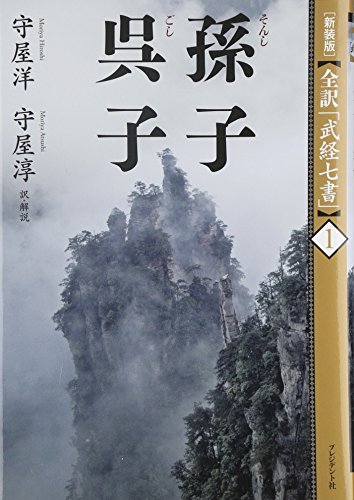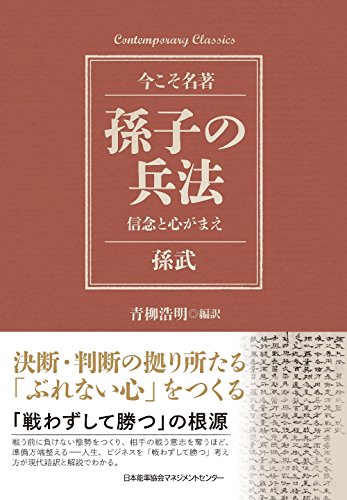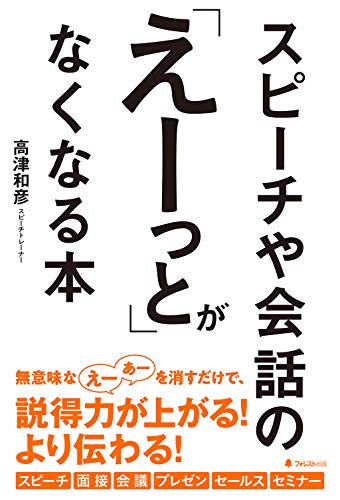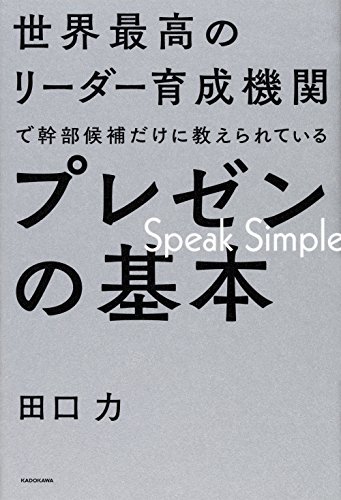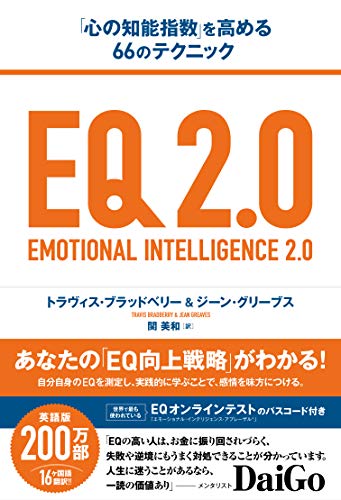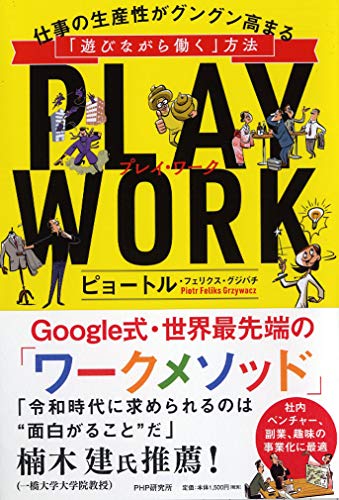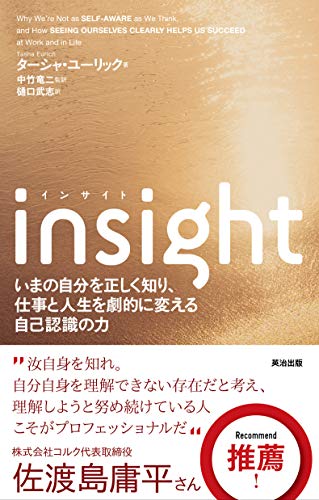まえがき
『真のセルフ・コンパッションを手に入れるためには、これらの3つの不可欠な要素を獲得し、統合する必要がある。』
リスト
- 【自分に対する優しさ】自分に対して厳しく批判的・判断的な態度を取らずに、優しく思いやりのある態度を取ろうとする
- 【共通の人間性】孤独感や疎外、苦しみを感じることなく、人間として生きる上で他者と繋がっているという感覚を持つ
- 【マインドフルネス】自分の経験による苦痛を無視したり誇張することなく、バランスの取れた自覚をもって捉える
あとがき
まえがきを含めて、クリスティーン・ネフ『セルフ・コンパッション』(金剛出版、2014年)より。本文を多少編集のうえリスト化しました。著者自身の論文(参考文献1)を引用していますが、論文と本書(の原著)では記述が微妙に異なっています。
- タイトル: セルフ・コンパッション―あるがままの自分を受け入れる
- 著者: クリスティーン・ネフ(著)、石村 郁夫(翻訳)、樫村 正美(翻訳)
- 出版社: 金剛出版
- 出版日: 2014-11-26
この本からの他のリスト
参考文献
- Neff, Kristin. “Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself.” Self and identity 2.2 (2003): 85-101.