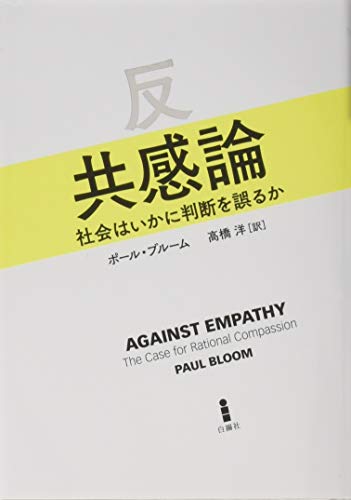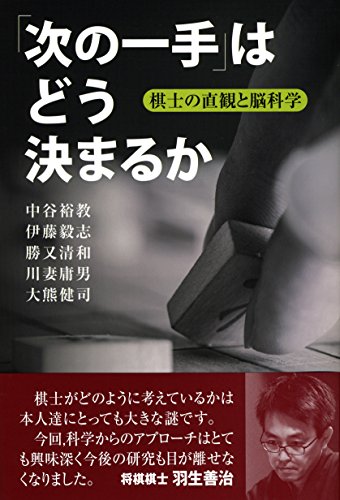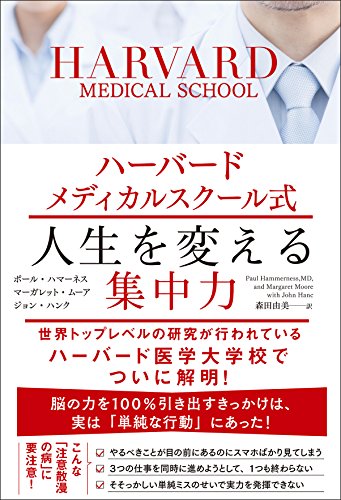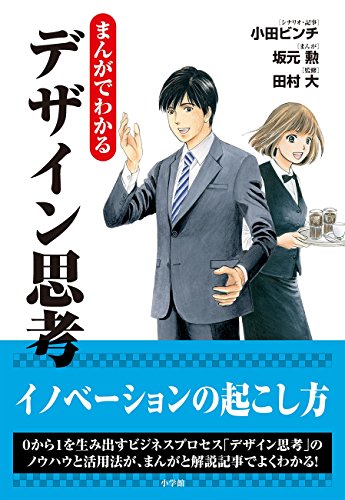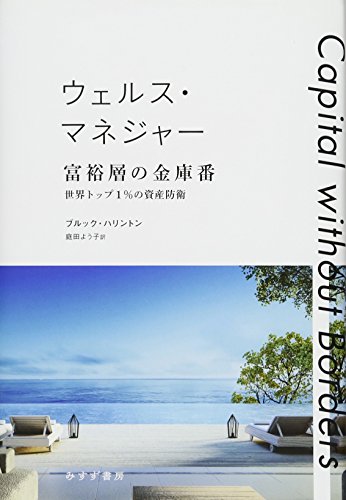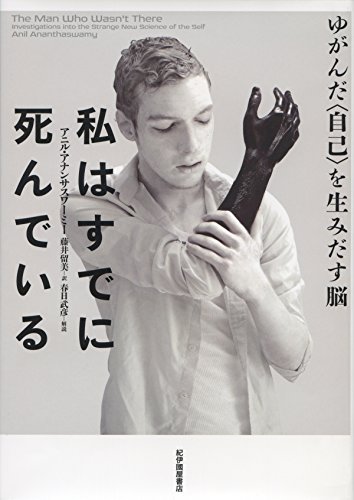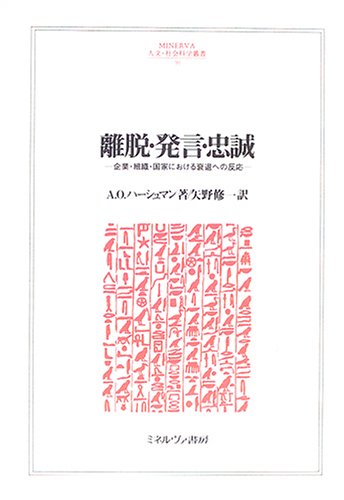まえがき
『たとえば、ある研究では次の五つの項目が尋ねられている。(略)読者が欧米人なら、これらの項目に対するどのような立場が、リベラルと保守主義のいずれに対応するのか、間違いなくわかるだろう。』
リスト
- アメリカにおける、より厳格な銃規制を規定する法律
- 国民皆保険制度
- もっとも高い収入を得ている人々を対象とする増税
- マイノリティに対するアファーマティブアクション〔マイノリティの不利を、歴史的経緯や社会環境を考慮しつつ是正する措置〕
- 地球温暖化対策としての厳格な二酸化炭素排出基準
あとがき
まえがきを含めて、ポール・ブルーム『反共感論―社会はいかに判断を誤るか』(白揚社、2018年)より。参考文献(1)からの引用だそうです。
『さらに言えば、これらの項目は連動する。つまり、ある一つの項目を承認する人は残りの項目も承認し、ある一つの項目に反対する人は、残りの項目にも反対するはずだ。』
- タイトル: 反共感論―社会はいかに判断を誤るか
- 著者: ポール・ブルーム(著)、高橋洋(翻訳)
- 出版社: 白揚社
- 出版日: 2018-02-02
この本からの他のリスト
参考文献
(1) “Do mass political opinions cohere? And do psychologists “generalize without evidence” more often than political scientists?” (cultural cognition project)