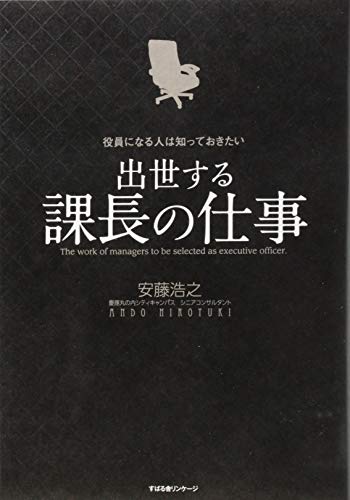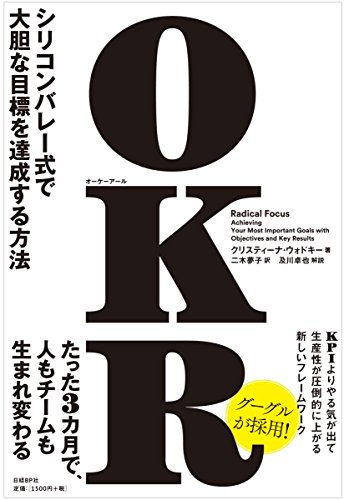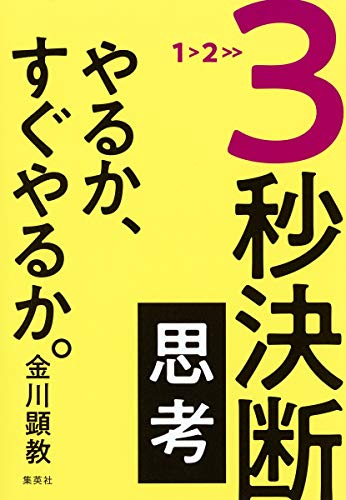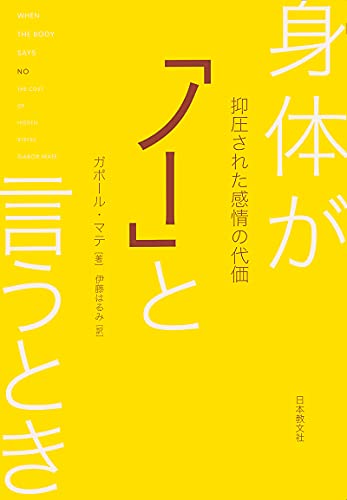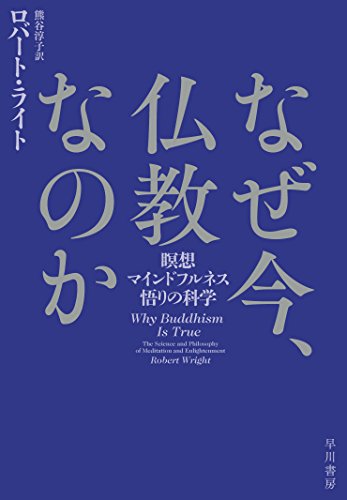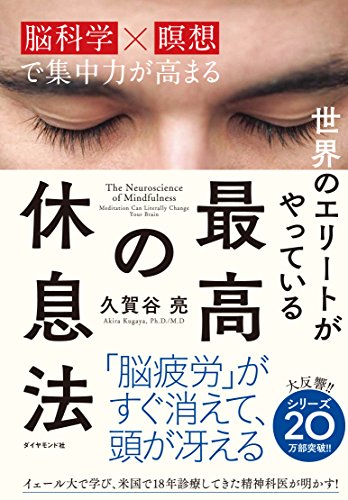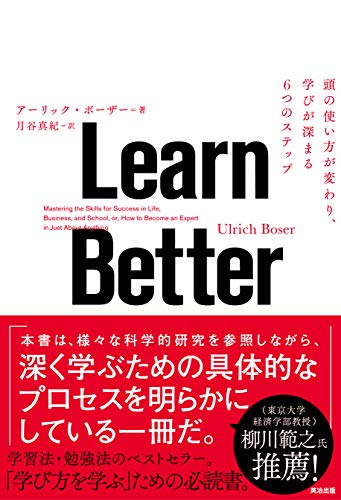まえがき
『課長の仕事とは(略)「仕組みをコントロールすること」と「メンバーにリーダーシップを発揮すること」です。』
リスト
- 分業と調整の仕組みをつくる
- 人材育成の仕組みをつくる
- 実行過程をモニタリングする仕組みをつくる
- メンバーを方向づける
- メンバーの模範となる
- メンバーを動機づける
- メンバーを育成する
- 職場の目標を明らかにする
- 目標を達成する見通しを立てる
あとがき
まえがきを含めて、安藤 浩之『役員になる人は知っておきたい 出世する課長の仕事』(すばる舎、2016年)より。1~3が「仕組み」、4~7が「人」、8~9が「前提」。
- タイトル: 役員になる人は知っておきたい 出世する課長の仕事
- 著者: 安藤 浩之(著)
- 出版社: すばる舎
- 出版日: 2016-09-23