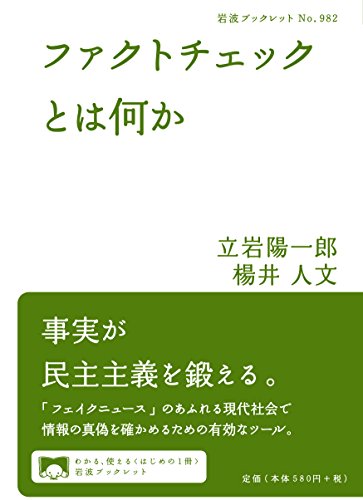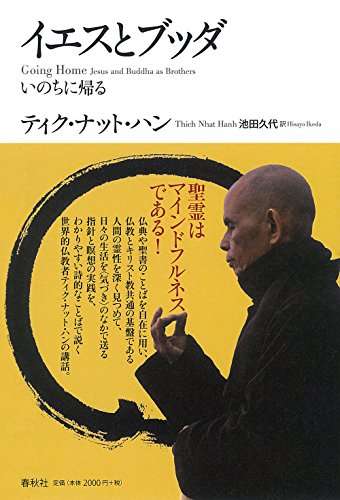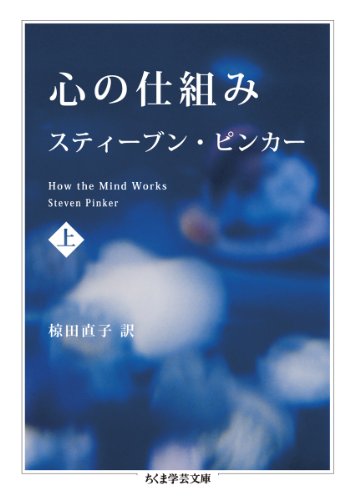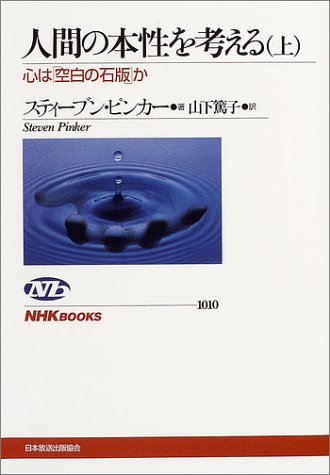まえがき
『「ポリティファクト」は「トゥルーソメーター」 (Truth-O-Meter) という独自のレーティングシステムを用いて正確性を判定しており、六種類の判定方法について説明されています。』
リスト
- 真実(True) ―― 正確であり、重要な事実が抜け落ちていないもの
- 大まかに真実(Mostly True) ―― 正確だが、説明や情報の補足が必要であるもの
- 半分真実(Half True) ―― 一部だけ真実。一部の事実に触れなかったり、文脈を無視したりしているもの
- 大半が間違い(Mostly False) ―― 真実も含んでいるが、決定的に重要な事実を無視しているため、異なる印象を読者に与えかねないもの
- 間違い(False) ―― 不正確なもの
- 全くのでたらめ(Pants on Fire) ―― 不正確であり、滑稽なもの
あとがき
まえがきを含めて、立岩 陽一郎, 楊井 人文 『ファクトチェックとは何か』(岩波書店、2018年)より。ファクトチェック団体はそれぞれに真偽の判定レベルを設けているとのことで、例として挙げられていました。
“Pants on Fire” は前に “Liar, Liar,” を付けて使われる、子供のはやし言葉。つまり、単に「間違い」というだけでなく「嘘」を連想させます。“ファクト”チェックのレベル名としては微妙に誘導的な気がしますが、どうなのかしら。
- タイトル: ファクトチェックとは何か (岩波ブックレット)
- 著者: 立岩 陽一郎(著)、楊井 人文(著)
- 出版社: 岩波書店
- 出版日: 2018-04-06
この本からの他のリスト
参考文献
(1) How we determine Truth-O-Meter ratings (PolitiFact)