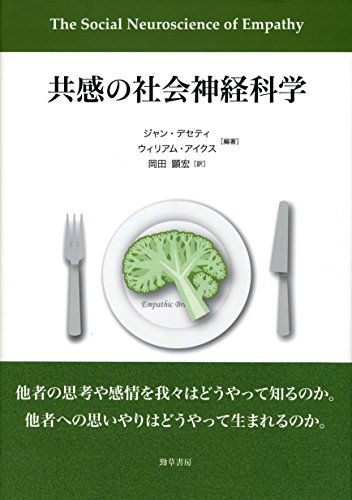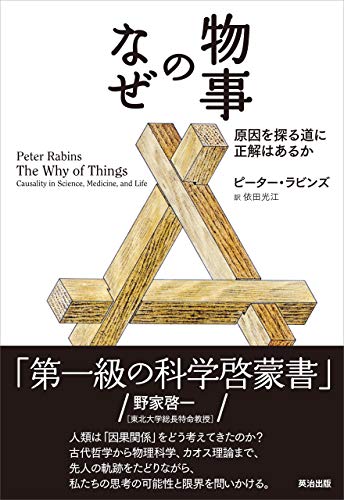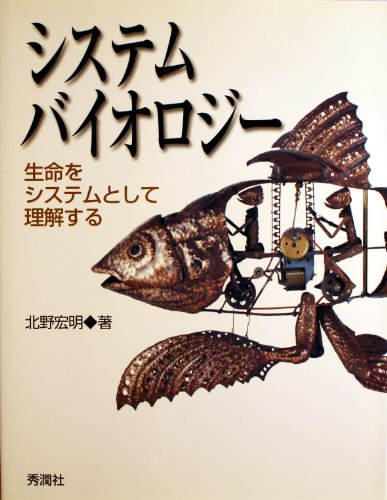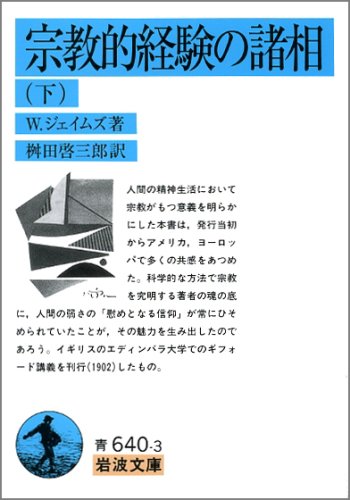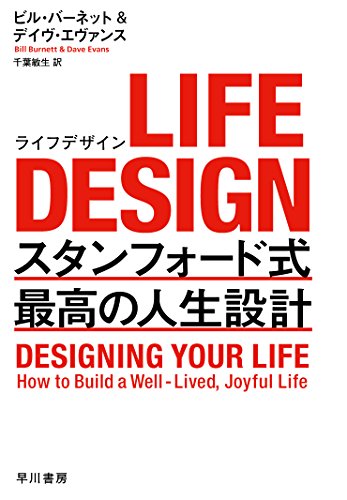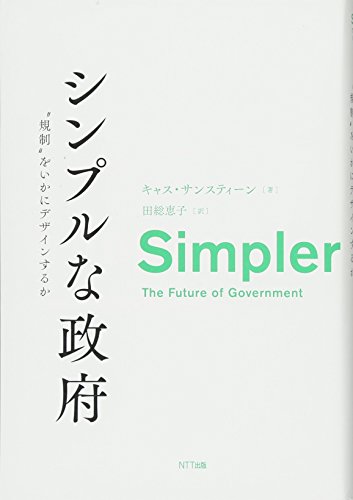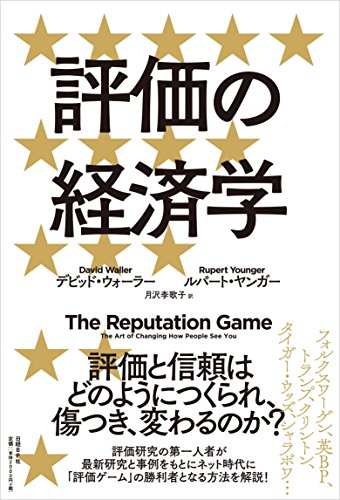まえがき
『真の共感のためには3つの異なる技能が必要だという点については、多くの臨床心理学者・カウンセリング心理学者が同意している。』
リスト
- 他者と感情を共有する能力
- 他者が何を感じているのかを直観する認知能力
- 他者の苦悩に対して思いやりを持って反応しようとする「社会的に有益」な意図
あとがき
まえがきを含めて、『共感の社会神経科学』(勁草書房、2016年)より。引用元は参考文献(1)。
- タイトル: 共感の社会神経科学
- 著者: デセティ,ジャン(著)、アイクス,ウィリアム(著)、Decety,Jean(原著)、Ickes,William(原著)、顕宏, 岡田(翻訳)
- 出版社: 勁草書房
- 出版日: 2016-07-29
この本からの他のリスト
参考文献
(1) Decety, Jean, and Philip L. Jackson. “The functional architecture of human empathy.” Behavioral and cognitive neuroscience reviews 3.2 (2004): 71-100.