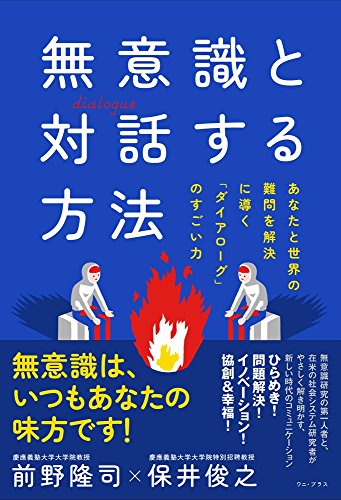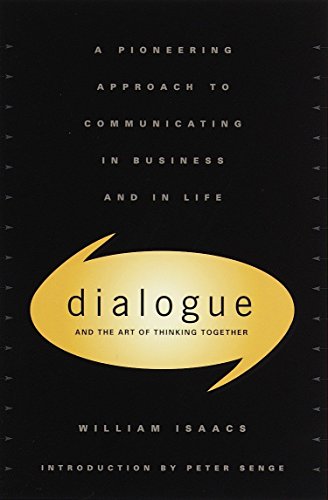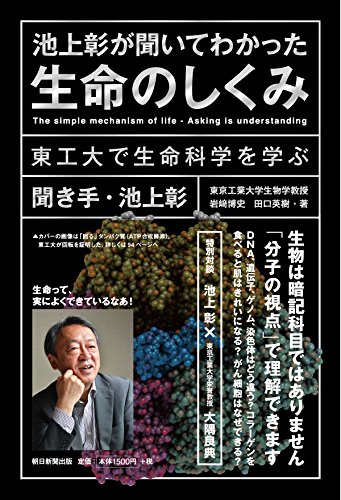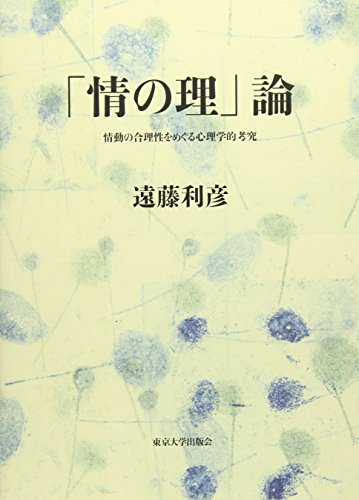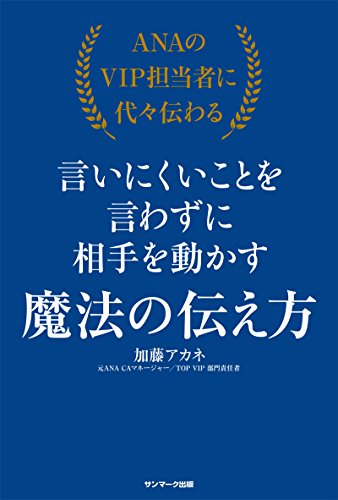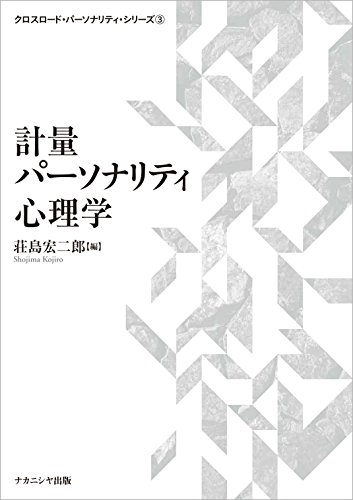まえがき
『全体像が聞き取れないのに無理して不明瞭なストラクチャー風にしてしまうよりは、まずは文字ベースでも全体を描けることが重要です。』
リスト
- 【レベル1:リスト】 主要なキーワードを聞き取り、抜け漏れなく文字で並べて描く、いわゆる箇条書き。
- 【レベル2:マークアップ】 似てる話題や大事な部分を見分けるため、色や形で目印をつけていく。
- 【レベル3:グルーピング】 分類を視覚的に理解できる状態にするため、似ている話題は近づけるなど配置を工夫する。
- 【レベル4:ストラクチャー】 複雑で抽象的な概念を、適切なフレームワークを活用して図示化する。
あとがき
清水 淳子 『Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)より。
後から議論をまとめたり、考えをまとめたりする手順としても普遍的で良いかと。
- タイトル: Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書
- 著者: 清水 淳子(著)
- 出版社: ビー・エヌ・エヌ新社
- 出版日: 2017-01-27