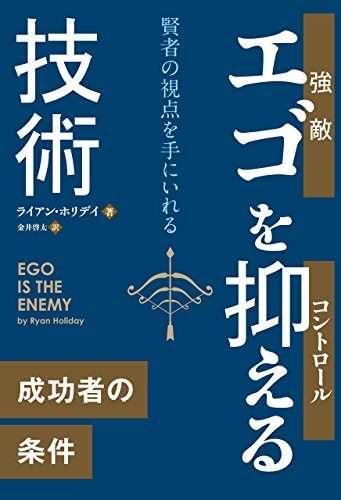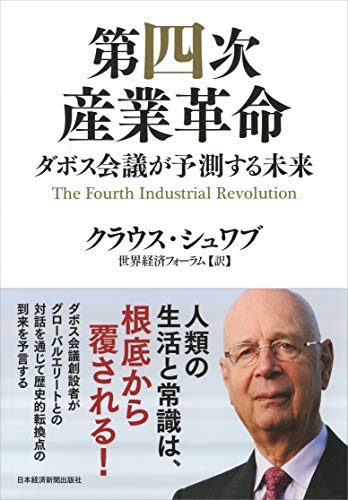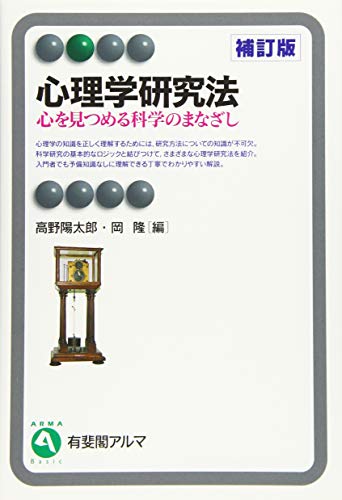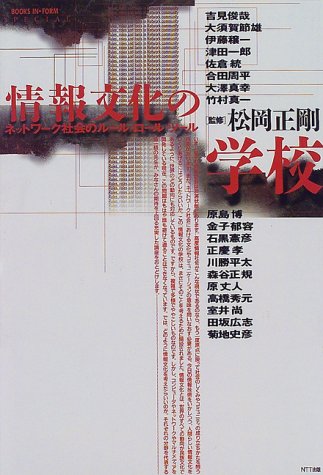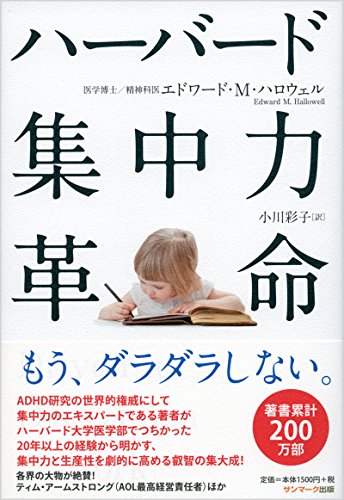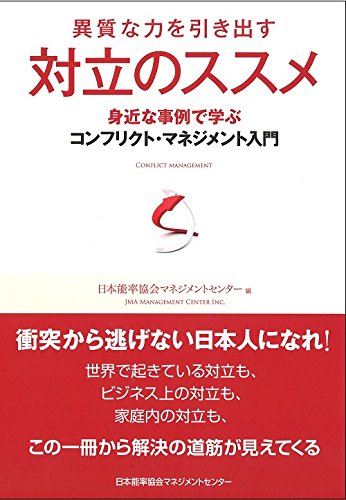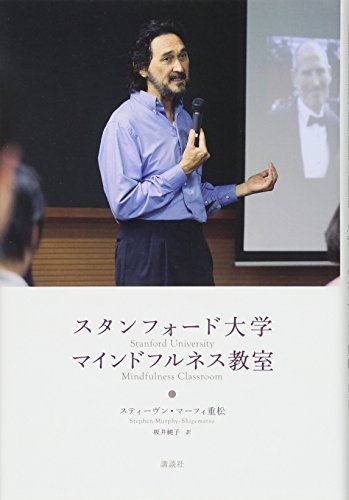まえがき
『成功を収めると、特に権力を手にすると、この上なく強力で危険な偏執にとりつかれる。つまり、○○の三つである。』
リスト
- 権利意識 (Entitlement)
- 支配欲 (Control)
- パラノイア(妄想症) (Paranoia)
あとがき
まえがきを含めて、ライアン・ホリデイ 『エゴを抑える技術』(パンローリング、2016年)より。まえがきの○○部分をリスト化しています。英語部分は見出しから引用しました。
- タイトル: エゴを抑える技術 (フェニックスシリーズ)
- 著者: ライアン・ホリデイ(著)、金井啓太(翻訳)
- 出版社: パンローリング
- 出版日: 2016-12-10