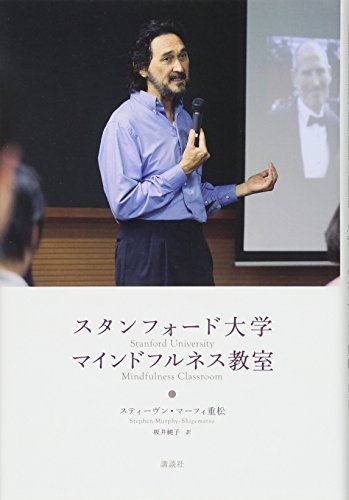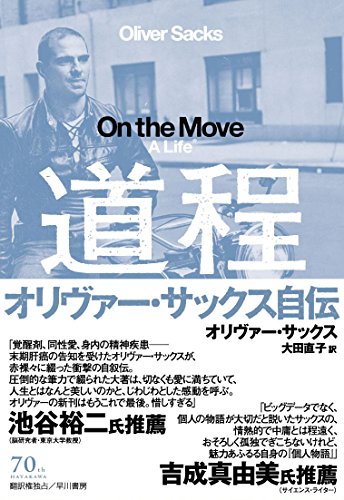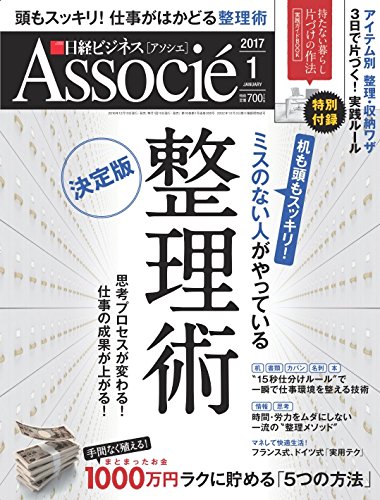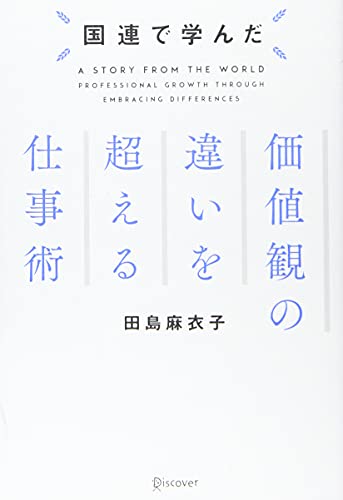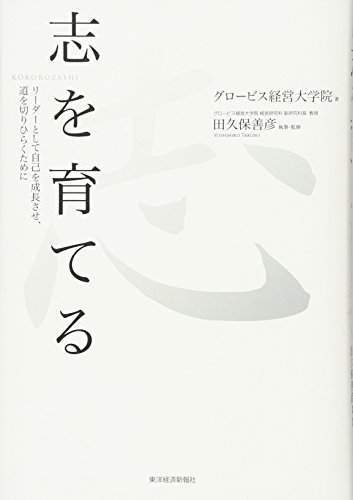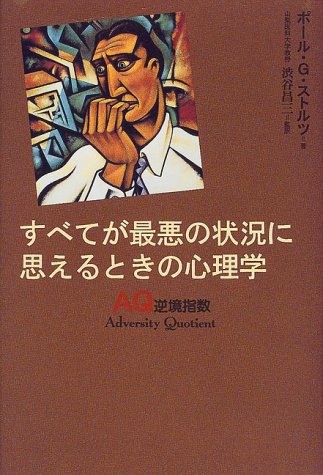まえがき
『私たちの自己理解および他者理解は、この三つの視点を意識にとどめて、そのバランスを取れるかどうかで決まるのだ。』
リスト
- 人間一人ひとりはある点で、
- a. 他のすべての人間と似ており、
- b. 他のある種の人間と似ており、
- c. 他の誰とも似ていない。
あとがき
まえがきを含めて、スティーヴン・マーフィ重松 『スタンフォード大学 マインドフルネス教室』 (講談社、2016年)より。
『自己と他者、両者の関係についての理解の骨組みづくりのために、私はヘンリー・マレーとクライド・クラックホーンが提唱したシンプルなモデルについて教えている。』という文章から引用元を検索したところ、Clyde Kluckhohn, Henry Alexander Murray “Personality in nature, society, and culture” (Google Books) という1953年の本(初版は1948年の模様)に次の記述がありました。
EVERY MAN is in certain respects
a. like all other men,
Clyde Kluckhohn, Henry Alexander Murray “Personality in nature, society, and culture”
b. like all some other men,
c. like no other man.
- タイトル: スタンフォード大学 マインドフルネス教室
- 著者: スティーヴン・マーフィ重松(著)、坂井 純子(翻訳)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2016-06-30