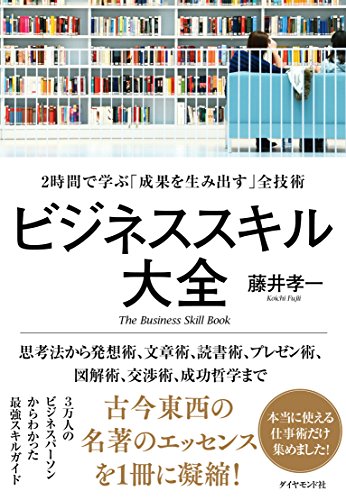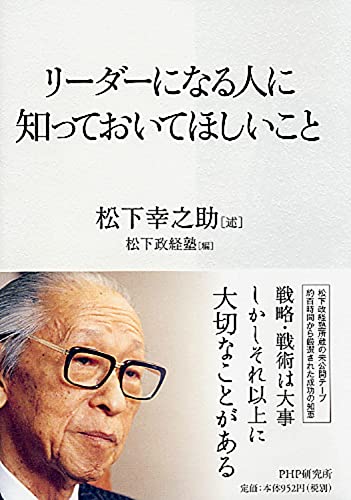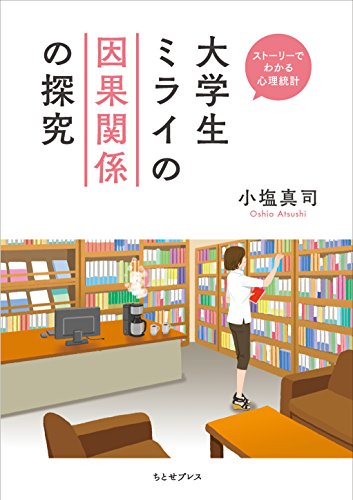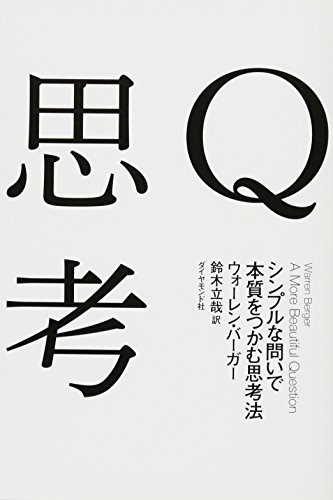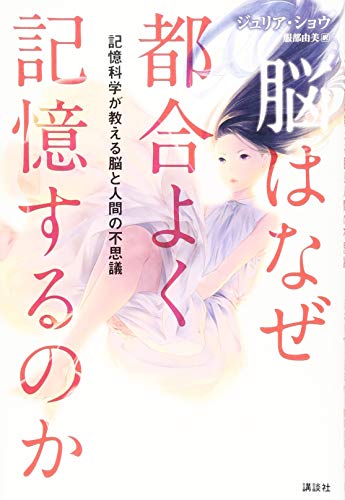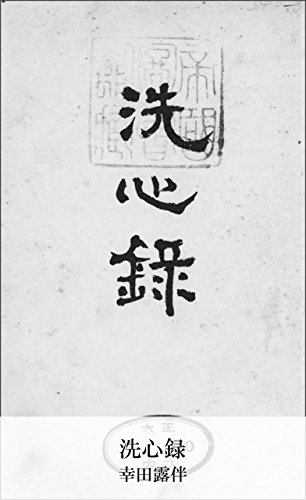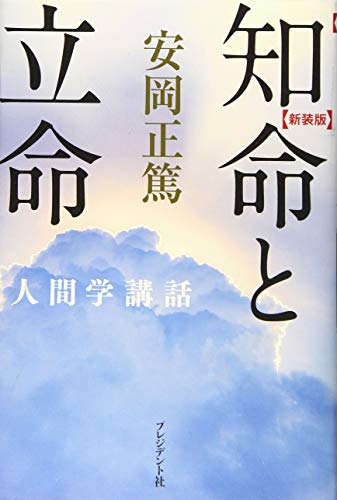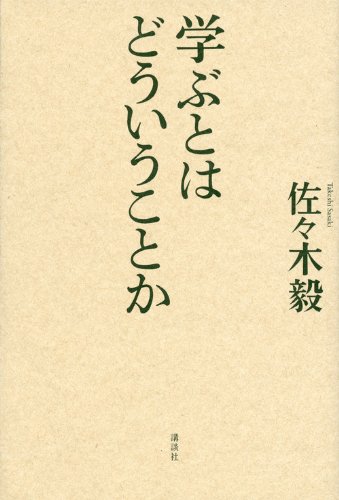まえがき
『いわゆる「心がけ」というものを、こうした言葉の力で培っていくのです。』
リスト
- 一、素志貫徹の事 …… 常に志を抱きつつ懸命に為すべきを為すならば、いかなる困難に出会うとも道は必ず開けてくる。成功の要諦は、成功するまで続けるところにある。
- 一、自主自立の事 …… 他を頼り人をあてにしては事は進まない。自らの力で、自らの足で歩いてこそ他の共鳴も得られ、知恵も力も集まって良き成果がもたらされる。
- 一、万事研修の事 …… 見るもの聞くことすべてに学び、一切の体験を研修と受けとめて勤しむところに真の向上がある。心して見れば、万物ことごとく我が師となる。
- 一、先駆開拓の事 …… 既成にとらわれず、たえず創造し開拓していく姿に、日本と世界の未来がある。時代に先がけて進む者こそ、新たな歴史の扉を開くものである。
- 一、感謝協力の事 …… いかなる人材が集うとも、和がなければ成果は得られない。常に感謝の心を抱いて互いに協力しあってこそ、信頼が培われ、真の発展も生まれてくる。
あとがき
まえがきは、藤井 孝一『ビジネススキル大全―――2時間で学ぶ「成果を生み出す」全技術』より。リスト項目は「塾是・塾訓・五誓」(松下政経塾)からの引用です。
本書では同じリストが松下 幸之助『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』からの引用として掲載されていました。
- タイトル: ビジネススキル大全―――2時間で学ぶ「成果を生み出す」全技術
- 著者: 藤井 孝一(著)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2016-07-15