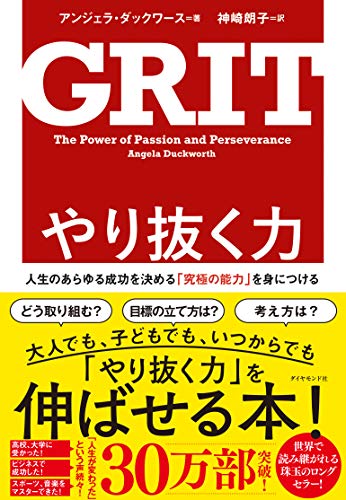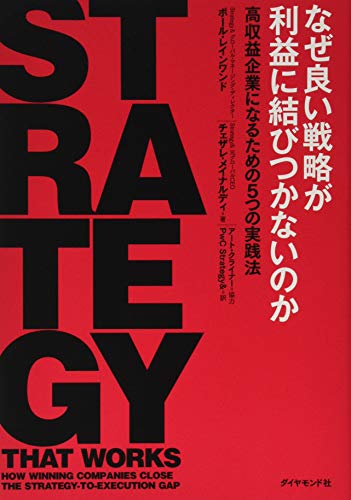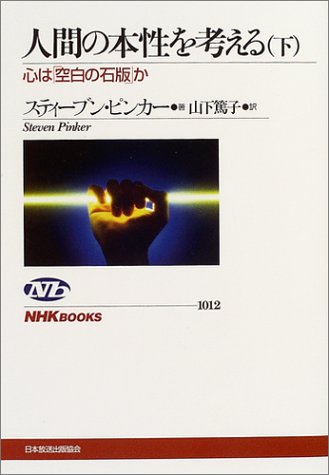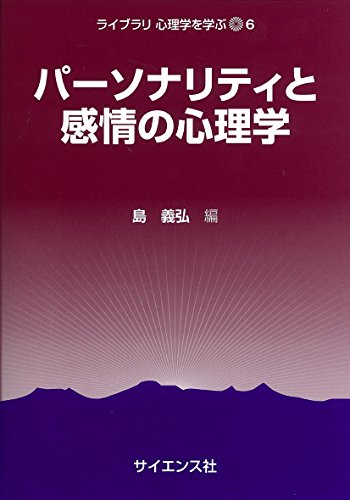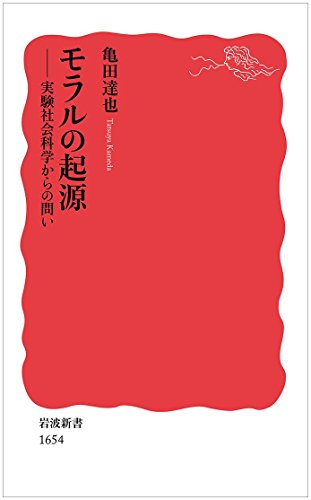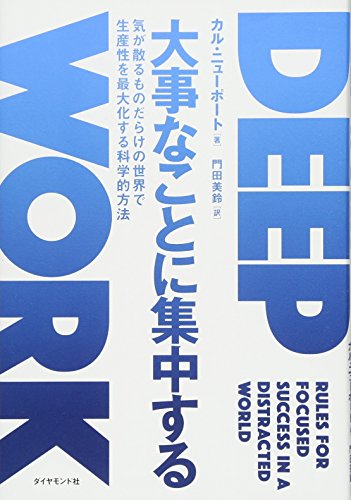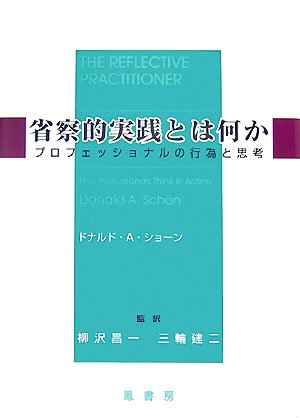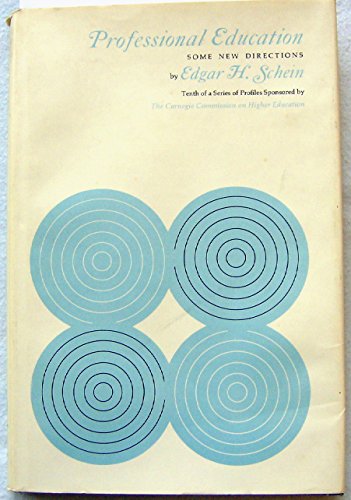まえがき
『あなたがいま何歳だろうと、「目的」の意識を育むのに早すぎることも、遅すぎることもない。そのために私から3つの提案がある。いずれも本章に登場した「目的」の研究者が勧めているアイデアだ。』
リスト
- いま自分のやっている仕事が、社会にとってどのように役立つかを考えてみる〈デイヴィッド・イェーガー〉
- いまの仕事がなるべく自分にとって一番大切な価値観につながるように、ささやかでも意義のある変化を起こしてみる〈エイミー・レズネスキー〉
- 目的を持った生き方の手本となる人物(ロールモデル)からインスピレーションをもらう〈ウィリアム・デイモン〉
あとがき
まえがきを含めて、アンジェラ・ダックワース『GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』(ダイヤモンド社、2016年)より。本文を編集・引用してリストを作成しました。文末の名前は、まえがきの『「目的」の研究者』です。
「目的」とカギカッコで括られているのは、これが一般名詞でなく本書で定義されている『「やり抜く力」を支える4つの特徴』の一つだから。
- タイトル: やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける
- 著者: アンジェラ・ダックワース(著)、神崎 朗子(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2016-09-09