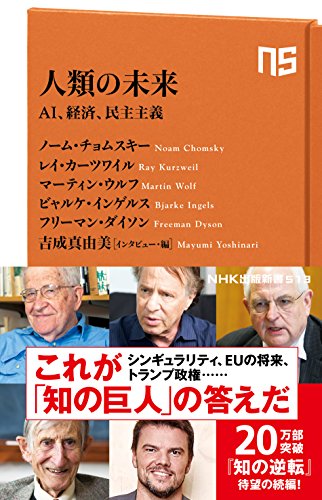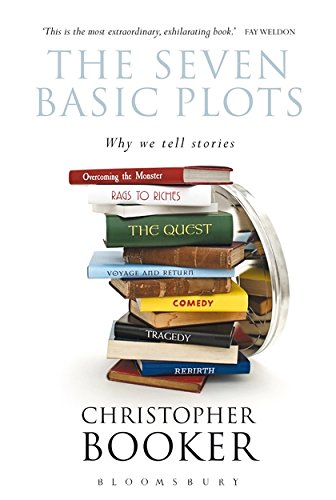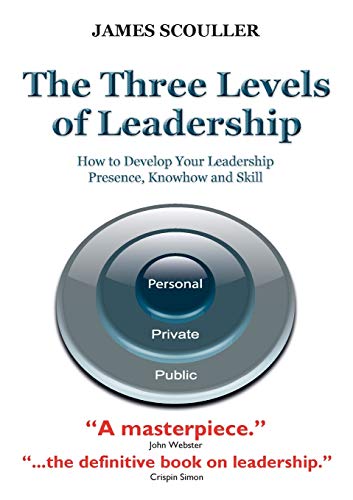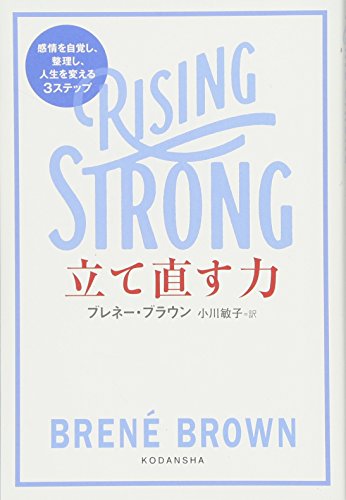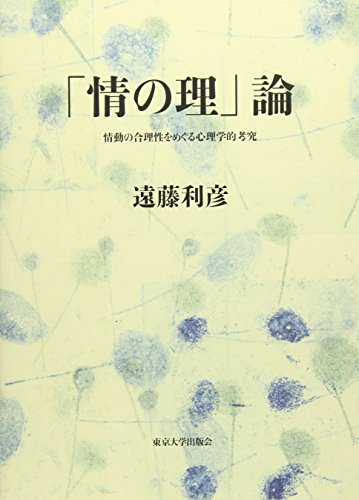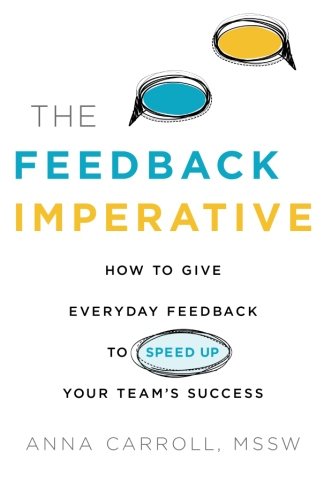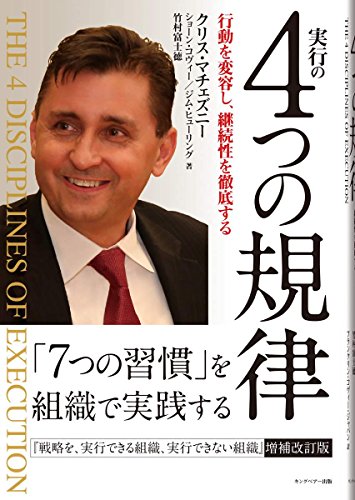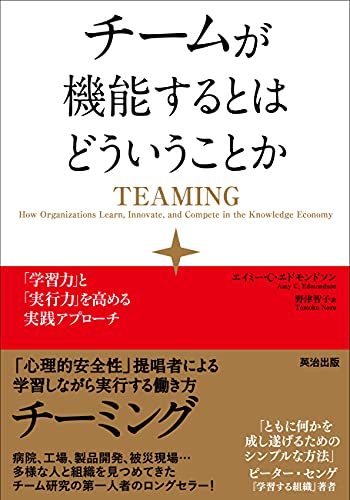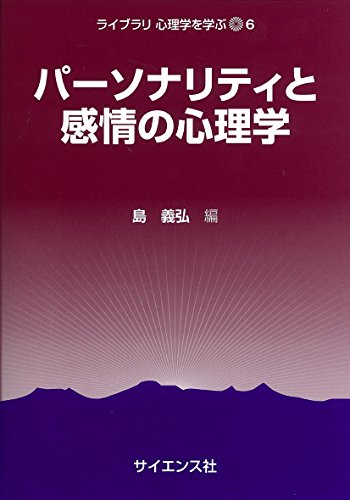まえがき
『4Cは、米国を中心とした Partnership for 21st Century Skills(P21) によって21世紀の教育に必要な最も重要なスキルとして特定された4つのスキルです。』
リスト
- 批判的思考 (Critical Thinking and Problem Solving)
- 創造 (Creativity and Innovation)
- コミュニケーション (Communication)
- 協働 (Collaboration)
あとがき
まえがきは “Four Cs of 21st century learning“(Wikipedia) からの翻訳・引用です。リストは “Framework for 21st Century Learning“(P21) からの翻訳・引用。参考文献(1)にも似たようなスキルセットの定義がいくつかありました。
『人類の未来―AI、経済、民主主義』という本で人間開発指数という指数の存在を知り、関連資料を読んでいたらこの4Cにぶつかりました。
- タイトル: 人類の未来―AI、経済、民主主義 (NHK出版新書 513)
- 著者: ノーム・チョムスキー(著)、レイ・カーツワイル(著)、マーティン・ウルフ(著)、ビャルケ・インゲルス(著)、フリーマン・ダイソン(著)、吉成真由美(編集)
- 出版社: NHK出版
- 出版日: 2017-04-11
この本からの他のリスト
参考文献
(1) “21st century skills“(Wikipedia)